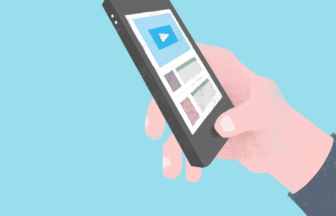プレミアムチケットから日用品まで|広がる転売ビジネスの闇
ある人気アーティストのコンサートチケットが発売から数分で完売しました。しかし、その直後からフリマサイトやオークションサイトには定価の5倍、10倍という価格でそのチケットが大量に出品されていました。これは、いわゆる「転売ヤー」による行為です。彼らは利益を得る目的だけで商品を買い占め、価格を吊り上げて再販売するのです。
転売問題は今やコンサートチケットやゲーム機だけの話ではありません。パンデミック時のマスクや消毒液、最近では人気の調味料やお菓子、さらには無印良品や特定メーカーの日用品まで、「人気がある」「品薄になりそう」と判断されたあらゆる商品が転売の対象になっています。SNSで話題になった商品が、翌日には店頭から姿を消し、オンラインマーケットで高額転売されるという光景は珍しくなくなりました。
組織化・効率化される転売ビジネスの手口
今日の転売ヤーたちは、かつてのような「たまたま入手した希少品を売る」という素人レベルではありません。彼らの多くは高度に組織化され、効率的なシステムを構築しています。
転売のプロフェッショナルは、発売情報を常に監視し、複数のクレジットカードや配送先を使い分け、購入制限を回避します。さらに、店舗の開店時間に合わせて行列を作る「並び屋」を雇ったり、オンライン購入を代行する「BOT」と呼ばれる自動購入プログラムを利用したりと、その手口は年々巧妙化しています。彼らにとって転売は立派な「ビジネス」であり、そのために必要なあらゆる手段を講じているのです。
転売がもたらす社会的損失と被害者

転売行為がもたらす悪影響は計り知れません。最も直接的な被害者は、本当にその商品を必要としている一般消費者です。例えば、子どもへのプレゼントとして人気ゲーム機を買おうとした親が、品切れのために諦めるか、定価の何倍もの金額を支払うかの選択を迫られるケースが後を絶ちません。
しかし、被害は消費者だけにとどまりません。メーカーや正規販売店も深刻な打撃を受けています。彼らは適正価格での販売を通じて顧客との信頼関係を構築しようとしていますが、転売ヤーの存在によってその努力が台無しになるケースも少なくありません。定価で買えないという不満が、ブランドイメージの低下につながることも懸念されます。
さらに見過ごせないのは文化的・社会的損失です。例えば、本当にアーティストのファンが、転売ヤーの買い占めによってコンサートに行けなくなるという事態は、文化体験の機会損失という点で社会的な問題と言えるでしょう。
法整備の進展と残された課題
こうした問題を受け、日本でも法整備が進みつつあります。2019年には「特定興行入場券の不正転売禁止法」が施行され、コンサートやスポーツイベントのチケット転売が規制されました。また、災害時の生活必需品の転売に対しては、特定商取引法や価格統制令による規制が可能です。
しかし、法規制にはまだ多くの抜け穴があります。例えば、一般の商品(ゲーム機やおもちゃなど)の転売は基本的に合法であり、また国外サイトを経由した転売規制は困難を極めます。さらに、法律があっても取り締まりのリソース不足という問題も指摘されています。
ある法律専門家は「現状の法規制は対症療法的で、転売ビジネスの本質的な問題に対処できていない」と指摘します。技術の進化に法整備が追いついていない現実があります。
1
2