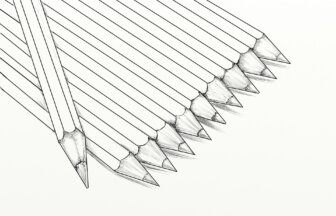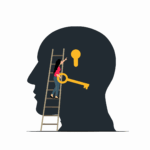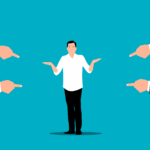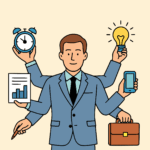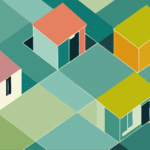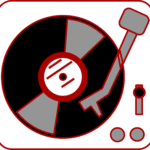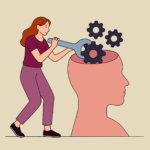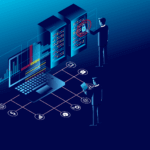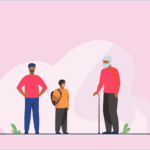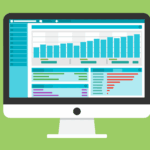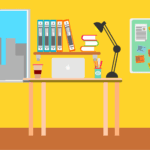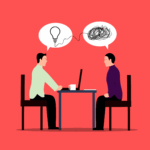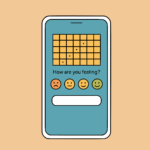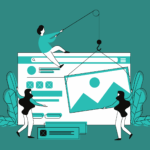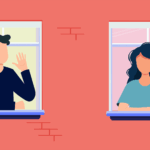6割の人が平均年収以下という衝撃の事実
日本で働く多くの人にとって、給与は生活の基盤であるのは言うまでもないが、最近発表されたデータが示す現実は、多くの人にとって厳しいものだった。日本の平均年収は約460万円とされているが、実に6割もの人がこの平均を下回る収入しか得ていないという事実が明らかになったのである。
これは日本社会の給与構造・社会的構造に深刻な歪みが生じていることを物語っている。なぜこのような現象が起こっているのか。そして、なぜ女性の年収は男性と比べて低い水準で推移し続けているのか。これらの疑問に対し考察し、給与格差の背景にある複雑な要因を詳しく分析していく。
平均値と中央値の違い|統計の罠が隠す給与の実態
給与格差を理解するうえで、まず押さえておかなければならないのが、平均値と中央値の違いである。多くの人が「平均年収460万円」という数字を聞いて、「自分の年収がそれより低いのは問題だ」と感じるかもしれない。しかし、この平均値という数字には大きな落とし穴がある。
平均値は、すべての人の年収を足し合わせて、その人数で割った値である。しかし、この計算方法には致命的な欠陥がある。極端に高い年収を得ている少数の富裕層が、全体の平均を大きく押し上げてしまうのである。例えば、年収300万円の人が9人いて、年収3000万円の人が1人いる場合、平均年収は570万円になってしまう。しかし、実際には10人中9人が平均以下という状況になるのである。
一方、中央値は全体を年収の高い順に並べたときの真ん中の値を指す。年収の中央値は約407万円であり、これは平均値の460万円よりも53万円も低い。この差が示すのは、日本の給与分布が正規分布ではなく、高収入層に偏った分布になっているということである。
この中央値こそが、一般的な働き手の実感により近い数字なのである。407万円という中央値を基準に考えれば、自分の年収がそれより低くても、決して異常なことではない。むしろ、平均値によって作られた「普通」という幻想から解放され、より現実的な視点で自分の立ち位置を把握できるようになる。
なぜ6割の人が平均以下なのか|給与分布の歪みを生む構造的要因
平均所得金額(547万5千円)以下の割合は 61.3%という厚生労働省のデータが示すように、6割以上の人が平均以下の収入しか得ていない。この現象は、日本の労働市場と企業の給与体系に深く根ざした構造的な問題から生まれている。
正規雇用と非正規雇用の格差拡大
まず考えなければならないのは、雇用形態の多様化がもたらした影響である。1990年代以降、日本企業は人件費削減と労働力の柔軟性確保を目的として、非正規雇用の比重を高めてきた。パートタイム、アルバイト、派遣社員、契約社員といった非正規雇用者の割合は、全労働者の約4割に達している。
正規雇用者と非正規雇用者の間には、時給ベースで見ても大きな格差が存在する。正規雇用者の場合、基本給に加えて各種手当、賞与、退職金、福利厚生などの恩恵を受けることができる。一方、非正規雇用者の多くは時給制であり、働いた時間分しか収入を得ることができない。さらに、昇進の機会も限られており、長期的な収入増加の見込みも少ない。
この格差は、単に雇用形態の違いというだけでなく、社会保障制度の設計とも密接に関係している。正規雇用者は厚生年金、健康保険、雇用保険などの社会保険に加入できるが、非正規雇用者の多くは国民年金、国民健康保険に加入することになり、将来的な保障水準にも差が生まれる。
企業規模による格差の固定化
日本の給与格差を語る上で見逃せないのが、企業規模による差である。大企業、中小企業、零細企業の間には、明確な給与格差が存在する。大企業では年功序列制度と終身雇用制度が比較的維持されており、勤続年数とともに着実に収入が増加する傾向がある。
しかし、中小企業や零細企業で働く人々は、そうした恩恵を受けにくい。資金力の限界から、大幅な昇給を行うことは困難であり、福利厚生制度も限定的である。さらに、業績の変動が直接的に給与に反映されやすく、収入の安定性にも課題がある。
この格差は、個人の能力や努力の差によるものではなく、どの規模の企業に就職するかという初期条件によって、その後の収入軌道が大きく左右されてしまう構造的な問題なのである。
業界による収益性の違い
業界間の収益性の違いも、給与格差を生む重要な要因である。金融業、情報通信業、電力・ガス業などの高収益業界では、従業員への還元も大きく、たばこ」(790万円)は、前年から123万円の大幅アップとなり、最も平均年収が増加した業種といったように、業界全体の業績向上が直接的に給与水準の上昇につながる。
一方、小売業、宿泊・飲食サービス業、介護・福祉業などの労働集約型産業では、人件費が収益に占める割合が高く、給与水準を大幅に引き上げることは困難である。これらの業界で働く人々の多くが、全体の平均を下回る収入となっているのが現実である。
女性の年収が変わらない理由|見えない壁が生み出すジェンダー格差

男性の年収が年齢とともに右肩上がりで増加する一方で、女性の年収は20代から横ばいで推移するという現象は、日本の労働市場における最も深刻な問題の一つである。令和3(2021)年の男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は75.2となっており、4分の1近い格差が存在している。
昇進機会の不平等|ガラスの天井の存在
女性は昇進しづらいこと。もう1つは、女性は昇進しても賃金スケールの下位の仕事に割り当てられやすく、男性ほどには賃金が上がらないという研究結果が示すように、女性が直面する問題は二重構造になっている。
まず、昇進機会そのものが男性に比べて限られているという問題がある。これは、長時間労働を前提とした日本の労働慣行と密接に関係している。管理職になるためには、残業や休日出勤を厭わない姿勢が評価される傾向があり、家庭責任を担うことが多い女性にとって、そうした働き方を続けることは現実的ではない。
さらに、昇進したとしても、男性と同等の昇給を得られないという問題もある。女性管理職の多くが、人事や総務といった間接部門に配置される傾向があり、売上に直結する営業や事業企画といった部門での管理職経験を積む機会が限られている。この結果、同じ管理職でも給与水準に差が生まれてしまうのである。
出産・育児による キャリア中断の影響
女性の年収が変わらない最も大きな要因の一つが、出産・育児によるキャリアの中断である。日本では、第一子出産を機に約半数の女性が退職するという統計があり、一度キャリアを中断すると、復職時に元の給与水準を維持することは困難である。
育児休業制度は整備されているものの、休業中は無給または減額された給付金のみとなるため、同世代の男性との収入格差は拡大する一方である。さらに、復職後も時短勤務を選択する女性が多く、フルタイムで働く男性との間で労働時間の差が生まれることも、年収格差の要因となっている。
また、子育て期間中は、残業や出張が困難になることが多く、昇進の機会を逃しやすくなる。これにより、20代で男性と同等だった年収が、30代、40代と年齢を重ねるごとに差が開いていく構造が生まれている。
性別役割分担意識の根強い影響
日本社会に根強く残る「男性は仕事、女性は家庭」という性別役割分担意識も、女性の年収が上がりにくい要因となっている。多くの企業で、無意識のうちに「女性は結婚や出産で辞める可能性が高い」という偏見を持たれ、重要なプロジェクトや昇進コースから外されることがある。
この問題は、統計的差別と呼ばれる現象でもある。個人の能力や意欲に関係なく、女性というカテゴリーに属することによって、キャリア形成の機会が制限されてしまうのである。こうした差別は、しばしば無意識に行われるため、被害者も加害者も気づかないうちに格差が拡大していく。
グローバル視点で見る日本の給与格差|世界との比較で浮かび上がる問題
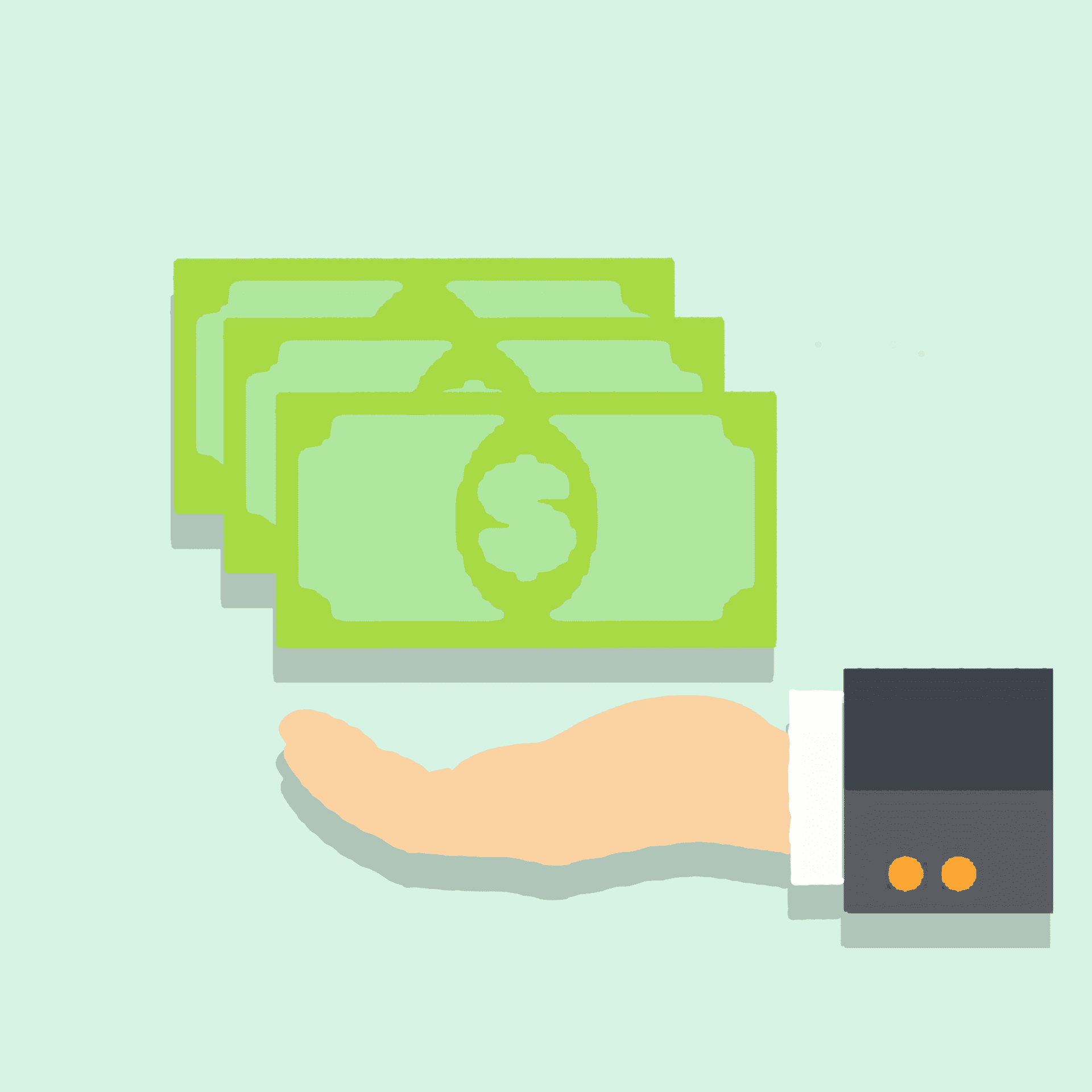
日本の給与格差問題を正しく理解するためには、国際的な視点からの分析も必要である。男女間の賃金格差は韓国が34.6%、日本が24.5%。欧米諸国が10%台なのに対して2国だけ突出しているという事実は、日本の問題が他の先進国と比べても深刻であることを示している。
1
2