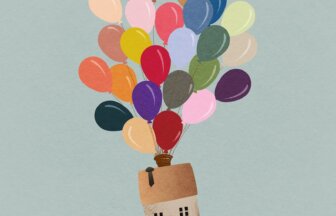売り手市場で気が触れたか?|就活面接のありえない思考
「短所、ハラスメント」という言葉が目に入ってきた。「あなたの短所は何ですか?」という質問が、ハラスメントとして認識されたという事象である。ふと日経新聞の最近の記事を見ると、面接や就活などの場で短所を聞くことは「仕事の役に立たない」という理由から、やめるべきだというような主張があったという。
しかし、この考え方は本当に正しいのだろうか。企業と求職者の双方にとって実りある採用プロセスを考えるとき、このような「防衛的思考」は行き過ぎていないだろうか。本記事では、就活面接における短所を問う質問の意義を再考し、近年の過剰な防衛思考がもたらす問題について論じていきたい。ただし、この事象は全ての就活生や人事担当者の賛同を得られるとは思っていない。最終的に危惧するのは、企業と社員双方の成長における原理原則に逆行する風潮ではないかと考えるに至る。
面接における「短所」の質問の本質的価値
人間性の多角的理解のために不可欠な質問
面接はスキルチェックの場ではない。それは人と人との出会いであり、共に働く可能性のある相手の人間性を理解するための貴重な機会である。企業側が「短所は何か」と尋ねるとき、そこには欠点を探り出そうという悪意はない。むしろ、その人がどのように自己認識しているか、自分の弱みをどう捉え、どう向き合っているかを知りたいという意図がある。
人間に完璧な人などいない。誰しも長所と短所を持ち合わせている。その両面を理解することなく、人を本当に知ることはできない。長所だけを聞いて採用を決めることは、まるで商品のカタログだけを見て高額な買い物をするようなものだ。実際に手に取り、あらゆる角度から確かめて初めて、その価値を正しく判断できる。至極当たり前な質問であると考える。
ミスマッチ防止の観点からの必要性
就職のミスマッチは、企業にとっても求職者にとっても大きな損失となる。採用後に「思っていた人材と違った」「想像していた職場環境と違った」という事態は、双方に時間と労力の無駄をもたらす。このミスマッチを防ぐためには、採用段階で互いをできるだけ深く理解することが不可欠である。
短所を聞くことは、その人が職場環境にうまく適応できるかを予測する上で重要な手がかりとなる。例えば、「細かいことに神経質になりすぎる」という短所は、精密さが求められる業務では長所にもなり得るが、スピードが求められる環境では足かせになるかもしれない。このような情報は、適材適所の人員配置を考える上でも極めて価値がある。
成長可能性の見極め
さらに、短所についての質問への回答は、その人の成長意欲や自己啓発の姿勢を知る手がかりにもなる。自分の弱みを認識し、それを克服するために何をしているか、または何をしようとしているかは、その人の将来性を占う重要な要素である。
「完璧を求めすぎて仕事が進まないことがあります。そのため、現在は『完璧よりも完了』を意識して、まずは形にすることを心がけています」といった回答は、短所を述べるだけでなく、それに対する対処法や改善への取り組みを示している。このような回答からは、その人の内省力や課題解決能力が垣間見える。
防衛思考の行き過ぎがもたらす弊害
本音と建前の乖離を助長する社会
表面的な良い面だけを見せ合う関係は、真の信頼関係とは言えない。互いの弱みも含めて受け入れ合うことができて初めて、強固な人間関係が築ける。企業と従業員の関係も同様である。互いの強みも弱みも理解した上で、それを補い合いながら成長していく―そんな健全な関係こそが、長期的な発展につながるのではないだろうか。
現実逃避的思考の蔓延
近年、不快な現実や困難から目を背けようとする思考が社会に広がっている。SNSではポジティブな情報ばかりが共有され、批判的な意見は「ネガティブ」というレッテルを貼られがちだ。しかし、成長には時として厳しい現実と向き合うことが必要である。
面接で短所を問うことを忌避する風潮も、この現実逃避的思考の一環と見ることができる。自分の弱みと向き合うことを避け、常に肯定的な側面や、当たり障りのない時間でありたいという願望が、「短所を聞くのはハラスメント」という主張につながっているのではないだろうか。しかし、弱みを隠すことは決して強さではない。むしろ、弱みを認識し、それを克服しようとする姿勢こそが真の強さである。
過保護による成長機会の喪失
過保護は時として最大の害悪となる。子育てにおいても、過度に子どもに気を遣ったり、優位性を持たせることで、子どもが困難に立ち向かう力を身につける機会を奪ってしまうこともあるだろう。同様に、面接における厳しい質問を排除することは、求職者から重要な成長機会を奪うことにつながりかねない。
「短所は何か」と問われて自己分析し、それを適切に言語化する経験は、自己理解を深め、コミュニケーション能力を高める貴重な機会である。この機会を「ハラスメント」という名目で奪うことは、若者のキャリア形成にとって決して有益ではない。
1
2