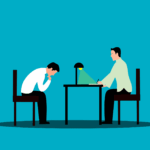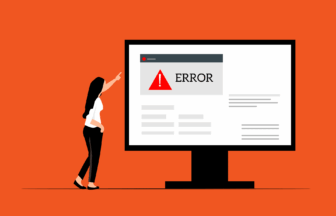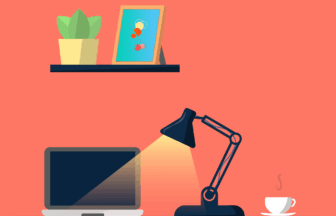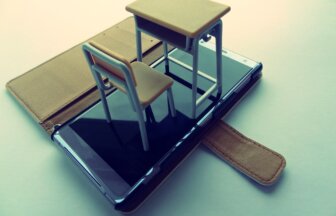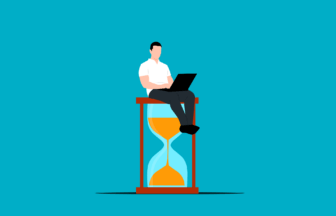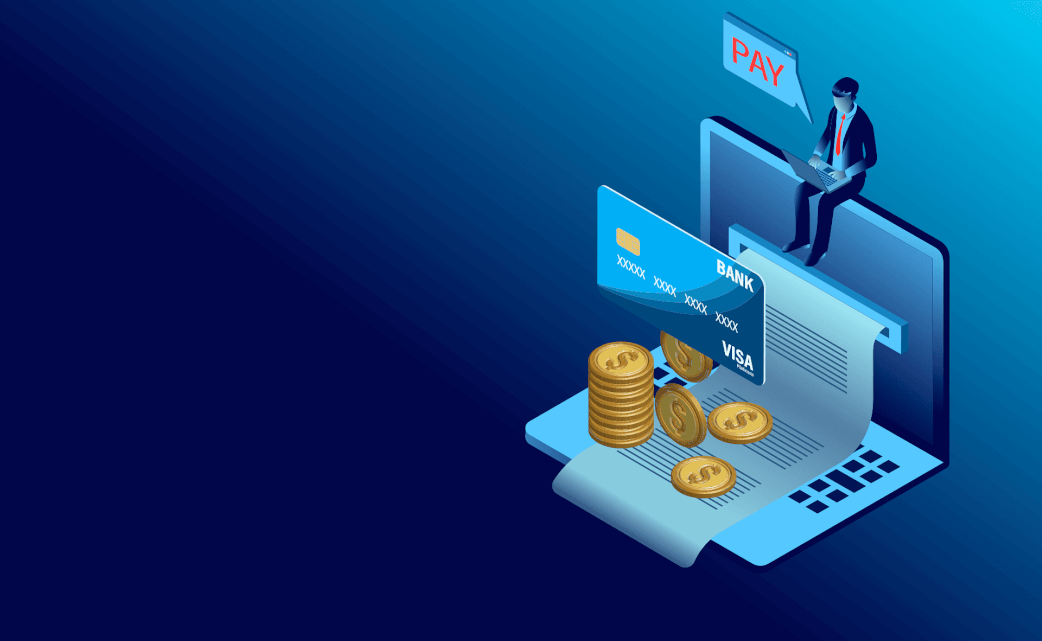
お金は「道具」である―その本質を理解する第一歩
「お金があれば幸せになれる」「お金がないと何もできない」。私たちは日常的にこうした言葉を耳にするが、果たしてお金とは本当にそのような存在なのだろうか。実は、お金というものを正しく理解している人は驚くほど少ない。多くの人がお金を「目的」だと勘違いしているが、お金の本質は「道具」なのである。
例えば、ハンマーという道具を考えてみよう。ハンマーそのものに価値があるわけではない。ハンマーは釘を打つため、何かを組み立てるため、つまり「目的を達成するための手段」として価値を持つ。お金もまったく同じである。お金は、私たちが本当に欲しいもの、本当にやりたいこと、本当に大切にしたい人生を実現するための「道具」に過ぎない。
この根本的な理解がないまま大人になると、人生の多くの時間を「お金を稼ぐこと」だけに費やし、何のためにそのお金を稼いでいるのか見失ってしまう。道具であるお金が、いつの間にか人生の主役になってしまうのだ。これは、まるでハンマーを集めることが目的になってしまい、本来作りたかったものを忘れてしまうようなものである。
マネーリテラシーの欠如が招く「見えない損失」
マネーリテラシーとは、お金に関する知識と判断力のことを指す。これが欠けていると、人生において計り知れない損失を被ることになる。しかも、その損失の多くは「見えない損失」であるため、本人が気づかないまま何十年も過ごしてしまうのだ。
まず考えてほしいのは、複利という概念である。アインシュタインが「人類最大の発明」と呼んだとされる複利の力を理解していない人は、若いうちから資産形成を始める機会を逃してしまう。例えば、20歳から毎月2万円を年利5%で運用した場合、40年後には約3,000万円になる。しかし、これを30歳から始めた場合、同じ条件でも約1,800万円にしかならない。たった10年の差が1,200万円もの違いを生むのだ。
この差は単なる金額の問題ではない。この1,200万円があれば、老後の生活に余裕が生まれ、子供や孫への教育投資ができ、自分がやりたかったことに挑戦できる。つまり、マネーリテラシーの欠如は、人生の選択肢そのものを奪ってしまうのである。
深刻な社会問題として挙げられているのが、詐欺や悪質な金融商品に引っかかるリスクである。日本では毎年、数千億円規模の特殊詐欺被害が発生している。「絶対に儲かる」「元本保証で高利回り」といった甘い言葉に騙されてしまうのは、基本的なマネーリテラシーが欠けているからだ。金融の世界には「ハイリターン・ハイリスク」という鉄則があり、リスクなしに高いリターンを得られることなど存在しない。この原則を知らないだけで、一生かけて貯めた財産を一瞬で失う可能性があるのだ。
「稼ぐ」「使う」「貯める」「増やす」「守る」―お金の5つの機能
マネーリテラシーを身につけるには、お金の5つの機能を理解することが不可欠である。多くの人は「稼ぐ」ことばかりに注目するが、それだけでは十分ではない。
「稼ぐ」。これは自分の時間、スキル、知識、労働力を価値に変換する行為だ。しかし、ここで重要なのは、時給思考から脱却することである。時給1,000円で働く人と時給5,000円で働く人の違いは何か。それは提供している価値の大きさであり、その価値を生み出すために身につけたスキルや専門性の差なのだ。
「使う」。お金を使うことは決して悪いことではない。むしろ、経済を回し、自分の人生を豊かにするために必要な行為である。問題は「消費」「浪費」「投資」の区別ができていないことだ。生活に必要なものを買うのが消費、その場の感情で不要なものを買うのが浪費、将来の自分の価値を高めるために使うのが投資である。書籍を買って知識を得ることは投資だが、読まずに積んでおけば浪費になる。この違いを理解せずに使っていると、いくら稼いでもお金は貯まらない。
「貯める」。これは将来の不確実性に備えるための行為だ。病気、失業、災害、予期せぬ出費は誰にでも起こりうる。緊急時に使える資金がなければ、高金利のローンに頼るしかなく、さらに状況が悪化する。一般的には、生活費の3〜6ヶ月分を貯蓄しておくことが推奨されている。これは「守りの資産」であり、安心して人生に挑戦するための基盤となるのだ。
「増やす」。である。ただ貯めるだけでは、インフレによって実質的な価値が目減りしていく。日本は長らくデフレが続いたが、世界的に見ればインフレが普通であり、今後の日本でもインフレが進む可能性は高い。お金を銀行に預けているだけで満足していると、物価が上がる分だけ購買力が下がってしまう。だからこそ、株式、債券、不動産、投資信託などを通じて資産を増やす知識が必要になるのだ。
「守る」。せっかく築いた資産を詐欺や不適切な投資、過度なリスクテイクで失わないようにする知識が必要だ。また、税金や社会保険制度を理解し、合法的に節税することも「守る」に含まれる。例えば、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用すれば、運用益が非課税になるため、同じ運用成績でも手元に残る金額が大きく変わってくる。
子供時代に身につけるべき「お金の感覚」

マネーリテラシーは、できるだけ早い段階から身につけるべきである。なぜなら、お金に対する感覚や習慣は、子供時代の経験によって大きく形成されるからだ。
「お金は無限ではない」という現実を理解することである。子供のころ、欲しいものをすぐに買ってもらえた人と、お小遣いをやりくりしながら計画的に貯めて買った人では、大人になってからのお金の使い方がまったく違ってくる。後者は「選択と集中」という重要な概念を体で学んでいるのだ。すべてを手に入れることはできないからこそ、本当に欲しいものを選び、そのために我慢する。この経験が、大人になってからの計画性と自制心につながる。
次に、「お金は労働の対価である」という認識も重要だ。お年玉やお小遣いとして何もせずにもらうお金と、お手伝いや勉強など何かをした対価として得るお金では、その価値の感じ方が異なる。自分で稼いだお金は、より慎重に、より大切に使うようになる。この感覚は、将来仕事をするときの責任感や、お金を稼ぐことの大変さを理解する基礎となるのだ。
さらに、「遅延報酬」の概念を学ぶことも極めて重要である。有名な「マシュマロ実験」では、目の前のマシュマロを15分我慢できた子供は、将来的に学業成績が良く、社会的にも成功しやすいという結果が出ている。これは自制心の問題であり、お金の世界では「今すぐ使いたい欲求を抑えて、将来のために貯蓄・投資する」という形で現れる。若いうちからこの感覚を身につけておくと、衝動買いや浪費を避け、長期的な視点でお金を扱えるようになる。
お金が生み出す「時間」という最大の資産
お金の本質を語るうえで、絶対に触れなければならないのが「時間」との関係である。実は、お金と時間は表裏一体の関係にあり、人生において最も重要な資産は時間なのだ。
「時は金なり」という言葉があるが、これは単に時間を無駄にするなという意味ではない。もっと深い意味がある。若いころに適切にお金を蓄え、増やしておけば、将来、自分の時間を買い戻すことができるのだ。
例えば、40代で十分な資産を築いた人は、週4日勤務にして家族との時間を増やすことができる。あるいは、好きなことを仕事にするために収入が下がっても生活できる。定年まで我慢して働き続けなくても、早期退職して第二の人生を始められる。これらはすべて、若いころからマネーリテラシーを持って資産形成をしてきた人だけが得られる選択肢である。
逆に、金融リテラシーがないまま過ごすと、一生お金のために働き続けなければならない。60代、70代になっても生活費のために働かざるを得ない状況は、決して珍しくない。体力も気力も衰えた状態で、選択の余地なく働き続けることほど辛いことはないだろう。
さらに考えるべきは、お金は時間を「圧縮」する力も持っているということだ。例えば、通勤に片道1時間半かかる安い家に住むか、会社の近くの少し高い家に住むかという選択がある。後者を選べば、毎日3時間、年間で約1,000時間を自由時間として取り戻せる。この時間を読書、スキルアップ、家族との団らん、趣味に使えば、人生の質は劇的に向上する。
つまり、適切なお金の使い方とは、時間を買うことでもあるのだ。食洗機やロボット掃除機を買うことは一見贅沢に見えるかもしれないが、それによって生まれた時間で自己投資ができれば、長期的には大きなリターンを生む。マネーリテラシーがある人は、こうした「時間対効果」を常に考えながらお金を使っているのだ。
1
2