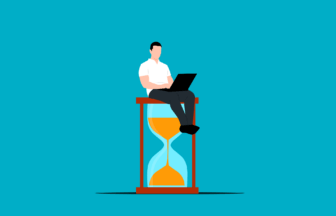採用にかけた時間とコストが水の泡になる瞬間、それは新入社員が数ヶ月で退職を申し出た時である。企業の人事担当者にとって、早期離職は頭を悩ませる大きな課題だ。
すぐに辞めてしまう社員にはいくつかの特徴や傾向が存在する。それらを理解することで、採用段階でのリスクを減らし、ミスマッチを防ぐことが可能になるのだ。本コラムでは、早期離職しやすい社員の特徴を10項目にわたって深掘りし、企業側が取るべき対策や見極め方についても詳しく解説していく。
1. 理想と現実のギャップに耐えられない完璧主義者
すぐに辞める社員の第一の特徴として挙げられるのが、過度な完璧主義の傾向である。彼らは就職活動中に企業のホームページや採用パンフレットに描かれた理想的な職場環境を信じ込み、入社前に頭の中で完璧な職場像を作り上げてしまう。
ところが実際に働き始めると、どんな優良企業でも多かれ少なかれ泥臭い業務や非効率な慣習、人間関係の摩擦といった「現実」が存在する。完璧主義者はこうした小さな瑕疵を許容できず、「こんなはずではなかった」という失望感に支配されてしまうのだ。
特に注意すべきなのは、面接時に企業に対して過度に理想化された質問をする候補者である。「御社では全員が目標に向かって一丸となって働いているのですか」「職場の人間関係は完璧ですか」といった、現実離れした完璧さを求める質問は、その人の期待値の高さを示すサインかもしれない。
採用時の見極めポイントとしては、過去の経験について質問した際に、困難やトラブルをどう乗り越えたかという「プロセス」ではなく、「結果」だけを語る傾向がないか観察することだ。失敗談や挫折経験を前向きに語れる人材は、現実とのギャップにも柔軟に対応できる可能性が高い。
2. 自己評価と市場価値のズレが大きい自信過剰タイプ
早期離職者の中には、自分の能力や市場価値を実際よりも遥かに高く見積もっている人材が少なくない。こうした自信過剰タイプは、入社後に任される業務のレベルや給与、ポジションが自分の期待に届かないと感じると、すぐに「自分の実力が正当に評価されていない」と結論づけてしまう。
実際には、どんなに優秀な人材でも入社当初は業界知識や社内システムの理解が不足しており、一定期間の学習期間が必要である。しかし自己評価が高すぎる人材は、この当然のプロセスを「不当な扱い」と受け取り、より良い条件を求めて短期間で転職を繰り返すパターンに陥りやすい。
面接時にこのタイプを見極めるには、具体的な実績について深掘りすることが有効だ。「このプロジェクトで成功した要因は何か」と尋ねた時に、チームの貢献や環境要因に言及せず、すべてを自分の手柄として語る候補者は要注意である。また、前職での評価や給与について質問した際に、不満を露わにしたり、「自分はもっと評価されるべきだった」という発言が多い場合も、同様のリスクがある。
健全な自信と過剰な自己評価の境界線を見極めることは難しいが、謙虚さと成長意欲のバランスが取れているかどうかが重要な判断基準となる。
3. 承認欲求が強すぎて些細なことで傷つきやすい人
現代社会において承認欲求の強さは珍しいものではないが、それが過度になると職場での継続性に悪影響を及ぼす。すぐに辞める社員の中には、上司や同僚からの頻繁な称賛や感謝の言葉を常に求め、それが得られないと自己価値を見失ってしまうタイプが存在する。
職場は学校のように毎日評価やフィードバックをもらえる環境ではない。上司は複数の部下を抱え、多忙な日々の中で一人ひとりに細やかな声かけをする余裕がないことも多い。承認欲求が強すぎる人材は、こうした「当たり前の職場環境」を「自分が認められていない証拠」と解釈し、モチベーションを急速に失ってしまう。
さらに問題なのは、小さな注意や建設的なフィードバックさえも個人攻撃と受け取り、深く傷ついてしまう点である。上司が業務改善のために「次回はこうしてみたらどうか」と助言しただけで、「自分は能力がないと思われている」と極端に落ち込み、退職を考え始めるケースも少なくない。
採用面接では、過去の職場や学校での評価について質問してみると良い。他者からの評価を過度に気にする発言が多い場合や、SNSでの「いいね」の数や周囲の反応について頻繁に言及する場合は、承認欲求の強さを示すサインかもしれない。また、「あなたの強みは何か」という質問に対して、自分自身の内的な基準ではなく、「周りからこう言われる」という他者評価ばかりを語る候補者も注意が必要である。

4. 忍耐力と継続力に欠ける飽きっぽい性格
すぐに辞める社員の特徴として見逃せないのが、物事を継続する力の欠如である。彼らは新しいことに挑戦する初期の興奮や刺激を求めるが、業務がルーティン化したり、地道な努力が必要な局面に入ると急速に興味を失ってしまう。
どんな仕事にも、華やかな部分と地味な部分が存在する。マーケティング職であってもデータ入力や報告書作成といった単調な業務は避けられないし、クリエイティブ職でも細かな修正作業の繰り返しは日常茶飯事だ。しかし飽きっぽい性格の人材は、こうした「地味だが必要な業務」に価値を見出せず、「こんなつまらない仕事をするために入社したわけではない」と不満を募らせる。
このタイプの人材は、職歴を見るとわずか数ヶ月から1年程度の短期間で複数の職場を転々としている傾向がある。また、趣味や習い事についても、様々なことに手を出すが長続きしないパターンが多い。
面接時には、過去の経験について「最も長く続けたこと」や「困難な時期をどう乗り越えたか」を具体的に質問することが効果的だ。すぐに成果が出ない時期をどう過ごしたか、単調な作業をどのようにモチベーションを保って続けたかといった質問に対して、具体的で説得力のある回答ができるかどうかが判断材料となる。
5. 主体性がなく指示待ち体質が染み付いている人
早期離職者の中には、驚くほど主体性に欠け、すべてを手取り足取り教えてもらわなければ動けない指示待ち体質の人材がいる。学生時代から受け身の姿勢が染み付いており、社会人になっても「誰かが教えてくれるのが当然」という意識から抜け出せないのだ。
新人に対して丁寧な研修期間を設ける企業は多いが、その後は自分で考え、必要な情報を自ら取りに行く姿勢が求められる。ところが指示待ち体質の人材は、詳細な指示がないと動けず、不明点があっても自分から質問せず、結果として業務が滞ってしまう。
さらに問題なのは、このタイプは「教えてくれない会社が悪い」「サポート体制が整っていない」と他責思考に陥りやすい点である。自分の受け身姿勢が問題だとは認識せず、環境のせいにして早期離職を選んでしまうのだ。
採用時の見極めには、過去の経験で「自分から何かを始めた」「課題を見つけて改善した」といった主体的な行動の実例を具体的に語れるかどうかが重要だ。また、面接の最後に「何か質問はありますか」と尋ねた際に、準備してきた表面的な質問しかできない、あるいは全く質問がない候補者は、主体性の欠如を示している可能性がある。逆に、面接中の会話から発展させた深い質問ができる人材は、自ら考え行動できる素質を持っている証拠である。
6. コミュニケーション能力が低く人間関係を構築できない
職場での人間関係は、仕事の満足度や継続性に大きな影響を与える要素である。すぐに辞める社員の中には、基本的なコミュニケーション能力が不足しており、同僚や上司との良好な関係を築けない人材が少なくない。
このタイプは、報告・連絡・相談といったビジネスの基本ができていないことが多い。問題が発生しても一人で抱え込んでしまい、手遅れになってから発覚するケースや、逆に些細なことでも過剰に相談し、自分で判断する力がないパターンもある。また、チームワークを必要とする業務において、自分の役割や責任を理解せず、周囲との連携が取れないことで孤立してしまう。
人間関係がうまく構築できないと、職場に居場所がないと感じ、疎外感や孤独感が募っていく。その結果、「この会社は自分に合わない」「職場の雰囲気が悪い」という結論に至り、退職を選択してしまうのだ。
面接時には、チームでの経験について具体的に質問することが有効である。「チームで取り組んだプロジェクトで、あなたはどんな役割を果たしたか」「意見の対立があった時にどう対処したか」といった質問に対して、自分の行動や考えを具体的に説明できるかどうかを確認したい。また、面接中の受け答えにおいて、質問の意図を正確に理解しているか、適切な長さと内容で回答できているかといった基本的なコミュニケーション能力も重要な判断材料となる。
1
2