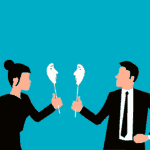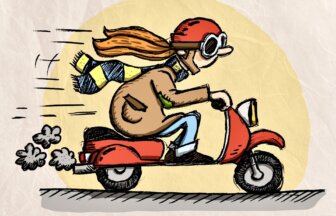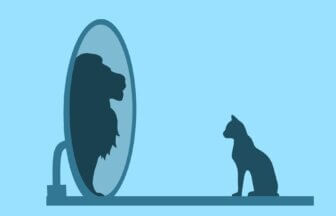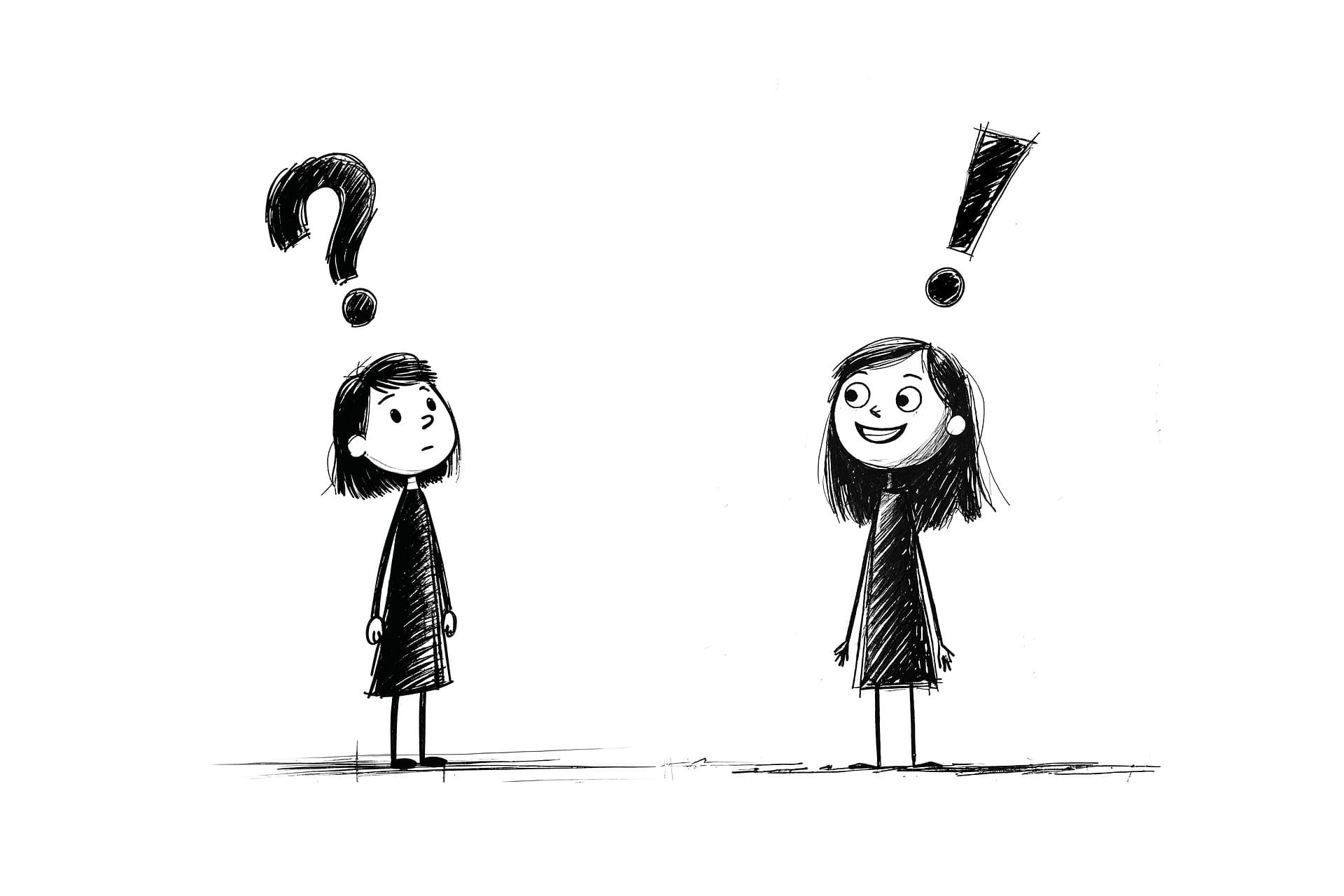
混沌とした現代を生き抜くために
ビジネスの世界でも日常生活においても、私たちは常に人間関係に囲まれています。取引先の担当者、採用候補者、新しい友人や恋人など、さまざまな場面で人との関わりが生じます。そんな中で「人を見抜く力」は、成功と失敗を分ける重要なスキルとなります。
今回の記事では、人を見抜く力がなぜ重要なのか、そしてどのようにして養うことができるのかについて、科学的根拠と実践的なアプローチから詳しく解説します。
人を見抜く力がないと直面する7つの困難
1. 詐欺や騙しの被害者になりやすい
信頼性の低い人物を見抜けないと、巧妙な詐欺の標的になることがあります。2023年の国民生活センターの調査によれば、詐欺被害に遭った人の約65%が「相手の言葉を信じてしまった」と回答しています。人を見抜く力は、自分自身を守るための防御壁となります。
2. ビジネスにおける判断ミス
取引先や協業相手の本質を見抜けないと、契約不履行や期待外れのサービス提供など、ビジネス上の損失につながります。東京商工リサーチの調査では、企業間トラブルの約40%が「相手企業の実態把握の不足」に起因しているとされています。
3. 採用ミスによる組織への悪影響
人事担当者が応募者の資質や人間性の見極めができないと、組織文化に合わない人材や、能力不足の人材を採用してしまう恐れがあります。一人の採用ミスが引き起こす損失は、その人の年収の1.5〜3倍にもなるという調査結果もあります。
4. 有害な人間関係に巻き込まれる
プライベートでも、悪影響を及ぼす人物を早期に見抜けないと、精神的なストレスや時間の浪費など、様々な負担を強いられることになります。心理学の研究では、有害な人間関係がメンタルに与える影響は、喫煙や肥満よりも深刻であるとされています。
5. 意図的に利用される危険性
自己中心的な人物や操作的な性格の持ち主は、他者を利用することで自分の利益を追求します。そうした人の本性を見抜けないと、知らず知らずのうちに利用され、損害を被ることになります。
6. 信頼関係の構築が困難になる
人を見る目がないと、誰を信頼すべきか判断できず、健全な信頼関係の構築が難しくなります。その結果、必要以上に警戒心を抱いたり、逆に無防備になったりと、バランスを欠いた人間関係に陥りがちです。
7. キャリアの停滞やチャンスの喪失
ビジネスの世界では、優れたメンターや協力者を見出す能力も重要です。人を見抜く力が不足していると、成長につながる出会いや機会を逃してしまうことがあります。
人を見抜く力を養う7つの方法

では、どうすれば人を見抜く力を養うことができるのかを考えてみます。
◾️観察力を磨くー言動の一貫性に注目する
人を見抜くためには、まず観察力を高めることが重要です。特に注目すべきは「言動の一貫性」です。人は自分の本質と異なる行動を長期間維持することは難しいため、発言と行動の矛盾を見逃さないことが大切です。
例えば、「チームワークを大切にしている」と主張する人が、実際の会議では他者の意見を遮ったり、功績を独り占めしたりする様子が見られれば、その不一致に注目すべきです。
著名な行動心理学者のポール・エクマン博士の研究によれば、人は嘘をつくとき、微妙な表情の変化(マイクロエクスプレッション)を示すことがあります。これらのサインを読み取る訓練をすることで、相手の真意を把握する能力が向上します。
・会話中の表情や身振り、声のトーンなど非言語的コミュニケーションに注意を払う
・人の言葉と行動の一貫性を意識的にチェックする習慣をつける
・初対面の印象だけでなく、時間をかけて相手の行動パターンを観察する
◾️傾聴スキルを向上させるー相手の価値観を理解する
真の傾聴には、単に言葉を聞くだけでなく、その背後にある価値観や動機を理解することが含まれます。人は会話の中で、意識せずに自分の優先事項や価値観を表現しています。
例えば、「成功」という言葉を使うとき、ある人は金銭的な利益を意味し、別の人はワークライフバランスや社会的影響力を指すかもしれません。こうした微妙な違いを捉えることで、相手の本質に迫ることができます。
効果的な傾聴が行われると、話し手は無意識のうちにより多くの情報を開示する傾向があることと言われています。つまり、良い聞き手になることで、相手の本質を見抜くための情報が自然と集まるのです。
・相手の話を遮らず、質問よりも理解に焦点を当てる
・「なぜそう思うのですか?」といった開かれた質問を活用する
・相手の言葉の選択や強調点に注意を払い、背後にある価値観を探る
◾️パターン認識力を高めるー状況を横断して分析する
人の本質は、色々な状況での行動パターンから浮かび上がります。例えば、ストレス下での反応、権力との関わり方、弱者への態度など、異なる文脈での行動を観察することで、より正確な人物像が見えてきます。
ハーバード大学の社会心理学者であるエイミー・カディ教授の研究によれば、人は権力や地位のある人に対する態度と、サービス業の従業員など「下」と認識される人への態度に大きな差がある場合、それはその人の本質を示す重要なサインとなります。
・相手が異なる状況(仕事場、社交の場、ストレス下など)でどう振る舞うかを観察する
・権力関係の非対称な場面(上司との会話、サービス業の人との対応)での態度の違いに注目する
・長期的な行動パターンを記録し、一時的な感情反応と区別する
1
2