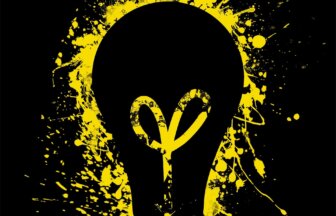「やる気が出ない」が続くとき、それは燃え尽き症候群かもしれない
毎日同じ繰り返し。朝起きて、学校や職場へ行き、帰宅して寝る。そんな日常の中で、ふと「なんでこんなに疲れているんだろう」「やる気が出ない日が続いている」と感じたことはありませんか?そんな状態が長く続くとき、それは日頃の疲れではなく「燃え尽き症候群」かもしれません。
本記事では、現代人に起こりえる「燃え尽き症候群」について詳しく解説し、その予防法やモチベーションを回復・維持する方法について探っていきます。忙しい日々を送る中で自分自身を大切にするヒントが見つかるはずです。
燃え尽き症候群とは?その正体を解明する
燃え尽き症候群(バーンアウト症候群)は、1970年代にアメリカの心理学者ハーバート・フロイデンバーガーによって提唱された概念です。当初は対人援助職(医療、福祉、教育など人と関わる仕事)に従事する人々に見られる症状でしたが、現在ではあらゆる職種や学生、主婦など幅広い層で見られる現象となっています。
世界保健機関(WHO)は2019年、燃え尽き症候群を「職場のストレスが上手く管理できないことによって生じる症候群」と定義しました。ただの疲労感とは異なり、長期間にわたるストレスの蓄積によって引き起こされる心身の消耗状態です。
燃え尽き症候群の3つの特徴
◾️極度の疲労感と消耗感
身体的にも精神的にも極度に疲れ切った状態が続きます。朝起きても疲れが取れず、簡単な日常タスクでさえエネルギーを使い果たしてしまう感覚に襲われます。
◾️冷笑的・皮肉的な態度(シニシズム)
仕事や学業に対して距離を置き、意味を見出せなくなります。「どうせやっても無駄だ」という諦めの気持ちや、周囲の人々に対する無関心さも生まれます。
◾️職務効率の低下
集中力や創造性が低下し、以前なら簡単にこなせていたタスクでも時間がかかるようになります。自分の能力や成果に対する自信も失われていきます。
燃え尽き症候群の肉体的・精神的サイン
肉体的サイン
- 慢性的な疲労感
- 頭痛や筋肉痛が頻繁に起こる
- 睡眠障害(眠れない、または寝ても疲れが取れない)
- 食欲の変化(食べ過ぎたり、食欲不振になったり)
- 免疫力の低下(風邪などを引きやすくなる)
精神面のサイン
- やる気や情熱の喪失
- 不安感や抑うつ感
- イライラや怒りっぽさ
- 無力感や自己効力感の低下
- 孤独感や疎外感
このような症状が複数現れ、それが長期間(通常は数週間から数ヶ月)続く場合、燃え尽き症候群の可能性が高いといえます。
燃え尽き症候群になりやすい人とは?自分は大丈夫?

燃え尽き症候群は誰にでも起こりうる現象ですが、特に以下のような特徴や状況にある人がなりやすいとされています。自分自身や周りの人の姿に当てはまるところはないか、チェックしてみましょう。
1. 完璧主義者
「妥協は許されない」「100%以上の結果を出さなければ」と自分を追い込む完璧主義者は、燃え尽き症候群のリスクが高い傾向にあります。常に高い基準を自分に課すことでプレッシャーが蓄積していき、その重圧に耐えきれなくなると燃え尽きてしまうのです。
例えば、テスト前に「すべての範囲を完璧に理解しないと気が済まない」と睡眠時間を削って勉強し続ける学生や、「この企画は絶対に成功させなければ」と休日返上で働き続ける社会人などが該当します。
完璧を目指すこと自体は悪いことではありませんが、「人間だから失敗もある」という現実を受け入れる柔軟性も必要です。
2. 責任感が強すぎる人
「自分がやらなければ誰がやるのか」と考え、周囲の期待に応えようとし過ぎる人も危険です。特に、他者からの評価に敏感で「ノー」と言えない人は、自分のキャパシティを超えた仕事や役割を引き受けてしまいがちです。
学校のグループワークで「みんな忙しそうだから自分が頑張ろう」と一人で作業を抱え込んだり、職場で「断ると迷惑をかける」と本来の業務外の仕事まで引き受けたりする人が当てはまります。
責任感は素晴らしい資質ですが、自分一人で全てを背負い込もうとすると、その重みで潰れてしまうことになります。
3. ワーク・ライフ・バランスが取れていない人
仕事や学業と私生活の境界線があいまいで、常に「やるべきこと」のことを考えている人も燃え尽きやすいです。スマートフォンやPCの普及により、いつでもどこでも仕事や勉強ができる環境が整った現代では、特にこの問題が顕著になっています。
例えば、夜遅くまで仕事のメールをチェックし続ける会社員や、休日も課題のことが頭から離れない学生などです。「オン」と「オフ」の切り替えができないと、心身を休める時間が確保できず、慢性的な疲労状態に陥りやすくなります。
4. 自己肯定感が低い人
「自分はもっとできるはず」「自分の成果は十分ではない」と常に自分を過小評価する人も、燃え尽き症候群になりやすい傾向があります。自分の成果や努力を適切に評価できないため、休息する理由を見つけられず、際限なく自分を追い込んでしまうのです。
テストで90点を取っても「あと10点取れたはず」と自分を責める学生や、プロジェクトが成功しても「もっと早く終わらせられたはず」と考える社会人などが該当します。
5. 環境的要因
個人の性格だけでなく、置かれている環境も燃え尽き症候群の原因になりえます。
- 過度な業務量や学習量:処理しきれないほどの仕事や課題が常に押し寄せている
- 締め切りのプレッシャー:常にタイトなスケジュールで追われている
- 評価や競争の激しい環境:常に他者と比較され評価される状況にある
- サポートの欠如:職場や学校、家庭で適切なサポートを受けられない
- 価値観の不一致:自分の価値観と組織や集団の価値観が合わない
例えば、「残業が当たり前」という企業文化の中で働く社会人や、「睡眠時間を削ってでも勉強するのが当然」という雰囲気の学校にいる学生は、知らず知らずのうちに燃え尽き症候群へと近づいている可能性があります。
燃え尽き症候群を回避するための具体的な対策
燃え尽き症候群は一度陥ってしまうと回復に時間がかかりますが、適切な対策を取ることで予防することが可能です。以下では、日常生活に取り入れやすい具体的な対策を紹介します。
1. 小さな目標と”ごほうび”を設定する
大きな目標だけを見ていると、達成感を得にくく、モチベーションが維持できません。大きな目標を小さく分割し、一つずつクリアしていくことで、定期的に達成感を味わうことができます。
例えば、「一日3ページ本を読む」「週に1回新しいレシピに挑戦する」といった小さな目標を設定し、達成したら自分へのご褒美として好きな映画を観たり、特別なスイーツを食べたりするなど、小さな報酬を用意しましょう。
2. 本当の休息を取り入れる
「休息」と「気分転換」は似ているようで実は異なります。SNSをチェックしたりゲームをしたりすることは、一見リラックスしているように見えても、脳は別の形で活動し続けています。真の休息とは、脳と体の両方を休める時間です。
3. 自己肯定感を高める習慣を取り入れる
自分の価値は成果や生産性だけで決まるものではありません。自分自身を認め、大切にする習慣を取り入れましょう:
1
2