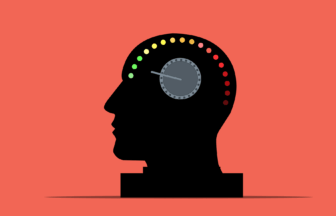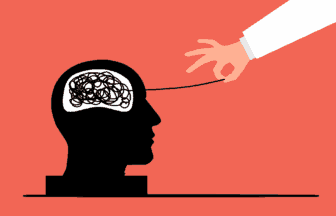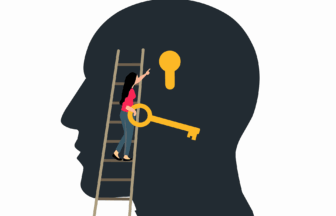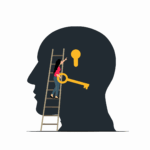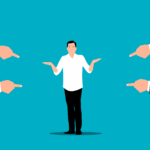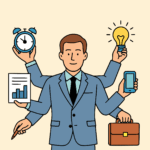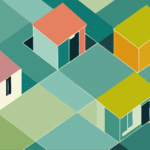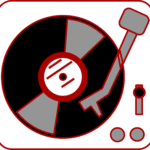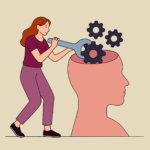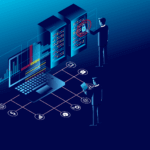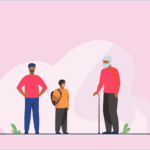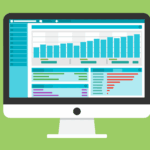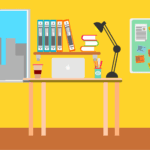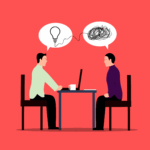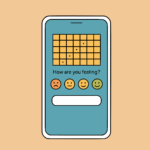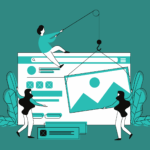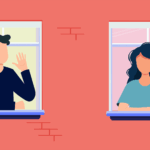先月3月、さいたま市のある中学校で卒業式に起きた出来事が、いま教育現場の姿勢に大きな疑問を投げかけています。不登校だった卒業生6人に椅子が用意されず、平均台に座らされたというニュースは、多くの人の心に衝撃を与えています。教育委員会は「配慮が足りなかった」と説明しましたが、果たしてこれは配慮不足で片付けられる問題なのでしょうか。
私たちの社会では、不登校の生徒に対する理解はまだまだ不十分です。彼らが抱える心の問題や社会的困難は見えにくく、ともすれば「問題児」や「怠け者」というレッテルを貼られがちです。簡単に解決できるものではないのは誰もがわかっているのですが、そのような偏見は教育現場こそが率先して払拭すべきではないでしょうか。
今回の件で最も考えさせられるのは、不登校の生徒たちが「卒業式に出席する」という勇気を振り絞った大きな一歩を踏み出したにもかかわらず、学校側の受け入れ態勢が整っていなかったという事実です。普段学校に来ていない彼らにとって、卒業式への出席は並大抵の決断ではなかったはずです。それなのに、彼らを迎えたのは「平均台」だったのです。
「配慮不足」では済まされない問題の本質
「配慮が足りなかった」ーこの言葉の軽さに筆者は違和感を覚えます。配慮が「足りなかった」のではなく、そもそも不登校の生徒たちへの配慮が「あったのか」という根本的な疑問があります。職員がどうとか状況がどうとかよりも、子どもたちの気持ちを考えると、やはり厳しいものがあります。
卒業式は学校行事の中でも最も重要なイベントの一つであり、教職員は当日の運営に追われ、確かにバタバタしていたことでしょう。そして今回は職員間の情報伝達のミスもあったようです。しかし、卒業式の主役は生徒たち、特に義務教育を終える卒業生たちです。不登校であっても、彼らは立派な卒業生であり、同じような扱いを受ける権利があります。
出席者の把握と必要な準備体制を整えておくのは、卒業式でなくても、様々な行事の基本的な準備のはずです。今回不登校の生徒たちの出席可能性を考慮していなかったとすれば、それは単なる不注意ではなく、彼らの存在を軽視する姿勢の表れではないでしょうか。仮に急遽の対応が必要だったとしても、教員の椅子を譲るなど、様々な解決策があったはずです。
「望まないメッセージ」を生み出す文化

この問題の背景には、日本の社会に根付いた「同調圧力」や「画一主義」があるように思えます。これを教育現場で考えると、毎日学校に通い、皆と同じ行動をとる生徒が「良い生徒」とされる価値観の中で、不登校の生徒たちは無意識のうちに「はみ出し者」として扱われがちなのではないでしょうか。
ある心理学者は学校教育に関する著書の中で、「学校システムにおいて、暗黙のうちに設定された『正常』の範囲から外れた子どもたちは、しばしば無意識レベルで排除の対象となる」と指摘しています。今回の事例は、まさにこの「無意識の排除」が可視化された形ではないでしょうか。
不登校の生徒たちに平均台を用意したことは、単なる物理的な座席の問題ではなく、彼らに「あなたたちは特別で、通常の対応の範囲外だ」というメッセージを伝えてしまったのです。これこそが「悪意のない悪意」であり、時に明確な差別よりも深く人の心を傷つけます。
当事者視点の欠如がもたらす結果
この問題の核心は、当事者視点の欠如にあります。不登校の生徒たちの立場に立って考えれば、卒業式への参加自体が大きな挑戦です。学校への足が遠のいていた彼らが、最後の儀式に参加する決断をした勇気を、教育関係者はどれだけ理解していたでしょうか。
不登校の子どもたちの多くは学校という場所に対して複雑なトラウマを抱えていると述べています。実は筆者もかつてその一人であり、すべて学校側が悪いとは考えないにしても、何かしらのトラウマによって登校することが恐いのです。そんな彼らが再び学校という場所に足を踏み入れるとき、そこでの体験がどれほど重要な意味を持つか、想像に難くありません。
彼らは人一倍デリケートであり、平均台に座らされるという体験は、彼らにとって「やはり自分は受け入れられていないのだ」「学校は変わっていなかった」という確信を強めることになりかねません。一瞬の配慮不足が、彼らの人生の大切な節目の記憶を、苦い思い出に変えてしまう可能性があるのです。
教育現場に求められる真の「インクルージョン」
文部科学省は近年、「多様な学び」や「インクルージョン教育」の重要性を強調していますが、今回の事例は、それらの理念が現場レベルでどれほど浸透しているかを問う出来事となりました。
インクルージョンとは、「同じ空間にいる」ことではなく、一人ひとりの存在が等しく尊重され、必要な配慮がなされる環境を意味します。不登校の生徒たちに平均台を用意したことは、物理的には同じ空間に「含める」努力をしつつも、精神的には彼らを「区別」してしまう矛盾した行為だったと言えるでしょう。
教育評論家の尾木直樹氏は「学校は多様性を認める場所であるべき」と主張しています。それは口先だけのスローガンではなく、日常の細かな配慮や準備に表れるものです。椅子一つを用意する行為にさえ、学校の本質的な姿勢が表れているのではないでしょうか。
「当たり前」を問い直す必要性
この問題を考える上で重要なのは、学校における「当たり前」を問い直すことです。多くの学校では、卒業式に全員が参加することが「当たり前」とされている一方で、不登校の生徒の出席は「例外的事態」と認識されがちです。しかし、現代の教育現場においては、不登校は珍しい現象ではありません。
文部科学省の調査によれば、2023年度の小中学校における不登校児童生徒数は約29万人(前年比22.1%増加)に上り、過去最多を更新しています。これは30人学級で計算すると、平均して1クラスに2〜3人の不登校の子どもがいる計算になります。もはや「例外」と言える状況ではないのです。
にもかかわらず、学校行事の準備段階で不登校の生徒への配慮が欠けていたとすれば、それは学校側の認識が現実から乖離していることを示しています。不登校の生徒たちも立派な卒業生であり、同じ権利を持つ存在です。彼らの参加を「イレギュラー」としてではなく、あらかじめ想定しておくべき「当たり前」として捉える視点の転換が必要なのではないでしょうか。
1
2