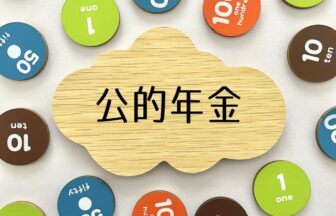世間の物申したい派は、「論破」という名の甘い蜜に酔いしれる時代を生きている。SNSを開けば知識や価値観の優越的地位をかざし、リプライ欄には自身の正義を振りかざす投稿が連なる。かつて議論は知的交流の場であったはずが、今や勝ち負けを決める闘技場と化している。なぜ人は他者を「論破」することに、これほどまでの優越感を覚えるのだろうか。本コラムでは、現代社会に蔓延する「論破文化」の実態と、その背後に潜む心理、そして私たちが目指すべき対話の姿について考察していく。
「はい、論破」世代の台頭|SNSで広がる優越感中毒
「朝食はパン一択だな」
このような何気ない発言があったとする。「栄養学的には和食の方が優れているんだが?データも見ずに発言するなよ。はい、論破」といった反応が返ってくる時代だ。特にX(旧Twitter)では、他者の投稿に対して自分の価値観を絶対視し、相手を打ち負かそうとする「論破マン」の存在が目立つようになった。
彼らの特徴は、相手の発言の文脈や背景を無視し、一部分だけを切り取って攻撃材料とすることだ。議論の目的は相互理解ではなく、「自分が正しいことを証明する」という自己満足に終始している。
さらに憂慮すべきは、この現象が若年層にまで広がっていることだ。近頃のニュース記事によれば、小学生の間でも「はい、論破」という言葉が流行語のように使われているという。友達や親の意見・感想に対して「それは論理的におかしい」と言い放ち、優位な立場を確保しようとする児童が増えているのだ。
彼らはなぜ、このような行動様式を身につけるのだろうか。その背景には、SNSでの「いいね」や「リツイート」という形での承認欲求の充足がある。「論破」という行為が瞬間的な達成感と承認をもたらし、それが中毒性のある「蜜の味」となっているのだ。
「論破」の心理学|なぜ人は他者を打ち負かしたがるのか
心理学的視点から見ると、「論破」行為の背後には複数の心理メカニズムが働いている。一つは「認知的不協和の解消」だ。自分の信念や価値観と矛盾する情報に接すると、人は不快感を覚える。この不快感を解消するための手段として、相手の意見を全否定し、自分の価値観を防衛しようとするのだ。
また、社会心理学における「内集団バイアス」も関係している。自分と同じ価値観を持つ集団(内集団)を優位に、異なる価値観を持つ集団(外集団)を劣位に見なす傾向だ。SNSは同じ価値観を持つ者同士が集まりやすく、この傾向をさらに強化する。
さらに重要なのは「ダニング・クルーガー効果」の存在だ。これは、能力の低い人ほど自分の能力を過大評価し、逆に能力の高い人ほど自分の能力を過小評価する傾向を指す。「論破マン」の多くは、自分の知識や論理的思考能力を過大評価しており、それゆえに「自分は相手より賢い」という錯覚に陥りやすい。
教育学者は「現代の子どもたちは、正解を求めることに慣れすぎて、多様な解や考え方があることを受け入れられなくなっている」と指摘する。学校教育、さらにはSNSをはじめとした私生活における「正解至上主義」が、他者の意見を受け入れず、正解か不正解かの二元論で物事を判断する傾向を助長しているのかもしれない。
ネット時代の「論破」文化|テクノロジーが変えた議論のあり方
インターネットの普及は、私たちの議論の場と方法を根本から変えた。かつての対面での議論では、相手の表情や声のトーンから感情を読み取り、それを考慮しながら会話を進めることができた。しかし、テキストベースのオンラインコミュニケーションでは、こうした非言語情報が欠如している。
さらに、SNSの「いいね」や「リツイート」といったシステムは、過激で断定的な発言ほど注目を集めやすい環境を作り出した。「論破」という行為は、こうしたプラットフォームの特性と相性が良いのだ。
メディア研究者のニール・ポストマンは著書『メディアの思想』で「メディアはメッセージだけでなく、私たちの思考様式そのものを形作る」と述べた。SNSという媒体が「勝ち負け」を重視する議論文化を形成し、それが私たちの日常的な思考様式にまで影響を及ぼしているのだ。
AI技術の発展も、この状況に一役買っている。ChatGPTのような生成AIの登場により、誰でも専門的な知識を引用したかのような文章を生成できるようになった。しかし、表面的な知識の羅列と深い理解は別物だ。AIによって生成された「論破」用の文章が、さらなる議論の混乱を招く可能性も否定できない。
「正義のヒーロー」症候群|自分の価値観を絶対視する危険性
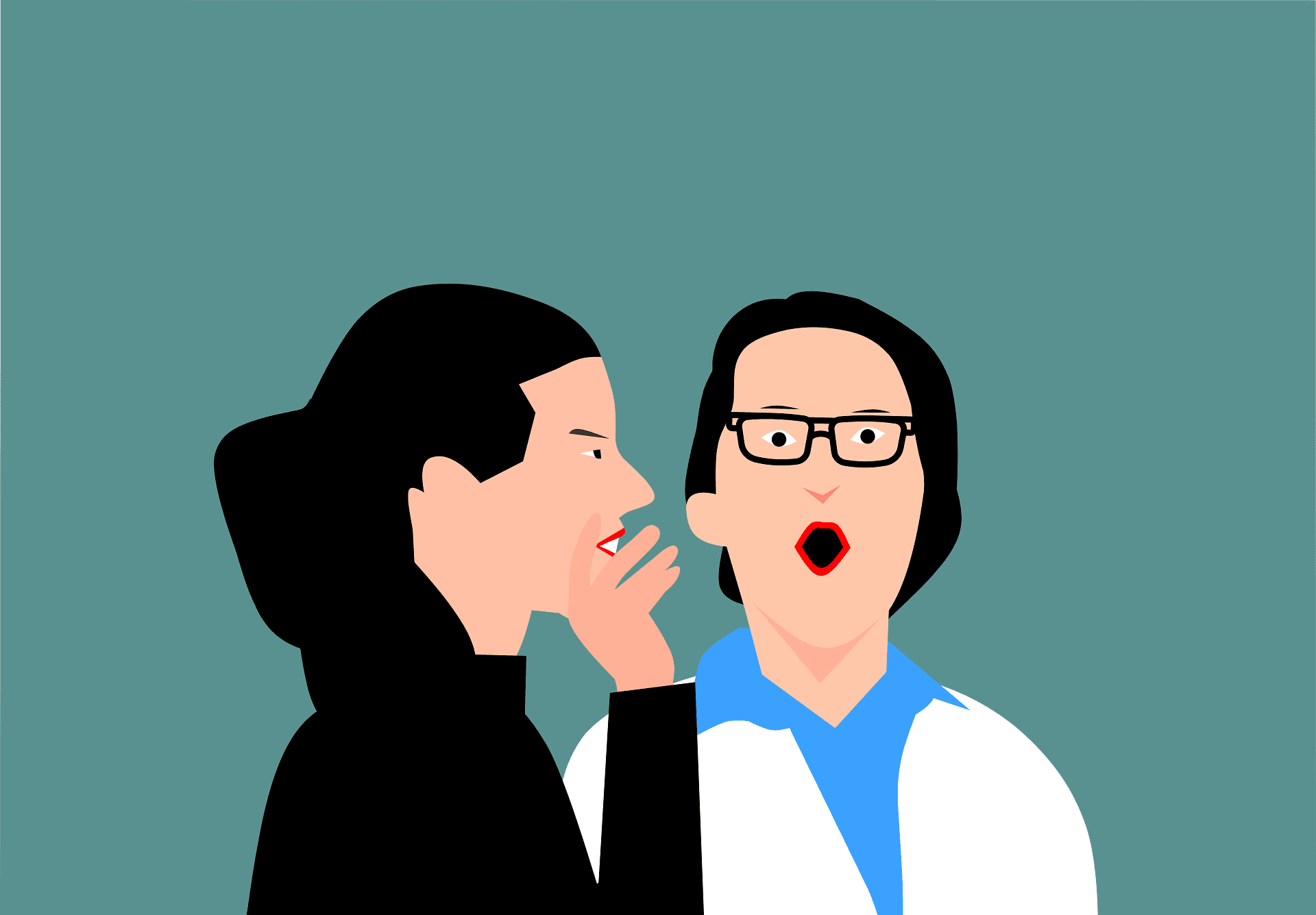
論破マンの多くは自分の価値観こそが絶対的に正しいと信じ、それに反する意見を「悪」として排除しようとする。しかし、現実世界において絶対的な正義など存在するのだろうか。
哲学的観点から見れば、価値観は文化、時代、個人の経験によって大きく異なる。西洋と東洋では美の概念が異なり、世代によって倫理観も変化する。「正しさ」は常に相対的で、文脈依存的なものだ。
マンガや映画に登場するヒーローは、明確な「善」と「悪」の二項対立の中で活躍する。しかし現実世界はそれほど単純ではない。複雑で多様な価値観が交錯する現代社会において、自分の価値観だけを絶対視することは、むしろ対話の可能性を閉ざしてしまう。
心理学者のジョナサン・ハイトは、道徳的判断の多くは直感的・感情的なものであり、理性はそれを後付けで正当化するに過ぎないと指摘している。「論破」を試みる人々は自分の判断が純粋に理性的だと思い込んでいるが、実際には彼ら自身の感情や価値観に強く影響されているのだ。
1
2