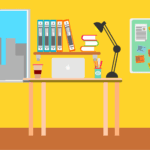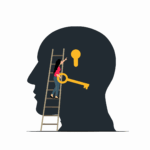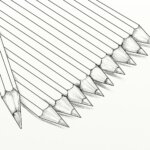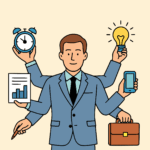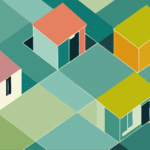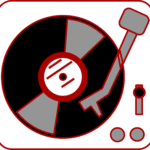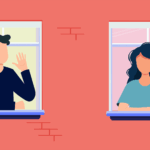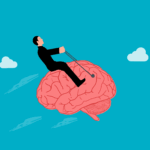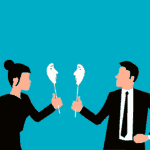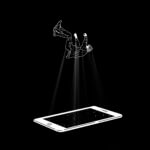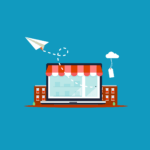誰もが通る道、されど誰も語らぬ真実
事業承継は、どんな企業にもいずれ訪れる通過儀礼である。だが、この当たり前のプロセスが、驚くほど多くの企業を混乱に陥れている。帝国データバンクの調査によれば、中小企業の約6割が後継者不在の状態にあり、後継者が決まっている企業でさえ、承継プロセスで致命的なトラブルを経験するケースが後を絶たないという深刻が垣間見える現実がある。
なぜ、これほどまでに事業承継は難しいのか。答えは単純だ。経営の引き継ぎは、株式の移転や社長の交代だけではない。それは権力構造の再編であり、人間関係の再構築であり、そして何より企業文化の世代交代という、極めて複雑な社会的プロセスなのである。
本コラムでは、後継者問題で経営者が陥りがちな典型的な事象と、そこから浮かび上がる要注意ポイントを、実践的な視点から掘り下げていく。これから承継を迎える経営者はもちろん、すでに承継プロセスの渦中にある方々にとっても、一つの羅針盤となれば幸いである。
「後継者はちゃんといる(決まっている)」という危険な思い込み
最初の落とし穴は、承継の入り口にある。多くの経営者が「うちは息子が継ぐことになっている」「専務が次期社長だと周囲も理解している」と話す。だが、ここに大きな認識のズレが潜んでいるかもしれないことに気づいていない。
「決まっている」と経営者が思っていても、当の後継者候補は全く別のことを考えている場合、あるいは途中から気持ちの変化が起きてしまう場合がある。典型的なのは、親子間での承継予定だ。父親である現社長は、長男が当然のように跡を継ぐものと信じて疑わない。だが息子の方は、「いずれは継ぐかもしれないが、今はまだ早い」「本当に自分が継ぐべきなのか迷っている」「実は別の道を考えている」といった複雑な思いを抱えている。
この認識のギャップが表面化するのは、多くの場合、最悪のタイミングの時である。現経営者の体調不良や、取引先からの信用不安、あるいは重要な経営判断を迫られた場面で、突然「実は継ぐつもりはない」と告げられる。そうなれば、企業は深刻な混乱に陥る。
この問題の根本にあるのは、コミュニケーションの欠如である。日本の文化は、あらゆる問題を「察すること」で処理しようとする傾向が強い。明確な意思確認の場を設けず、「わかっているだろう」という前提で物事を進める。だが、人生の重大な決断を、曖昧な察しに委ねることがいかに危険か、言うまでもない。
後継者候補との間で、承継についての率直な対話の場を定期的に設けること。それも、一度や二度ではない。人の考えは変わる。経営環境も変わる。だからこそ、継続的な対話を通じて、互いの認識を常に確認し合う必要がある。そして何より重要なのは、後継者候補が「ノー」と言える環境を作ることである。
「いつでも引き継げる」という時間感覚の錯覚
二つ目の陥りやすい罠は、時間に対する甘い認識だ。「まだ自分は元気だから、あと数年は大丈夫」「後継者も若いから、ゆっくり育てればいい」──こうした楽観的な見通しが、承継のタイミングを遅らせる。
だが、経営の引き継ぎには想像以上に時間がかかる。業務を覚えるだけなら数年で済むかもしれないが、真の意味での承継とは、経営者としての判断力を身につけ、社内外のステークホルダーからの信頼を獲得し、自らのビジョンで会社を動かせるようになることだ。これには、最低でも5年、場合によっては10年という時間が必要になる。
さらに、予期せぬ事態の発生である。現経営者の急病、事故、あるいは認知機能の低下。これらは誰にでも起こりうることだが、多くの経営者は「自分は大丈夫」と考えてしまう。結果、準備が整わないうちに承継を余儀なくされ、後継者は十分な準備期間もないまま重責を担うことになる。
時間感覚の錯覚がもたらすもう一つの問題は、現経営者の「手放せない症候群」だ。「もう少し、もう少し」と引き継ぎを先延ばしにするうちに、後継者のモチベーションは低下し、優秀な幹部社員は将来に見切りをつけて退職していく。承継のベストタイミングは、現経営者が「まだやれる」と感じているときなのだが、まさにその感覚が承継を妨げる皮肉な構図がある。
具体的な承継スケジュールを、逆算して設計することだ。「何歳で引退する」ではなく、「後継者が経営者として独り立ちするまでに何年必要か」を起点に考える。そして、そこから逆算して、いつから本格的な承継プロセスを開始すべきかを明確にする。さらに、万一の事態に備えた緊急時承継プランも用意しておくことが不可欠である。
「経営のすべてを教える」という誤った教育観
三つ目の落とし穴は、承継における教育のアプローチにある。多くの現経営者は、自分が培ってきた知識や経験のすべてを後継者に伝えようとする。だが、これは効果的どころか、しばしば逆効果となる。
問題は二つある。一つは、現経営者の成功体験は、その時代の経営環境に最適化されたものであり、必ずしも今後の経営に有効とは限らないという点だ。過去の成功法則に固執することで、後継者の新しい発想や挑戦を抑圧してしまう危険がある。
もう一つは、膨大な情報を詰め込もうとすることで、本当に重要なことが伝わらなくなるという点だ。経営において最も大切なのは、個々の知識やノウハウではない。判断の基準となる価値観、危機に直面したときの決断力、そして自ら学び続ける姿勢である。これらは、座学で教えられるものではなく、実践を通じて身につけるしかない。
さらに、「教える」という姿勢そのものが、後継者の成長を妨げることがある。常に現経営者が指示を出し、答えを与えていては、後継者は自分で考え、決断する力を養えない。いつまでたっても「社長の代理」から脱却できず、真の経営者にはなれないのだ。
実際、成功している承継のケースを見ると、現経営者は「教える」よりも「任せる」ことに重点を置いている。もちろん最初は小さな権限から始めるが、徐々に意思決定の範囲を広げ、失敗する機会さえも与える。失敗から学ぶ経験こそが、経営者を育てる最良の教材なのである。
後継者教育を「知識の伝達」ではなく「経営者としての成長指南」として捉え直すことだ。具体的には、早い段階から実際の経営判断に関わらせ、責任ある立場を経験させる。そして、現経営者は「指示する人」ではなく「相談相手」「助言者」としての役割にシフトしていく。こうした段階的な権限移譲こそが、真の承継教育なのである。
「社内は理解してくれる」という人間関係の楽観視
四つ目の陥穽は、社内の人間関係に対する認識の甘さだ。後継者が決まれば、社員は自然とその人についてくると考える経営者は多い。だが現実はそう単純ではない。
特に問題となるのが、後継者よりも年上で、長年会社に貢献してきたベテラン社員や幹部の存在だ。彼らは表面上は後継者を受け入れたように見えても、内心では「あの若造に何がわかる」「俺の方が会社のことをよく知っている」という思いを抱いていることが少なくない。
このような感情は、重要な局面で表面化する。後継者が新しい方針を打ち出そうとしたとき、ベテラン社員は「そんなやり方はうまくいかない」と抵抗する。新規事業に挑戦しようとすれば、「リスクが高すぎる」と反対する。こうした抵抗は、必ずしも悪意からではない。長年の経験に基づく懸念である場合も多い。だが結果として、後継者の手足を縛り、改革を妨げることになる。
さらに複雑なのは、現経営者がいつまでも会社に顔を出し、影響力を保持し続けるケースだ。社員の中には、表向きは後継者に従いながらも、重要な判断は「先代に確認してから」という姿勢を取る者が出てくる。これでは後継者は名ばかりの社長となり、真のリーダーシップを発揮できない。
親族内承継の場合、この問題はさらに深刻化する。後継者である息子や娘が社長になっても、会長となった父親が実権を握り続ける。社員は新旧どちらの指示に従うべきか迷い、組織は二重権力構造に陥る。こうした状況は、社内の混乱を招くだけでなく、後継者の自信や意欲を大きく損なう。
承継を「人の交代」ではなく「組織変革」として捉えること。後継者が真にリーダーシップを発揮できる環境を整えるには、現経営者の明確な退き方が重要になる。段階的に引き継ぐのは良いが、一定の時点で完全に手を離す覚悟が必要だ。
また、ベテラン社員との関係構築も欠かせない。後継者は、彼らの経験と知見を尊重しながらも、自らのビジョンを明確に示し、対話を重ねて信頼を獲得していく必要がある。そして現経営者は、公の場で後継者への全面的な支持を示し、権威の移行を明確にすることが求められる。
「家族だから大丈夫」という身内への過信
五つ目の問題は、親族内承継に特有の落とし穴だ。血縁関係があるからこそ、かえって深刻な問題が生じることがある。
最も典型的なのは、複数の後継者候補がいる場合の兄弟姉妹間の確執だ。長男が継ぐのが当然と考える父親の下で、実は次男の方が経営能力が高く、周囲の信頼も厚いというケースは珍しくない。だが、長男が継ぐことが既定路線となっていれば、次男は疎外感を抱き、最悪の場合、独立や転職を選択する。優秀な人材を失うだけでなく、家族関係にも亀裂が入る。
また、後継者以外の親族、特に娘婿や次男の妻などの存在も、しばしば火種となる。株式の分散により、経営に関与していない親族が一定の発言権を持つようになると、事あるごとに「配当を増やすべきだ」「会社の資産を売却すべきだ」といった要求が出てくる。これは後継者の経営判断を大きく制約する。
さらに、配偶者の影響も見過ごせない。後継者の妻が会社経営に強い関心を持ち、経営判断に口を出すようになると、社内の人間関係は一気に複雑化する。特に、先代の妻(後継者の母)と後継者の妻の間で意見が対立すれば、家族問題が企業経営を揺るがす事態となる。
親族内承継のもう一つの落とし穴は、「家業」意識の強さだ。家族経営の良さは、強い結束力と長期的視点にある。だが、「家の事業」という意識が強すぎると、能力よりも血縁が優先され、非親族の優秀な社員が排除される。結果、組織の活力が失われ、競争力が低下する。
親族内承継を選択する場合でも、能力主義の原則を貫くことが重要だ。後継者は血縁だからではなく、経営者としての資質があるから選ばれるべきであり、それを親族全員が理解し、納得する必要がある。
また、株式の集中も考慮すべきだ。経営に関与しない親族に株式が分散すると、将来的に経営の自由度が失われる。信託や持株会社の活用など、専門家の助言を得ながら、適切な株式保有構造を設計することが求められる。
「取引先は変わらずついてくる」という外部関係の軽視

六つ目の盲点は、社外のステークホルダーとの関係性である。長年にわたって現経営者が築いてきた取引先や金融機関との信頼関係は、実は極めて属人的なものであることが多い。
典型的なのは、銀行との関係だ。現経営者の個人的な信用によって融資が実行されてきた場合、後継者に代わった途端、融資姿勢が厳しくなることがある。特に、後継者がまだ若く、経営実績がない場合、金融機関は慎重にならざるを得ない。結果、必要な運転資金が調達できず、経営が行き詰まるケースも出てくる。
取引先との関係も同様だ。現経営者の人脈で成立していた取引は、後継者に代わることで見直される可能性がある。特に、競合他社が営業攻勢をかけてくれば、「新しい社長では不安」という理由で取引を変更されることもある。
さらに、重要な顧客情報や取引の詳細が、現経営者の頭の中にしかない場合だ。承継後に「あの取引はどういう経緯だったのか」「あの顧客にはどう対応すべきか」といった疑問が次々と生じるが、現経営者がすでに一線を退いていれば、対応に苦慮することになる。
また、同業者との関係や業界団体での立場も、承継によって変化する。現経営者が業界の重鎮として影響力を持っていた場合、その地位は自動的には引き継がれない。後継者は一から信頼を築き直す必要があり、そのプロセスで情報収集力や交渉力が一時的に低下することもある。
承継プロセスの早い段階から、後継者を外部に露出させ、関係構築の機会を作ることだ。取引先への挨拶回り、業界団体への参加、金融機関との定期的な面談など、現経営者と一緒に行動することで、後継者の存在を印象づけ、信頼の橋渡しをする。
また、重要な取引や顧客に関する情報は、必ず文書化しておく必要がある。口頭での引き継ぎだけでは不十分だ。取引の経緯、顧客の特性、注意すべき点などを記録し、後継者がいつでも参照できるようにしておくことが、スムーズな承継につながる。
「株式と経営権の整理」という法務面の見落とし
七つ目の、そして最も技術的に複雑な問題が、法務・財務面の整備である。多くの経営者は、事業承継を「経営の引き継ぎ」としてしか捉えていないが、実際には法的な権利関係の移転という側面が極めて重要だ。
最も基本的なのは株式の承継だが、これが想像以上に複雑な問題を引き起こす。現経営者が株式の大半を保有している場合、その相続や贈与には多額の税金が発生する。事業承継税制を活用すれば税負担を軽減できるが、要件が厳しく、専門家の助言なしには適切に活用できない。
さらに、株式が親族間で分散している場合、意思決定が困難になる。特に、経営に関与していない親族が株式を保有していると、重要な決議で反対票を投じられるリスクがある。最悪の場合、経営方針をめぐって親族間で対立が生じ、訴訟に発展することもある。
個人保証の問題も見過ごせない。中小企業の多くは、現経営者が会社の借入金に対して個人保証を提供している。承継時にこの保証をどう引き継ぐか、あるいは解除できるかが大きな課題となる。後継者に引き継げば、その個人資産がリスクにさらされる。かといって保証を外せなければ、現経営者はいつまでも会社のリスクを負い続けることになる。
事業用資産の名義も重要だ。工場や店舗の不動産が現経営者の個人名義になっている場合、その承継には相続税や贈与税がかかる。また、賃貸借契約や設備のリース契約なども、名義変更の手続きが必要となる。これらを適切に処理しないと、承継後に思わぬトラブルが生じる。
法務・財務面の整備は、承継の5年以上前から着手すべきである。税理士、弁護士、事業承継の専門家などと連携し、総合的な承継計画を立てる必要がある。特に、事業承継税制の活用、株式の集約、個人保証の見直しなどは、計画的に進めなければならない。
また、定款の見直しも重要だ。後継者が安定的に経営できるよう、株式の譲渡制限や、少数株主の権利を適切に設計する必要がある。さらに、万一に備えた事業継続計画(BCP)の中に、緊急時の経営権の移転についても規定しておくことが望ましい。
まとめ|承継は「終わり」ではなく「始まり」である
ここまで、後継者問題で陥りがちな事象と要注意ポイントを見てきた。これらに共通するのは、事業承継を「一時点のイベント」として見る誤りである。承継とは、数年にわたるプロセスであり、しかもそれは「終わり」ではなく、新しい経営の「始まり」なのだ。
現経営者にとって、自らが築いた事業を手放すことは、人生の一大決断である。だからこそ、感情的になりやすく、客観的な判断が難しくなる。だが、企業を次世代に引き継ぐことは、経営者としての最後の、そして最も重要な仕事である。
後継者にとっても、承継は大きな試練であり、前任者の築いた基盤を引き継ぎながら、自らの色を出していく。伝統を守りつつ、革新を起こす。この難しいバランスを取りながら、企業を成長させていかねばならない。
だが、これらの困難を乗り越えた先には、大きな可能性が広がっている。世代交代は、企業に新しいエネルギーをもたらし、組織を活性化させる機会でもある。適切に準備され、丁寧に実行された承継は、企業を次のステージへと押し上げる推進力となる。
事業承継に「完璧な正解」はない。それぞれの企業に、それぞれの事情があり、それぞれの最適解がある。だが、先人たちが経験してきた教訓に学び、起こりうる問題を予見し、適切に準備することで、承継の成功確率は大きく高まる。本コラムが、そのための一助となれば幸いである。
著者【ALL WORK編集室】

-
「真面目に生きている人が、損をしない世界を。」
キャリアの荒波と、ネット社会の裏表を見てきたメディア運営者。かつては「お人好し」で搾取され続け、心身を削った経験を持つ。その絶望から立ち直る過程で、世の中の「成功法則」の多くが、弱者をカモにするための綺麗事であると確信。
本メディア「ALL WORK」では、巷のキラキラした副業論や精神論を排し、実体験に基づいた「冷酷なまでに正しい生存戦略」を考察・発信中。