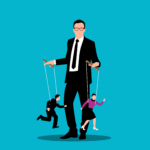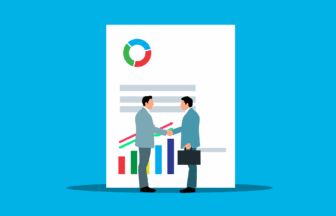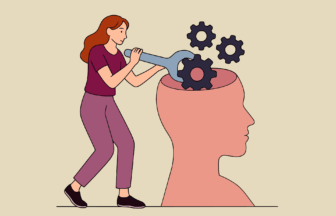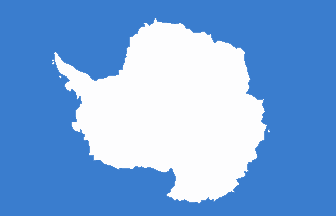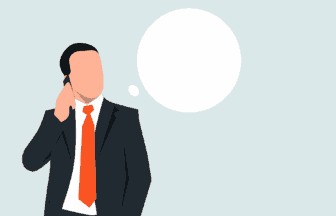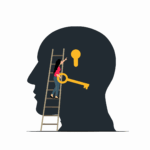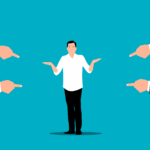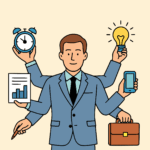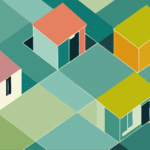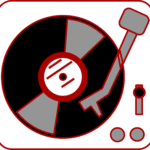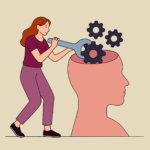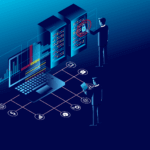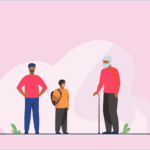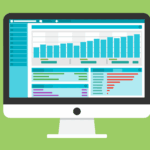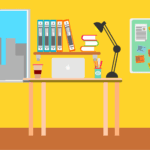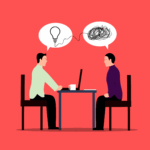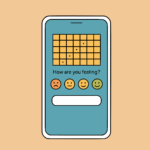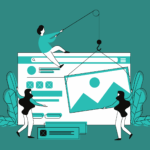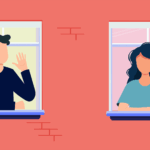インバウンド需要の回復とともに高騰する宿泊料金。その一方で、新たに導入される宿泊税。この二つの動きに、違和感を感じている人は少なくないのではないだろうか。今回は、観光立国を掲げる日本で起きている宿泊業界の現状と課題について、詳しく掘り下げていきたい。
止まらない宿泊料金の高騰、その背景にある真実
2025年時点、都心部の主要ホテルの宿泊料金は、コロナ禍以前と比較して50%以上上昇している。一般的なビジネスホテルですら、一泊15,000円を超えることが珍しくない状況となっている。確かに、人件費の上昇やエネルギーコストの高騰など、ホテル運営における負担は増加している。しかし、それだけで現在の価格水準は説明できるのだろうか。
業界関係者によると、多くのホテルでは稼働率が90%を超える状況が続いているという。特に訪日外国人観光客の増加により、都市部のホテルは予約が取りにくい状況が恒常化している。この需要と供給のアンバランスにより、ホテル側は料金を引き上げても客室を埋めることができる状況となっているのである。
さらに注目すべきは、多くのホテルが採用している収益管理システム(レベニューマネジメント)の存在だ。このシステムは需要予測や実績に基づいてより最適な収益活動をアシストするもので、利用客の動向に基づいて自動的に料金を変動させるなどの機能があるようだ。予約予測のボリュームが多いのに価格を安くしてしまえば収益は落ちるし、ボリュームが少ないのに価格が高いままというのも利用者減に繋がりかねない。こういった課題を効率的に解決させるのがレベニューマネジメントの役割であろうが、現状では料金高騰を助長する可能性があるのではないだろうか。
宿泊税導入の真意を問う
このような状況下で、各地方自治体は相次いで宿泊税の導入を進めている。東京都では一泊当たり100円から200円の宿泊税が課されており、大阪府や京都市でも同様の制度が導入されている。導入の理由として、観光インフラの整備やオフシーズン対策、広義の観光振興のための財源確保が挙げられている。
しかし、すでに高騰している宿泊料金に追加の負担を求めることは、国内観光の活性化という観点からみて本当に適切なのだろうか。宿泊税の導入以前は、観光振興は一般財源から賄われていた。なぜ今、宿泊者だけに特別な負担を求める必要があるのか。
さらに違和感を拭いきれないのは、宿泊税の使途の不透明さである。確かに、観光案内所の整備やバリアフリー化など、目に見える施策も実施されている。しかし、徴収された税金の大部分が、地域のために、観光客のために使われているとするならば、誰に対して、具体的にどのような経済的な効果をもたらすものなのか、あるいは自治体や観光協会等の、プロセスを主導する組織が数値的な分析を行い、しっかりとしたPDCAが回されているのか、そういった動きは十分とは言えない。
1
2