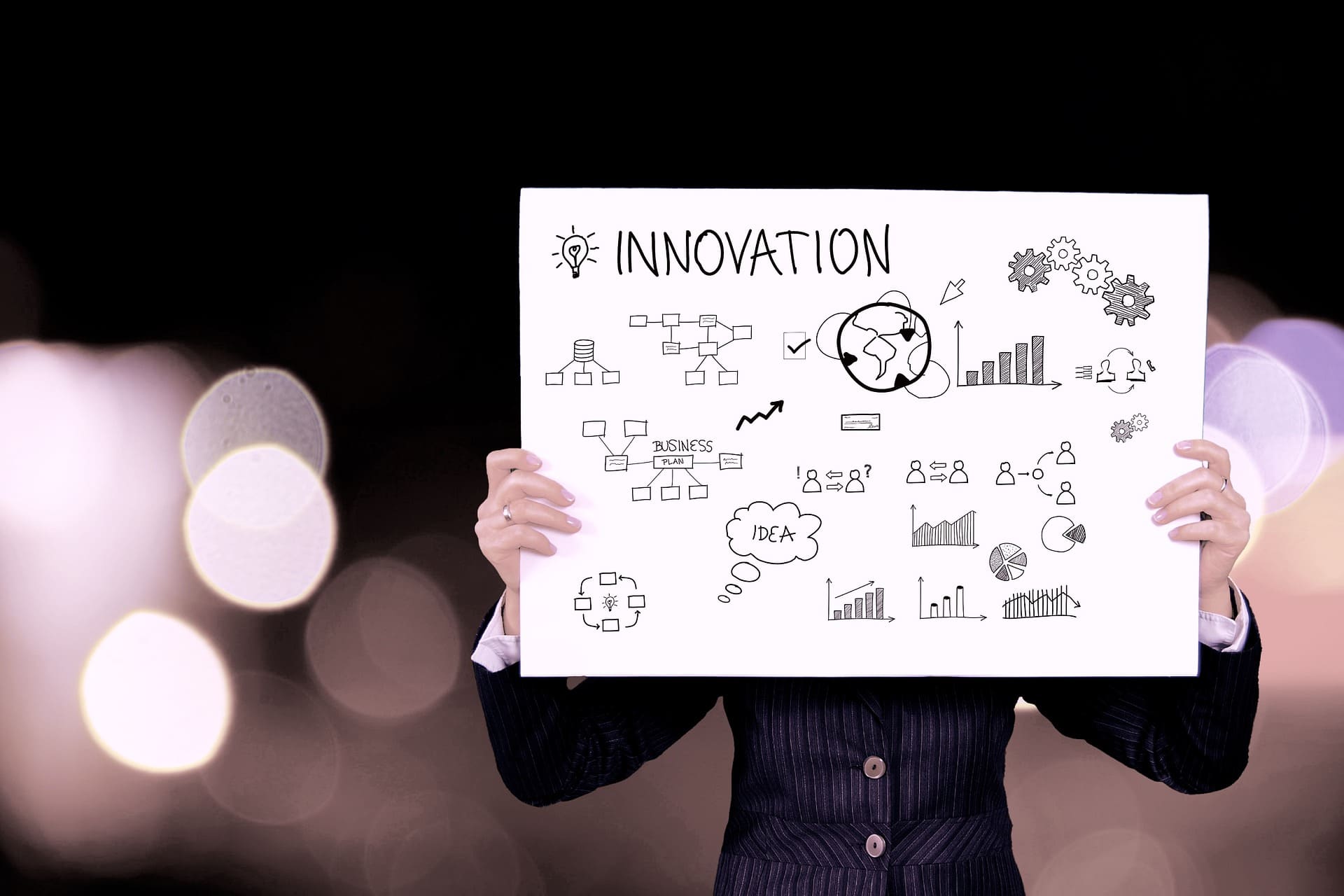
経営とリスクの切っても切れない関係
経営において、リスクは避けて通れない要素である。企業活動そのものがリスクを内包しており、リスクなくして成長なしという側面も持ち合わせている。しかし、全てのリスクが等しく価値あるものではない。経営者が直面する最も重要な判断の一つは、「どのリスクを取るべきか、どのリスクを避けるべきか」という選択である。
これには二面性があり、適切に管理されたリスクは成長と革新の源泉となるが、無計画に受け入れたリスクは企業の存続を脅かす。本記事では、経営におけるリスク判断の本質に迫り、企業が取るべきリスクと避けるべきリスクについて、実務的観点から考察する。
リスク管理の基本概念
リスクとは単に「損失の可能性」ではなく、「不確実性の影響」と定義できる。この不確実性は、ポジティブな結果をもたらす可能性(アップサイド・リスク)とネガティブな結果をもたらす可能性(ダウンサイド・リスク)の両方を含んでいる。
経営学者のピーター・ドラッカーは「企業の本質的機能は二つある。マーケティングとイノベーションだ」と述べているが、これらの機能を果たすためには、適切なリスクテイクが不可欠である。イノベーションを追求しない企業は、長期的には市場から淘汰されるというリスクに直面する。つまり、リスクを取らないことも一種のリスクなのである。
積極的に取るべきリスクの特徴

1. 計算され、マネジメントされているものであること
取るべきリスクの第一の特徴は、それが「計算された」ものであることだ。これは数値化できるものという意味ではなく、以下の要素が明確に検討されていることを意味する。
・リスクの大きさと発生確率
・最悪のシナリオとその対応策
・期待されるリターンとの比較
・企業の吸収能力との整合性
例えば、新市場への参入は大きなリスクを伴うが、市場調査に基づく需要予測、段階的な投資計画、撤退シナリオの策定などを通じて、「計算されたリスク」として管理することが可能である。このようなリスクは、企業の成長戦略において積極的に取るべきものである。
2. 学習が促進されるものであること
企業の持続的成長には、組織的な学習能力の向上が不可欠である。この観点から、たとえ失敗したとしても組織に価値ある学びをもたらすリスクは、積極的に取るべきである。
スタートアップ企業の世界では「フェイル・ファスト(素早く失敗する)」という考え方が浸透しているが、これは失敗を推奨するものではなく、小さなリスクを取りながら迅速に学習サイクルを回すことの重要性を説いている。大企業においても、イノベーションを促進するために、管理された範囲内での実験的取り組みとそこからの学習は奨励されるべきである。
トヨタ自動車の「カイゼン」の文化も、小さなリスクを継続的に取ることで学習と改善を積み重ねるアプローチの一例と言える。
3. 中核能力と関連するものであること
企業の中核能力(コア・コンピタンス)に関連するリスクは、比較的取りやすい。なぜなら、そこには既に専門知識や経験が蓄積されており、リスクの評価と管理が効果的に行えるからである。
例えば、アップルのような製品設計に強みを持つ企業が新製品開発に投資することは、その中核能力を活かしたリスクテイクである。一方で、全く異なる業界への多角化は、より慎重な判断が求められる。
4. 戦略的方向性と一致するものであること
企業の取るべきリスクは、その企業の戦略的方向性と一致している必要がある。明確な戦略なくしてリスクを取ることは、無計画な賭けに等しい。
アマゾンのジェフ・ベゾスは、「長期的な視点を持ち、短期的な結果に一喜一憂しないこと」の重要性を説いているが、これは戦略的方向性に沿った持続的なリスクテイクの姿勢を表している。アマゾンのAWSやキンドルなどの新規事業は、当初は大きなリスクを伴ったが、企業のビジョンと戦略に沿ったものであった。
避けるべきリスクの特徴

1. 企業の生存を脅かすもの
企業が最も避けるべきリスクは、その存続自体を脅かすものである。どれほど大きなリターンの可能性があろうとも、企業の存続が危ぶまれるレベルのリスクは、原則として避けるべきである。
この観点から、資金繰りに直結する過度な財務レバレッジや、コンプライアンス違反によるレピュテーションの致命的な毀損などは、その潜在的なリターンがいかに魅力的であっても避けるべきである。
日本企業の多くが長期存続を重視する経営スタイルを採用しているのは、この「生存を脅かすリスク」への慎重な姿勢の表れと見ることができる。
2. コントロール不能なもの
リスク管理の基本原則として、「コントロールできないリスクは取らない」という考え方がある。ここでいう「コントロール」とは、リスクの発生確率や影響度を調整する能力だけでなく、状況が悪化した場合の対応策を持つことも含まれる。
例えば、為替変動は企業がコントロールできないリスク要因だが、為替ヘッジなどの手段を通じてそのエクスポージャーを管理することは可能である。一方、予測不能な政治変動や天変地異などについては、その発生自体をコントロールすることはできないが、事業継続計画(BCP)の策定によって影響を緩和する準備は可能である。
完全にコントロール不能で、かつ甚大な影響をもたらす可能性のあるリスクについては、極力回避する戦略が賢明である。
3. リターンとバランスしないもの
リスクとリターンはビジネスの基本方程式である。リスクに見合わないリターンしか期待できない案件は、避けるべきである。この判断においては、機会費用の考え方も重要となる。
例えば、10%のリターンを得るために大きなリスクを取るよりも、同じ資源を使ってより少ないリスクで8%のリターンを得る選択肢があるなら、後者を選ぶ方が合理的であることが多い。リスク調整後リターン(リスクあたりのリターン)という観点からの評価が重要である。
1
2




























































































