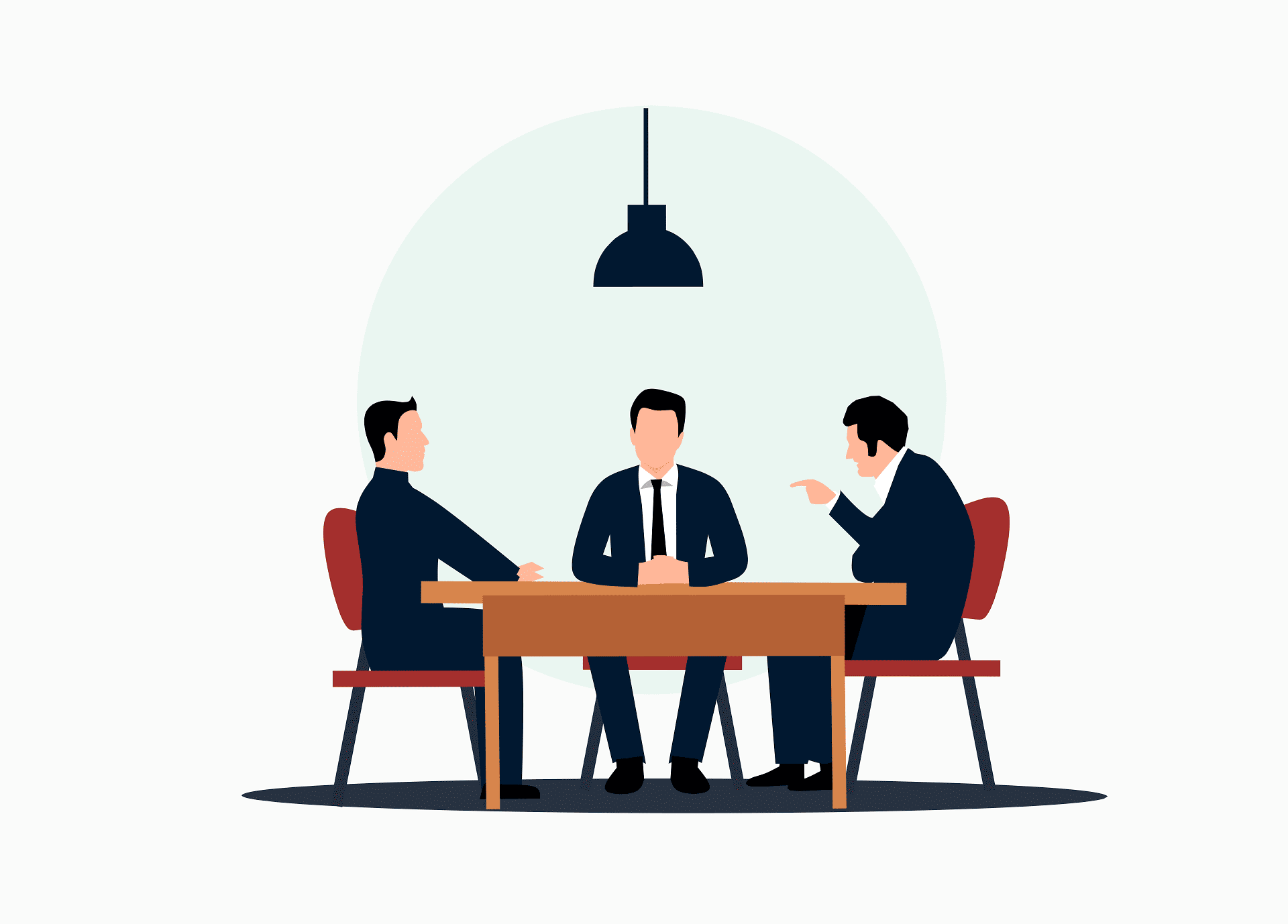
青年たちが描いた「夢」
今や日本経済の中核を担う大企業の創業者たちも、最初はみんな一人の青年だった。彼らがどのような思いで会社を立ち上げ、どんな困難を乗り越えてきたのか。その壮大なストーリーの第一章を紐解いてみよう。
本田宗一郎|町工場から世界のホンダへ
自転車屋の少年が見た夢
本田宗一郎の物語は、静岡県浜松市の小さな自転車修理工場から始まる。1906年に生まれた宗一郎は、幼い頃から機械いじりが大好きな少年だった。父親が営む鍛冶屋の手伝いをしながら、壊れた自転車を直すことに夢中になっていた。
当時の日本では自動車なんて夢のまた夢の時代である。しかし、宗一郎は15歳の時に初めて自動車を目にし、その瞬間に人生が変わったのだ。「この鉄の塊が走るなんて!」と興奮した宗一郎は、その場でエンジンオイルの匂いを嗅ぎ、一生忘れられない体験として心に刻んだという。
町工場での苦闘時代
1946年、戦後の混乱期に宗一郎は浜松で「本田技術研究所」を設立した。といっても、従業員はたった12人、資金もわずか30万円という極めて小規模なスタートだった。最初に作ったのは、なんと自転車に軍用エンジンを取り付けた原動機付き自転車である。
この発想がすごい。戦後の物資不足の中、人々は移動手段に困っていた。宗一郎は「歩くより楽で、自転車より速い乗り物を作ろう」と考えたのだ。この単純だが実用的な発想こそが、後のホンダ帝国の礎となった。
しかし、創業初期は失敗の連続だった。エンジンがすぐに故障する、燃費が悪い、音がうるさいなど、クレームの嵐である。宗一郎は夜遅くまで工場に残り、一台一台手作業で改良を重ねた。「失敗は成功の母」という言葉を地で行く日々だった。
世界への第一歩
1958年、宗一郎は「世界のホンダ」への第一歩として、アメリカ進出を決断する。当時の日本製品は「安かろう悪かろう」の代名詞だった時代に、この決断は周囲から無謀と言われた。しかし宗一郎は「技術に国境はない」と信じていたのだ。
アメリカでの苦戦は想像を絶するものだった。大型バイクで勝負しようとしたが、アメリカの道路事情に合わず連戦連敗。しかし、社員が通勤に使っていた小型の「スーパーカブ」が現地で注目を集めた。これが転機となり、「You meet the nicest people on a Honda」という名キャッチコピーとともに、ホンダはアメリカ市場を制覇したのである。
松下幸之助|電球ソケットから始まった経営の神様
9歳で奉公に出された少年
松下幸之助の人生は、まさに波乱万丈のドラマであった。1894年、和歌山県の農家に生まれた幸之助は、家の没落により9歳という幼さで大阪の火鉢店に奉公に出された。現代では考えられない過酷な環境だが、この経験が後の幸之助の人格形成に大きな影響を与えたのである。
奉公先では朝早くから夜遅くまで働き、わずかな給金で生活していた。しかし幸之助は決して絶望しなかった。「今は辛いけれど、きっといいことがある」という楽観的な性格は、この頃から培われたものだ。16歳の時に大阪電灯会社(現在の関西電力)に就職し、電気という新しい技術に触れることになる。
電球ソケットという小さな発明
1918年、23歳の幸之助は退職を決意し、自宅の借家で松下電気器具製作所(現在のパナソニック)を創業した。創業メンバーは幸之助と妻のむめの、そして義弟の井植歳男の3人だけ。資本金はたったの100円である。
最初に手がけたのは、電球ソケットの改良品だった。当時の電球ソケットは接触不良が多く、すぐに電球が点かなくなってしまう問題があった。幸之助は「もっと確実に接続できるソケットを作ろう」と考え、独自の改良を加えたのである。
この商品が大ヒットした理由は、技術的な優秀さだけではない。幸之助は「お客様の立場に立って考える」ことを徹底していた。電球が点かないというささいな不便を解決することで、多くの人の生活を豊かにしたいと真剣に考えていたのだ。
水道哲学の誕生
幸之助の経営哲学で最も有名なのが「水道哲学」である。これは1932年に開催された第1回松下電器全国大会で発表された理念だ。「物資を水道の水のように豊富で安価に提供し、お客様の生活向上に貢献する」という考え方である。
この哲学が生まれた背景には、幸之助自身の貧しい少年時代の体験がある。「良い物が高くて買えない」という悔しさを知っていたからこそ、「良い物を安く、たくさんの人に届けたい」という強い想いが生まれたのだ。
松下電器は戦前から戦後にかけて、ラジオ、洗濯機、テレビ、冷蔵庫など、数々のヒット商品を世に送り出した。それらすべてに共通していたのは、「普通の家庭でも手の届く価格で、確実に役立つ商品」というコンセプトだった。
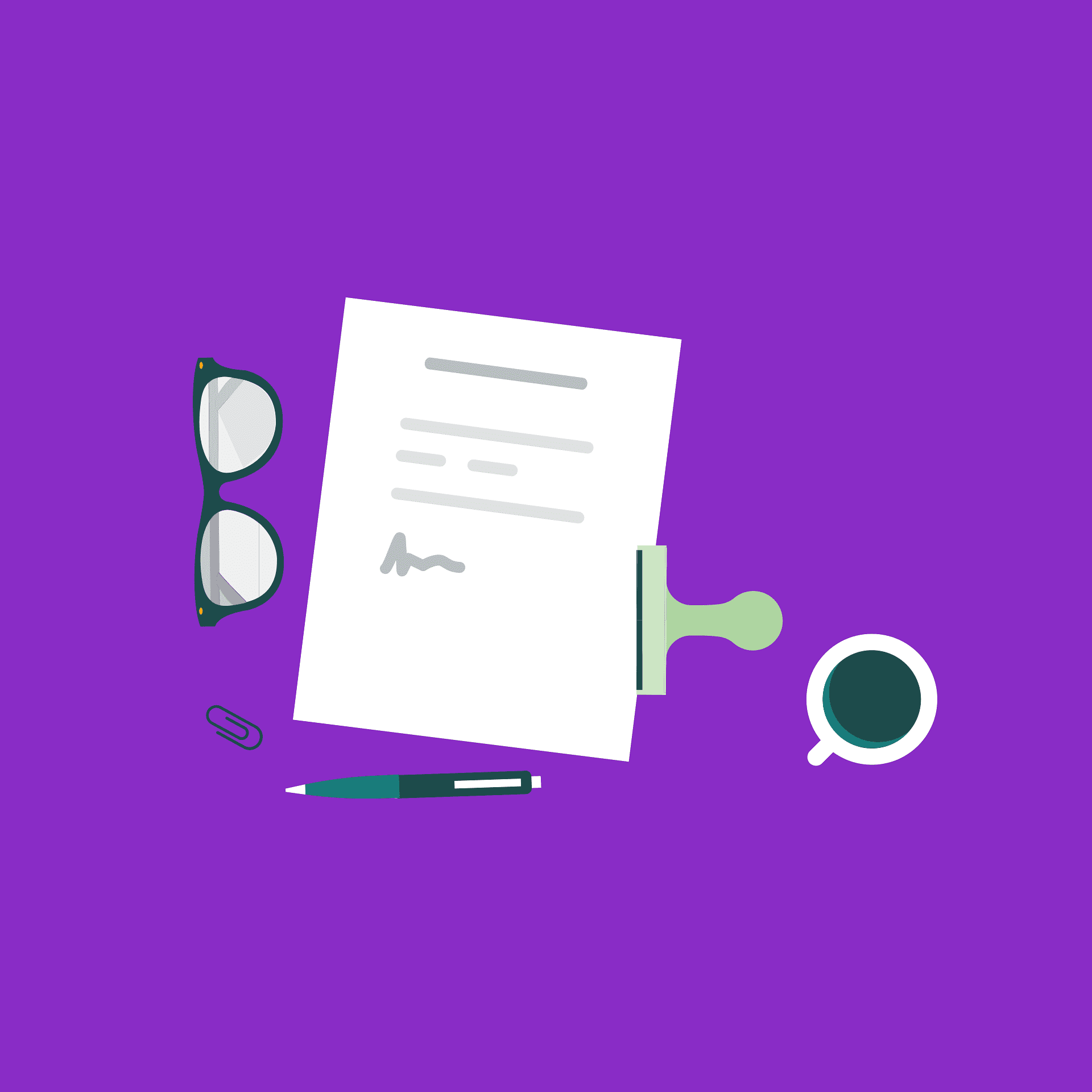
井深大・盛田昭夫|焼け跡から始まったソニーの奇跡
戦後の焼け跡で出会った二人
1946年5月、東京の焼け跡に建つ小さなバラック小屋で、井深大と盛田昭夫は運命的な出会いを果たした。井深は当時41歳、盛田は25歳。年齢差は16歳もあったが、「新しい技術で世の中を面白くしたい」という共通の夢で結ばれた二人だった。
井深は戦前から測定器の開発で知られた技術者で、盛田は愛知県の老舗酒造メーカー「盛田」の長男である。全く異なる背景を持つ二人だが、最初に会った時から意気投合し、その場で会社設立を決意したという。資本金はわずか19万円、従業員は20人という小さなスタートだった。
最初の大失敗と転機
創業当初の東京通信工業(後のソニー)は、まさに試行錯誤の連続だった。最初に手がけたのは電気炊飯器である。戦後の食糧難の時代に「電気で美味しいご飯を炊こう」という発想は素晴らしかったが、技術的な問題で商品化に失敗してしまった。
次に取り組んだのがテープレコーダーだった。アメリカで開発されたこの技術を日本に導入しようと考えたのだが、当時の日本人にはテープレコーダーの使い道がピンと来なかった。「音を録音して何に使うんだ?」という反応が大半だったのである。
しかし井深と盛田は諦めなかった。学校での語学教育、裁判所での会議録音、放送局での番組制作など、様々な用途を提案して回った。特に盛田は営業の天才で、自ら全国を飛び回って商品の良さを説明した。この地道な努力が実り、テープレコーダーは徐々に普及していったのである。
トランジスタラジオで世界へ
ソニーが世界的企業になる転機となったのが、1955年に発売されたトランジスタラジオである。当時のラジオは真空管を使った大型の製品が主流だったが、ソニーはトランジスタ技術を使って手のひらサイズの小型ラジオを開発した。
この商品の革新性は、サイズだけではない。従来のラジオは家庭の居間に置いて家族で聞くものだったが、トランジスタラジオは個人が持ち運んで楽しめる全く新しいメディア体験を提供したのだ。「音楽を外に持ち出す」という発想は、後のウォークマンにも通じる重要なコンセプトだった。
アメリカでの販売も大成功を収めた。盛田は自らニューヨークに乗り込み、現地の販売店を一軒一軒回って商品説明をした。「SONY」というブランド名も、この時に世界を意識して決められたものである。「誰でも発音できて、覚えやすい名前にしよう」という盛田の発想から生まれた。
1
2




























































































