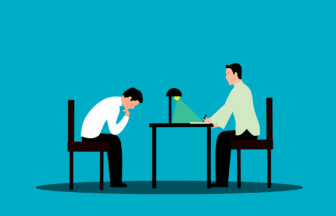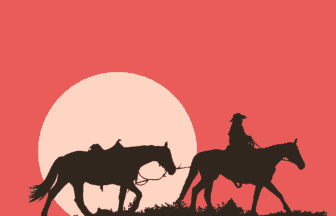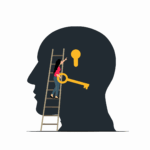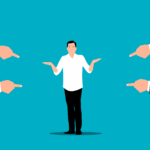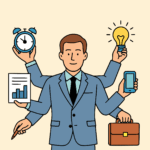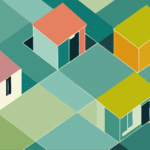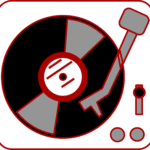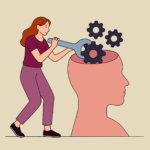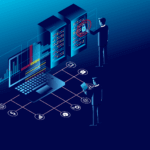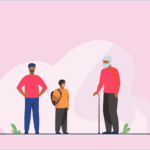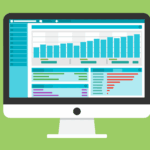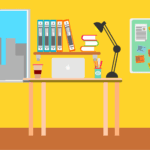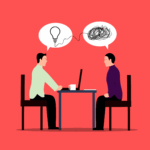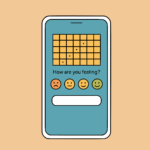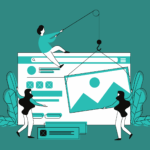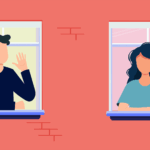「悪意のない悪意」がもたらす深い傷
今回の事例で最も問題なのは、おそらく学校側に明確な差別意識はなかったであろうという点です。むしろ「不登校の生徒にも参加してほしい」という思いはあったのだろうとは推測します。しかし、結果として生じた対応は、不登校の生徒たちに負のメッセージを伝えてしまいました。
これが「悪意のない悪意」の恐ろしさです。明確な悪意や差別意識がなくても、無意識の思い込みや配慮の欠如が、人を深く傷つけることがあります。特に立場の弱い人々に対しては、この「悪意のない悪意」が思いがけない形で表れ、彼らの心に長く残る傷を残すことがあるのです。
空気を読むことを重視するこの世の中では、明示的な排除よりも暗黙の排除が多く見られるような感覚値があります。誰も明確に排除しようとしていなくても、結果として排除が生じる状況は、日本社会の様々な場面で見られるものです。
必要なのは「想像力」と「準備」
では、このような問題を防ぐために必要なものは何でしょうか。それは一言で言えば「想像力」です。不登校の生徒たちがどのような思いで卒業式に参加するのか、彼らにとって何が必要なのかを想像する力が教育者には求められます。
また同時に重要なのは「準備」です。教育現場では様々な予期せぬ事態が起こり得ますが、基本的な準備と臨機応変な対応によって、多くの問題は防ぐことができるはずです。特に卒業式のような重要な行事では、事前に様々なシナリオを想定し、必要な物品や対応策を用意しておくことが不可欠です。
これは決して難しいことではなく、出席予定者数に若干の余裕を持たせて椅子を用意しておくだけで、今回のような事態は防げたはずです。また、不登校の生徒たちがより安心して参加できるよう、事前に声かけをしたり、座席の配置に配慮したりといった細やかな準備も考えられます。
教育の本質を問い直す機会に
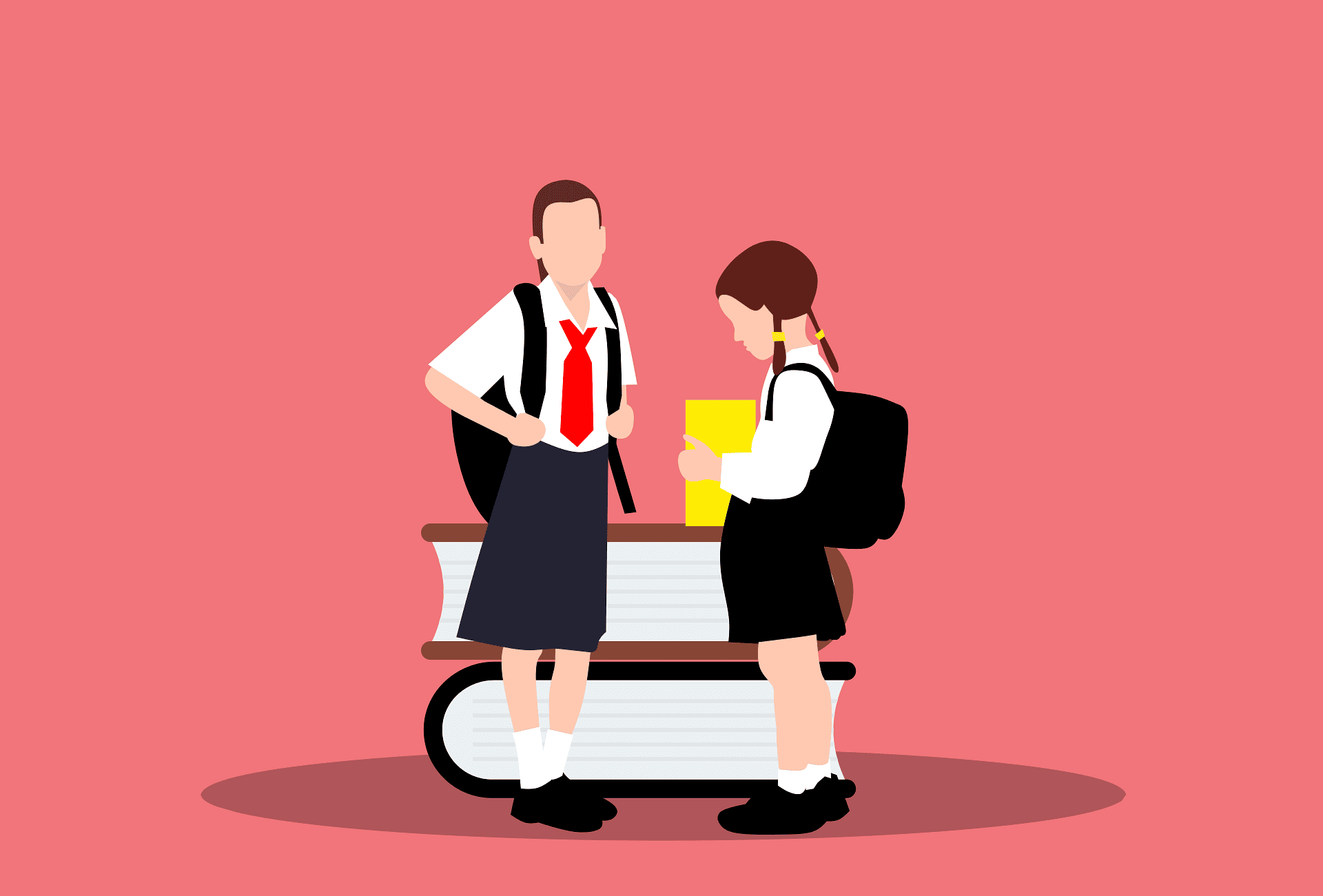
この事例は、一つの学校での出来事に留まらず、教育のあり方全体を問い直す機会となるべきではないでしょうか。教育の目的は何か、学校は誰のためにあるのか、卒業式の意義は何か—こうした根本的な問いに立ち返ることが必要です。
教育哲学者のジョン・デューイは「教育とは、子どもたちが自分自身の可能性を発見し、それを最大限に伸ばしていくプロセスを支援すること」と述べています。この観点から見れば、卒業式は単なる儀式ではなく、一人ひとりの生徒が自らの成長を実感し、次のステージへの希望を見出す貴重な機会のはずです。
不登校であっても、義務教育9年間の節目を迎えた生徒たちには、その機会が平等に与えられるべきです。平均台に座らされるという体験は、彼らからその貴重な機会を奪ってしまったかもしれません。
変化のきっかけとしての「気づき」
今回の出来事から学ぶべきことは多くありますが、最も重要なのは「気づき」ではないでしょうか。私たちの社会には、まだ多くの「悪意のない悪意」が存在しています。それらに気づき、改善していくことが、真に包括的な教育環境を作るための第一歩となります。
「配慮が足りなかった」という言葉を、謝罪の言葉として受け流すのではなく、教育現場全体が変わるきっかけとして捉えたいものです。一人ひとりの教育関係者が、自らの無意識の偏見や思い込みを見つめ直す機会となれば、今回の出来事も無駄にはならないでしょう。
まとめ|すべての卒業生に等しい尊厳を
卒業式は、義務教育の締めくくりとして、すべての卒業生にとって特別な意味を持つ儀式です。そこでは、どんな事情があろうとも、すべての生徒が等しく尊厳を持って扱われるべきです。今回の事例は、その当たり前のことが実現できていなかった現実を私たちに突きつけました。
不登校の生徒たちは、様々な理由から学校という場所と距離を置いてきました。しかし、彼らも立派な卒業生であり、同じ学び舎で同じ時間を過ごした仲間です。卒業式という人生の大切な節目に、彼らが平均台に座らされるという体験をしたことは、私たち社会全体の問題として受け止める必要があります。
子どもたちは鋭い観察者です。周囲の大人の何気ない言動や態度から、自分がどのように見られているかを敏感に感じ取ります。不登校の生徒たちに椅子ではなく平均台を用意したという行為は、意図せずとも「二次的な存在だ」というメッセージを伝えてしまったかもしれません。
しかし、この事例をきっかけに多くの学校や教育関係者が自らの姿勢を見つめ直し、すべての子どもたちを等しく大切にする教育のあり方を模索するならば、今回の出来事も無駄ではなかったと言えるでしょう。それを解消していく努力こそが、真の教育の姿なのです。
2