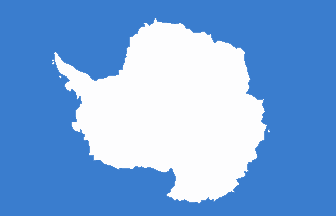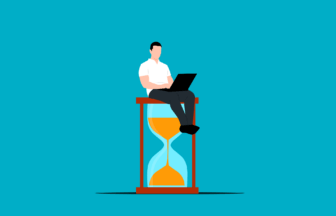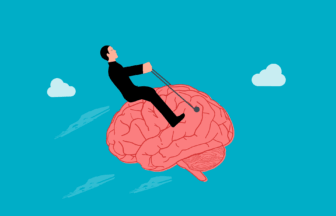ステルス値上げ、私たちが気付かぬ間に・・・
毎日の買い物で、「あれ?この商品、前より少なくなってない?」と感じたことはないだろうか。実は、多くの商品で内容量が減っているのに、値段は変わっていないという現象が起きている。これが「ステルス値上げ」だ。
スーパーやコンビニの棚に並ぶ商品を見ると、一見何も変わっていないように見える。しかし、よく見ると内容量が減っていたり、枚数が少なくなっていたりする。企業は「価格据え置き」と言うが、実は私たちの財布には確実に影響が出ているのだ。
なぜこのような状況が起きているのか。そして、私たち消費者はどのように対応していけばいいのか。商品の選び方から家計の管理まで、この物価上昇の時代を賢く生きていくためのヒントを探っていきたい。
ステルス値上げとは?
ステルス値上げとは、商品の内容量や個数を減らしながら価格を据え置く、あるいはわずかな値下げにとどめる企業の価格戦略である。「量目減量」や「実質値上げ」とも呼ばれ、消費者に価格上昇を気づかれにくくする手法として近年特に注目されている。

この価格戦略が採用される背景には、原材料費の高騰や人件費の上昇といった企業のコスト増加がある。しかし、競争が激しい市場において、直接的な値上げは消費者の反発や売上減少につながる可能性が高い。そのため企業は、商品の価格を維持しながら内容量を減らすことで、実質的な値上げを実現しようとしているのだ。
現在の日本市場では、菓子類や飲料、日用品など、幅広い商品カテゴリーでステルス値上げが確認されている。例えば、従来150gだった菓子が140gに減量されても、パッケージデザインはほとんど変更されず、価格も据え置かれる。また、ティッシュペーパーやトイレットペーパーでは、1箱あたりの枚数が減少しているケースが報告されている。
また近年では、住宅等の建築物においても、国の最新の調査では1住宅あたりの面積がピーク時から狭くなっているという結果も出ているとの話である。住宅が狭くなってしまうと、結婚そのものや、家族の住設計に影響が出てしまうのではないかと懸念する。
企業側は「原材料費高騰による負担を軽減するため」「品質維持のための苦渋の決断」といった説明を行うことが多い。しかし、これらの説明は必ずしも消費者に十分に伝わっているとは言えず、商品パッケージの目立たない場所に小さく記載されるのみであることも少なくない。
このような状況は、消費者の購買行動や商品選択に影響を与えている。特に、日常的に購入する商品の場合、消費者は価格を基準に商品を選択する傾向が強いため、内容量の変化に気づきにくい。そのため、実質的な価格上昇が家計に及ぼす影響を正確に把握することが困難になっているのが現状である。

対応策はあるのか?
筆者も良くスーパー等で買い物をしている消費者としての視点から、ステルス値上げへの対応策と生活の質を維持するための方策を提案したいと思う。
1
2