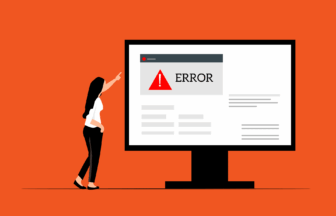過度な配慮が生み出す新たな組織リスク
過度な配慮が生み出す新たな組織リスク
現代の日本企業において、ハラスメント問題への意識は確実に高まっている。パワーハラスメント防止法の施行、メディアでの報道増加、そして働き方改革の浸透により、多くの管理職が部下との接し方に細心の注意を払うようになった。これは確実に組織文化を良い方向に変化させている一方で、新たな問題を生み出している現実がある。
「部下を叱ることができない」「厳しい指導をするとハラスメントと言われるのではないか」そんな不安を抱える管理職は少なくない。その結果、本来必要な指導や叱責を避け、問題を先送りする風潮が一部の組織で見られるようになっている。これは一見すると働きやすい環境のように思えるが、実際には組織全体の成長を阻害し、最終的には従業員にとってもマイナスの結果をもたらす可能性が高い。
適切な指導と不適切なハラスメントの境界線を理解し、健全な組織運営を実現することは、現代の管理職に求められる重要なスキルである。本コラムでは、叱ることを恐れた組織で実際に起こる問題について、具体的な事例とともに詳しく解説していく。
問題1|成長機会の喪失が招く組織全体の停滞
叱ることを恐れた組織で最初に現れる問題は、従業員の成長機会の著しい減少である。これは単純に「厳しくされないから楽になる」という表面的な話ではない。人間の成長には適度な負荷とフィードバックが不可欠であり、それが欠如した環境では組織全体が停滞状態に陥ってしまう。
具体的な例を挙げよう。ある中堅IT企業では、過去にパワハラ問題が発生したことをきっかけに、管理職が部下への指導を極端に控えるようになった。新人プログラマーがコードレビューで明らかなミスを犯しても、「本人が気づくまで待とう」という姿勢を貫いた結果、同じミスが数か月間繰り返された。最終的にはクライアントからのクレームに発展し、プロジェクト全体が遅延する事態となった。
この事例が示すように、適切な指導を避けることは、短期的には人間関係の摩擦を回避できるかもしれないが、長期的には組織全体のパフォーマンス低下を招く。特に新入社員や若手社員にとって、適切なフィードバックを受ける機会は貴重な学習機会である。上司からの指導がなければ、彼らは自分の弱点や改善点を把握することができず、成長の機会を逸してしまう。
さらに深刻なのは、この状況が組織文化として定着してしまうことである。「ここの会社は甘い」という認識が広まると、向上心のある優秀な人材は物足りなさを感じて離職し、逆に現状維持を好む人材ばかりが残る傾向が生まれる。これは組織の競争力を根本から損なう重大な問題である。
成長機会の喪失は、個人レベルでも深刻な影響をもたらす。適切な挑戦や指導を受けずに過ごした従業員は、いざ転職活動を行う際に自身のスキル不足に直面することになる。結果的に、「優しい会社」にいたはずの従業員が、長期的には不利な立場に置かれてしまうという皮肉な状況が生まれる。
問題2|責任感の欠如と当事者意識の低下
叱られることを恐れた組織では、従業員の責任感と当事者意識が著しく低下する現象が見られる。これは心理学的にも説明可能な現象で、適度な緊張感や責任感が欠如した環境では、人は自然と楽な方向に流れてしまう傾向がある。
ある製造業の工場では、品質管理の責任者が部下のミスを指摘することを避けるようになった結果、検査工程での見落としが頻発するようになった。従業員たちは「どうせ誰も怒らない」という認識を持つようになり、検査作業の精度が明らかに低下した。最終的には出荷後に不良品が発見され、大規模なリコール騒動に発展してしまった。
この事例が示すのは、適切な緊張感と責任感が組織運営において果たす重要な役割である。人間は本能的に「楽をしたい」と思う生き物であり、外部からの適度なプレッシャーがなければ、自然とパフォーマンスが低下してしまう。これは決して従業員の人格的な問題ではなく、組織構造上の問題として捉える必要がある。
責任感の欠如は、チームワークにも悪影響を及ぼす。自分の担当業務に対する責任感が薄れると、他のメンバーとの連携も疎かになりがちである。「自分がやらなくても誰かがやってくれるだろう」という思考が蔓延すると、組織全体の生産性が大幅に低下してしまう。
そして、このような環境で育った従業員が、将来的に管理職になった際の問題である。責任感や当事者意識の薄い状態で管理職になると、部下に対して適切な指導や責任の所在を明確化することができない。結果として、組織全体が「なあなあ」の文化に染まってしまい、競争力を失っていく危険性がある。
問題3|コミュニケーション能力の退化と職場の表面化
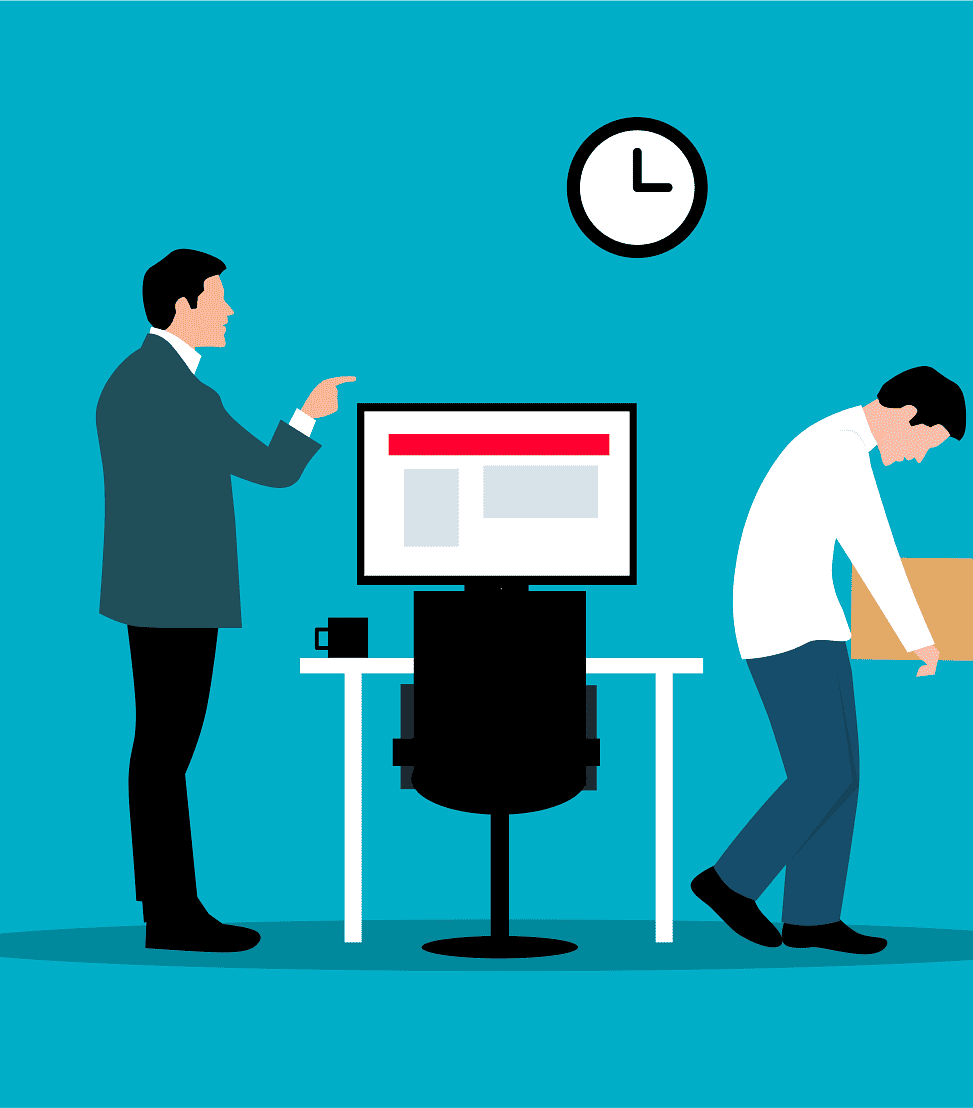
叱ることを恐れた職場では、深刻なコミュニケーション能力の退化が進行する。これは単純に「会話が減る」という問題ではなく、組織内での本質的な議論や建設的な対立を避ける文化が形成されることを意味する。
具体例として、ある広告代理店では、クリエイティブな議論を重視していたにも関わらず、ハラスメントを恐れるあまり、上司が部下の企画案に対して厳しい指摘をしなくなった。その結果、表面的な褒め言葉ばかりが飛び交い、本当に必要な改善点や問題点が議論されなくなった。最終的には、クライアントから「提案のレベルが下がった」という厳しい評価を受けることになった。
このような環境では、「察する文化」や「空気を読む」ことが過度に重視され、率直な意見交換が困難になる。表面上は平和に見えるかもしれないが、実際には重要な問題が水面下に隠れてしまい、いざ表面化した時には手遅れになっているケースが多い。
コミュニケーションの表面化は、特に若手社員にとって深刻な問題である。本来であれば、上司との議論や時には厳しい指摘を通じて、論理的思考力やコミュニケーション能力を向上させるはずが、その機会が奪われてしまう。結果として、社会人として必要なスキルが身につかないまま年数だけが過ぎてしまう。
また、この問題は組織の革新性にも大きな影響を与える。新しいアイデアや改善提案は、往々にして既存の方法に対する批判や疑問から生まれる。しかし、そのような「異議申し立て」がタブー視される環境では、イノベーションの芽が摘まれてしまう。競争が激化する現代のビジネス環境において、これは組織の生存に関わる重大な問題である。
問題4|優秀な人材の流出と組織の質的劣化
叱ることを恐れた組織では、皮肉なことに最も価値のある人材から離れていく現象が起こる。これは「優秀な人材ほど成長機会を求める」という人材心理に基づいた現象である。
実際のケースとして、ある金融機関では、リスク管理部門において上司が部下への厳しい指導を控えるようになった結果、向上心の高い若手アナリストが次々と転職していった。彼らの離職理由は「成長できない環境」「挑戦的な仕事がない」というものだった。一方で、現状に満足している、あるいは変化を好まない職員は残り続けた。
この現象は「逆淘汰」と呼ばれる組織論上の問題である。本来であれば組織にとって最も価値のある人材が流出し、相対的に価値の低い人材が残る構造が形成される。これは組織の長期的な競争力を根本から損なう深刻な問題である。
優秀な人材が流出する理由は複数ある。一つは、自分自身の成長を重視するため、適切なフィードバックや挑戦的な課題がない環境では満足できない。そして優秀な人材は往々にして高い責任感を持っているため、緊張感のない環境に居心地の悪さを感じる。また、彼らは将来のキャリアを見据えているため、スキルアップの機会がない組織に留まることのリスクを理解している。
優秀な人材の流出が加速度的に進行するということで、例えば一人の優秀な社員が転職すると、その人とのネットワークを持つ他の優秀な社員も連鎖的に転職を検討し始める。また、優秀な人材が抜けた穴を埋めるために、残った社員に過度な負担がかかり、それがさらなる離職を招くという悪循環が生まれる。
この問題の解決は容易ではない。一度「甘い組織文化」が定着してしまうと、それを変革するためには相当な時間と労力が必要になる。また、質の低い人材ばかりが残った組織では、変革を推進できるリーダーシップ自体が不足している場合が多い。
1
2