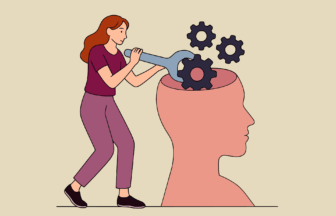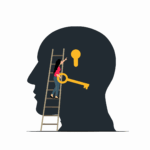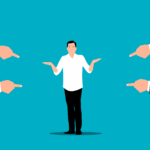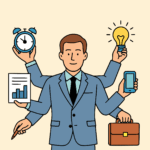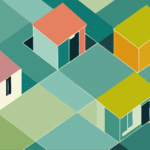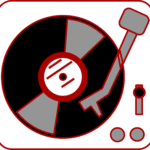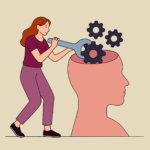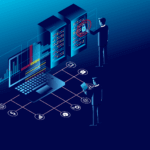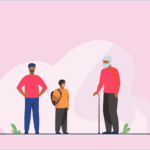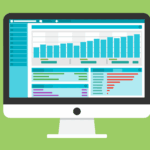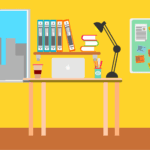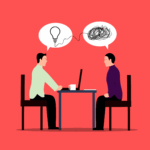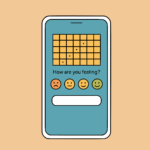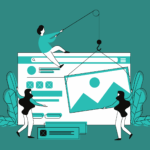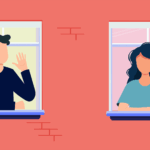流行という名の蜃気楼
現代社会は「次世代の○○」「革命的な△△」という言葉に溢れている。スタートアップ企業が颯爽と登場し、メディアがこぞって取り上げ、SNSでバズり、そして気づけば誰も話題にしなくなる。この繰り返しを、私たちは何度目撃してきただろうか。
流行というものは本来、人々の生活に新しい風を吹き込む可能性を秘めている。しかし実際には、その大半が定着することなく消えていく。それは決して偶然ではなく、ある種の構造的な問題を抱えているからだ。今回は、すぐに衰退してしまう流行りモノに共通する特徴を20個挙げながら、本当に定着するプロダクトやサービスとは何が違うのかを考察していく。
1.コンセプトの「美しさ」だけで突っ走る危うさ
衰退が速い流行りモノの特徴として久しいのは、コンセプトが美しすぎることだ。これは一見矛盾しているように聞こえるかもしれない。しかし、プレゼンテーション資料やプロモーション映像で描かれる理想的な未来像と、実際のユーザー体験との間に深い溝がある場合、その落差が致命傷となる。
例えば、かつて「スマートグラス」として鳴り物入りで登場した製品群を思い出してほしい。プロモーション映像では、街を歩きながら情報が目の前に浮かび上がり、手をかざすだけで買い物ができる未来が描かれていた。しかし現実は、バッテリーが2時間しか持たず、デザインは不格好で、周囲からの視線も気になる。理想と現実のギャップが大きすぎたのだ。
定着するプロダクトは、むしろコンセプトを控えめに語り、実際の体験で期待を超えてくる。アップルのiPhoneが初めて登場したとき、スティーブ・ジョブズは「電話、インターネット、音楽プレイヤー」という極めてシンプルな説明をした。しかし実際に触れてみると、その体験は想像を遥かに超えていた。このギャップの方向性が、定着の鍵を握っている。
2.解決すべき「問題」が実は存在しない
誰も困っていない問題を解決しようとすることである。シリコンバレーでよく聞かれる言葉に「ソリューション・イン・サーチ・オブ・ア・プロブレム(問題を探すソリューション)」というものがある。これは皮肉を込めた表現で、技術やアイデアが先行し、後付けでニーズを探しているプロダクトを指す。
ジュースを自動で絞る高額な機械、ボタン一つで特定の商品を注文できるIoTデバイス、AIを使った自動作曲サービス。これらは確かに面白い技術だが、多くの人にとって「なくても困らない」ものだった。ジュースは手で絞れるし、スマホで注文すれば済む。音楽は人間が作った方が心に響く。
一方、定着したサービスを見ると、明確な「痛み」を解決している。メルカリは、不用品の処分という面倒な作業を楽しいものに変えた。Slackはメールとチャットツールが混在する混乱を整理した。人々が日常的に感じている小さなストレスやイライラこそが、ビジネスの種なのだ。
3.使い続けるための「理由」が弱い
初回体験は良くても、リピートする動機が弱いこと。多くの流行りモノは、最初のインパクトに全力投球する。ダウンロードしてもらうため、試してもらうために、派手なキャンペーンや無料期間を用意する。しかし、その後が続かない。
動画配信サービスの乱立がいい例だ。各社が独自コンテンツを用意し、無料トライアルで加入者を集める。しかし、見たいコンテンツを見終わったら解約される。なぜなら、その先に継続する理由がないからだ。一方、NetflixやSpotifyが定着したのは、アルゴリズムによるレコメンデーションで「次に見るもの」を常に提案し続けたからだ。使えば使うほど精度が上がり、離れる理由が減っていく。
定着するプロダクトには、ユーザーが投資した時間やデータが蓄積され、それが参入障壁になる仕組みがある。Evernoteにメモを溜め込んだ人は、他のメモアプリに移行するのが億劫になる。Spotifyでプレイリストを作り込んだ人は、Apple Musicに移るのを躊躇する。この「スイッチングコスト」の設計が、継続利用の鍵となる。
4.価格設定の致命的なミスマッチ
提供価値と価格が釣り合っていないことだ。特にスタートアップは、開発コストや調達した資金を回収しようと、ユーザーが感じる価値以上の価格を設定してしまうことが多い。
月額課金モデルの落とし穴もここにある。一つ一つは数百円、数千円でも、気づけばサブスクリプションが10個、20個と積み重なり、ユーザーは「サブスク疲れ」に陥る。そして、最も使用頻度が低いものから順に解約していく。ここで生き残るのは、明確に価値を感じられるサービスだけだ。
無料でも衰退するサービスはある。これは金銭的コストではなく、時間的コストや心理的コストが高すぎる場合に起こる。新しいSNSが次々と登場するが、ほとんどが定着しない理由がここにある。すでにInstagram、X(旧Twitter)、TikTokと複数のSNSを使い分けている人にとって、新しいプラットフォームで一から人間関係を構築する労力は、無料であっても「高すぎる」のだ。
5.マーケティングに頼りすぎた虚構
マーケティングの力で無理やり流行を作り出そうとすること。インフルエンサーを総動員し、広告を大量出稿し、話題性だけで押し切ろうとする。しかし、中身が伴っていなければ、熱狂は一瞬で冷める。
「バズる」ことと「定着する」ことは全く別物だ。バズは瞬間風速であり、話題になること自体が目的化してしまう。一方、定着には地道な口コミと、実際に使った人の満足度が必要だ。GoogleやAmazonが莫大な広告費を使わずに成長したのは、プロダクト自体の品質が高く、自然と広がっていったからだ。
マーケティングが悪いわけではない。しかし、それは美味しい料理をより多くの人に知ってもらうための手段であって、まずい料理を無理やり食べさせる魔法ではない。順序を間違えてはいけないのだ。
6.使用体験の「摩擦」が多すぎる
使い始めるまでのハードルが高いこと。アカウント登録、個人情報入力、クレジットカード情報、初期設定、チュートリアル。これらのステップが多ければ多いほど、途中で離脱する人が増える。
かつて流行ったQRコード決済の乱立を思い出してほしい。各社が独自のアプリをリリースし、それぞれで登録が必要だった。店頭で「このQRコードはどのアプリに対応していますか?」と確認するやり取りが発生し、結局現金やクレジットカードの方が早いという結論に至った人も多い。利便性を提供するはずのサービスが、むしろ不便を生んでいたのだ。
定着するプロダクトは、この摩擦を徹底的に削減する。Googleアカウントでログイン、ワンクリック購入、顔認証でのアクセス。ユーザーが意識しないうちに、体験が始まっている。AmazonのCEOジェフ・ベゾスが「ワンクリック購入」の特許を取得したのは、この摩擦の削減がいかに価値があるかを理解していたからだ。
7.プラットフォームとしての「閉鎖性」
他のサービスと連携できない閉じた世界を作ってしまうこと。スマートホーム製品がいい例だ。各メーカーが独自の規格を作り、自社製品でしか動かない仕組みを構築した。結果、ユーザーは一つのメーカーに縛られ、新しい製品を買うたびに互換性を気にしなければならなくなった。
これに対して、MatterやThreadといったオープンな規格が登場し、徐々に支持を集めている。なぜなら、ユーザーは自由を求めるからだ。最良の製品を自由に選び、組み合わせたい。その自由を奪うプロダクトは、初期は囲い込みに成功しても、長期的には競争力を失う。
iPhoneが成功したのは、App Storeという開かれたエコシステムを作ったからだ。Apple単独では開発できない膨大な数のアプリが、無数の開発者によって生み出された。プラットフォームとして開くべき部分と閉じるべき部分を見極めることが、定着の条件となる。
8.ターゲットの「誤認」という根本的過ち
本当のターゲット層を見誤っていること。多くの流行りモノは、アーリーアダプターと呼ばれる新しいもの好きな層に受け入れられる。彼らは喜んで試用し、SNSで拡散してくれる。しかし問題は、彼らと一般層(アーリーマジョリティやレイトマジョリティ)の間には「キャズム(深い溝)」があることだ。
VR(仮想現実)ヘッドセットの例が分かりやすい。ゲーム好きやテクノロジーマニアは飛びついた。しかし、一般層に広がらない。なぜなら、一般の人々が求めているのは「VR体験」ではなく、「家族と楽しい時間を過ごすこと」や「リラックスすること」だからだ。技術そのものではなく、それがもたらす結果に興味がある。
任天堂Switchが成功したのは、このキャズムを理解していたからだ。ゲーマーだけでなく、家族全員が楽しめる設計。持ち運べて友達の家でも遊べる柔軟性。複雑な設定が不要なシンプルさ。これらは全て、一般層のニーズを深く理解した結果である。
9.「新しさ」だけが売りになってしまう危険性
新規性以外にアピールポイントがないこと。「世界初」「業界初」という言葉は確かに注目を集める。しかし、それだけでは不十分だ。なぜなら、新しいこと自体には価値がなく、それが生活をどう改善するかに価値があるからだ。
3Dテレビを覚えているだろうか。メーカーは「映像体験の革命」として大々的に宣伝した。確かに新しかった。しかし、専用のメガネをかけなければならない煩わしさ、長時間視聴による疲労、コンテンツの不足。これらの問題を解決しないまま、新規性だけで押し切ろうとした結果、数年で市場から消えた。
一方、4Kテレビは定着した。なぜなら、ユーザーは特別なことをしなくても、ただ美しい映像を楽しめるからだ。新しさは入口に過ぎず、使い続ける理由が本質なのだ。
10.タイミングという残酷な現実
市場に出るタイミングが早すぎるか遅すぎること。イノベーションには適切な「熟成期間」がある。技術は完成していても、社会がそれを受け入れる準備ができていなければ失敗する。逆に、タイミングを逃せば、すでに市場は別の解決策を見つけている。
電子書籍端末が良い例だ。ソニーは2004年にLibrieという電子書籍端末を日本で発売した。しかし普及しなかった。一方、Amazonが2007年に米国でKindleを発売したときは爆発的にヒットした。わずか3年の差だが、この間にブロードバンドが普及し、オンライン購買が一般化し、デジタルコンテンツへの抵抗感が薄れた。同じような製品でも、タイミングが全てを変える。
定着するプロダクトは、技術の成熟度、市場の準備状態、競合の動向、規制環境など、複数の要素が揃うタイミングを見極めている。ビル・グロスというベンチャーキャピタリストは、スタートアップの成功要因を分析し、「タイミング」が42%を占めると結論づけた。アイデアやチーム、資金よりも、タイミングが重要なのだ。
1
2