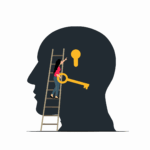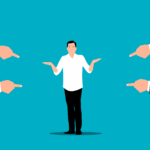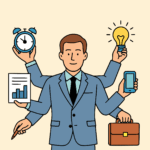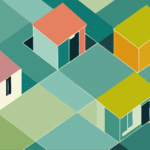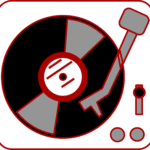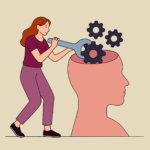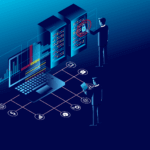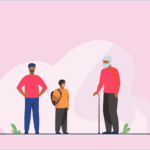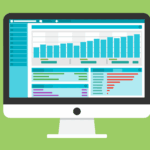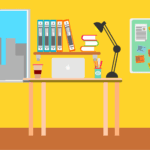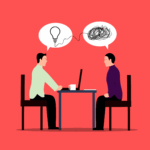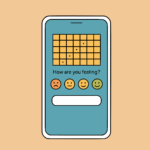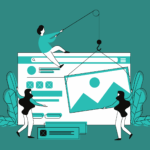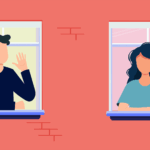あの頃、レジで計算がこんなにもシンプルだった理由
「100円です」と店員が言えば、本当に100円だった。消費税導入前の日本では、価格表示と支払額が完全に一致していた。今では当たり前になった「税込○○円」という表示も、レジで小銭が中途半端に増えていく感覚も、1989年4月以前の日本には存在しなかった。
消費税が導入される前、つまり昭和から平成初期にかけての日本では、買い物の計算は驚くほど明快だった。子供が駄菓子屋で10円玉を握りしめて向かえば、10円のお菓子が確実に買えた。自動販売機のジュースは100円なら100円、120円なら120円きっかりで、財布の中身と相談するのも簡単だった。
当時の商店街を思い出してほしい。八百屋では「キャベツ一玉150円」と手書きの札が立っていた。その150円を払えば取引は完了する。魚屋でも、肉屋でも同じだった。価格に対する信頼がシンプルで、消費者も店主も余計な計算に頭を悩ませる必要がなかった。
この明快さは、計算の簡単さ以上の意味を持つ。価格と価値が直結していたのである。1000円の価値は1000円分の商品やサービスであり、そこに付加される税という概念が介在しなかった。金銭感覚を養う上でも、この明確さは重要だった。子供たちは自分の小遣いで何が買えるか、正確に把握できたのである。
「端数」という概念が生まれた日
消費税導入は、日本人の財布の中身を劇的に変えた。それまで比較的すっきりしていた小銭入れが、突如として1円玉と5円玉で溢れかえるようになったのである。
1989年4月1日、消費税率3%でスタートした新制度は、あらゆる価格に3%を上乗せした。100円の商品は103円に、500円のランチは515円になった。この「中途半端な数字」が日本中に出現したのである。スーパーのレジでは、それまで見たこともないような端数の合計金額が表示されるようになった。
特に影響を受けたのが自動販売機業界である。当時の自動販売機は100円玉と10円玉しか受け付けない機種がほとんどだった。消費税導入により、飲料メーカーは難しい選択を迫られた。100円の缶ジュースに3%を加えると103円になるが、自動販売機を全て改修するには膨大なコストがかかる。結果として多くのメーカーは価格を据え置き、実質的に自社で消費税分を負担する選択をした。やがて自動販売機は110円、120円といったキリの良い数字に落ち着いていくが、それでも従来の100円という価格から変わってしまったことへの消費者の違和感は大きかった。
財布の重さも変わった。それまで500円玉や100円玉が中心だった小銭が、1円玉や5円玉の比率が急増したのである。レジで「1,234円です」と言われれば、多くの人が1,240円や1,250円を出してお釣りをもらう習慣が生まれた。端数を減らそうとする努力が、日本人の日常に組み込まれていった。
価格表示の裏にあった「正直さ」
あの時代の価格表示には、ある種の潔さがあった。店が提示する価格が、そのまま消費者が支払う金額だったからである。
昭和の商店では、値札に書かれた数字がすべてだった。「この品物の価値は○○円」という店側の判断が、そのまま取引価格となる。駆け引きはあっても、それは売り手と買い手の間で行われるものであり、そこに第三者としての税金が介在することはなかった。
デパートの価格表示も明快で。ワンピースが5,800円なら、財布に6,000円あれば確実に買えた。レストランのメニューに「ビーフカレー600円」とあれば、600円が財布に入っていれば注文できた。この明快さは、消費行動における心理的な負担を大きく軽減していた。
また、価格競争もわかりやすい。隣の店が98円で売っているなら、うちは95円で売ろうという競争が繰り広げられた。消費者も「あの店は3円安い」という判断が即座にできた。税金を含めた実質価格を計算する必要がなかったのである。
さらに「端数」を使った心理的な価格設定が、今ほど一般的ではなかったことである。現在では「1,980円」のように、わざと2,000円を下回る価格設定をすることで安く見せる手法が当たり前だが、消費税導入前はむしろキリの良い価格が好まれた。「2,000円」「3,000円」という価格の方が、取引における信頼感を醸成したのである。
給料日の「重み」が違った時代
消費税導入前の給料明細は、今よりもシンプルだった。もちろん所得税や社会保険料は引かれていたが、日常の買い物で追加の税負担がない分、手取り額に対する実感が違っていた。
当時のサラリーマンにとって、月給20万円は「20万円分の購買力」を意味した。現在のように、消費する度に実質的な価値が目減りしていく感覚はなかった。給料日に受け取った金額で、その月の生活設計をそのまま立てることができたのである。
特に大きな買い物をする際、この差は顕著だった。10万円の家電製品を買うために、10万円を貯めれば良かった。現在のように「10万円の商品だから、実際には10万8千円必要だな」という計算をする必要がない。目標額と実際の支出額が一致していたのである。
この時代、百貨店の外商担当者との会話も今とは違っていた。「奥様、こちらの着物、30万円でございます」と言われれば、それがそのまま支払額だった。高額商品であればあるほど、この差は大きく感じられた。30万円なら30万円、50万円なら50万円と、提示された価格への信頼が絶対的だったのである。
また、ボーナスの使い道を考える際も計算が楽だった。「ボーナス50万円が出たら、20万円で旅行に行って、15万円で家具を買って、残りは貯金しよう」という計画が、わかりやすく実行できた。税金による目減りを考慮に入れる必要がなかったため、計画と実行の間にズレが生じにくかったのである。
子供の金銭教育が「純粋」だった理由
消費税のない時代に育った子供たちは、お金の計算を極めてシンプルに学ぶことができた。
小学生が100円玉を握りしめて駄菓子屋に行く。棚には10円、20円、30円のお菓子が並んでいる。「10円のが5個で50円、20円のが2個で40円、合わせて90円。あと10円で何が買えるかな」という計算が、そのまま現実の買い物として成立した。この純粋な算数の実践が、金銭感覚を育てる最良の教育だった。
親から子へのお小遣いも明快だった。「今月のお小遣いは500円ね」と渡されれば、その500円で何ができるか、子供は正確に把握できた。漫画雑誌が250円、アイスクリームが100円、ノート1冊が80円。自分の予算内で何が買えて何が買えないか、実に明確だった。
この時代の子供たちは、貯金の喜びも純粋に味わえた。「500円玉を10枚貯めたら5,000円だから、あの模型が買える」という目標設定が、そのまま達成可能だった。現在のように「5,000円の商品だから、実際には5,400円必要だな」と考える必要がなく、貯金目標と達成が一致していたのである。
お年玉の使い道を考える楽しみも、より純粋だった。祖父母から1万円をもらえば、その1万円で何を買おうか考える。ゲームソフトが6,800円、参考書が1,500円、残りは貯金という計画が、計算通りに実行できた。金銭教育における「計画」と「実行」のギャップが小さかったことは、子供たちの金銭感覚形成に大きく寄与していたのである。
商店街の値札に込められた「誇り」
昭和の商店街を歩くと、各店舗の値札には店主の個性と誇りが滲み出ていた。消費税という外部要因に左右されない、純粋な価格設定がそこにあった。
八百屋の店主が「今日の大根は150円」と値札を書く。その150円には、朝早く市場に出向いて目利きした大根の品質、自分の店の立地や客層、そして適正な利益を考慮した、店主の総合的な判断が込められていた。消費税による上乗せがない分、価格そのものが店主の哲学を表していたのである。
洋服店でも同様だった。「このワンピース、8,800円で出そう」と決めるとき、店主は生地の質、デザイン、縫製の丁寧さ、そして地域の相場を総合的に判断した。その8,800円という数字が、店の看板であり、信用でもあった。「うちは品質に自信があるから、この価格なんです」というメッセージが、値札を通じて顧客に伝わったのである。
街の定食屋も然りである。「カツ丼650円」という値札には、使用する豚肉の部位、米の品種、秘伝のタレの配合、そして何より「この価格で満足してもらいたい」という店主の意地が込められていた。消費税分を上乗せするという機械的な作業がない分、価格設定そのものに店主の哲学が反映されていたのである。
この時代の商店主たちは、価格を変更することに大きな責任を感じていた。「値上げをする」という決断は、今もそうだが原材料費の高騰や人件費の増加といった明確な理由が必要で、「消費税が上がったから」「なんか世間的に物価上昇が」という外部要因による値上げではなく、自分の店の経営判断として価格を決めることができた時代だったのである。
1
2