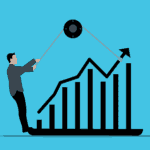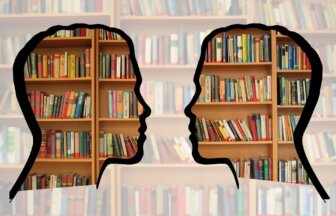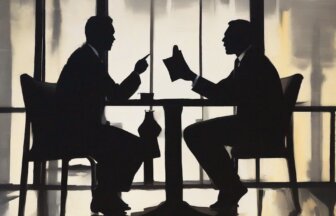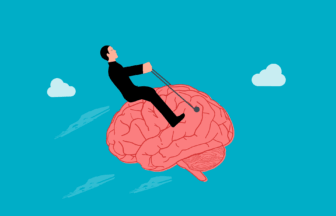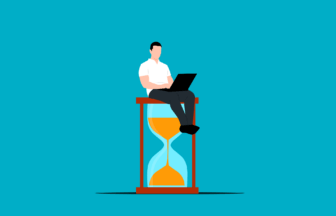優秀な人ほど「答える力」より「問う力」に長けている
会議で誰もが納得する提案をする人、取材で核心に迫る記者、顧客の本音を引き出す営業担当者。彼らに共通するのは、膨大な知識でも流暢な話術でもない。それは「的確な質問を投げかける力」である。
私たちは学校教育の中で「正しい答えを出す訓練」は受けてきたが、「正しい質問をする訓練」はほとんど受けていない。テストでは常に問題が与えられ、それに答える形式だった。しかし実社会では、問題そのものを発見し、適切な問いを立てることの方が圧倒的に重要だ。
グーグルの元CEOエリック・シュミットは「私たちは答えを持っている時代から、適切な質問を持つことが価値になる時代へ移行した」と語っている。情報があふれる現代において、答えそのものは検索すれば見つかる。だが、何を問うべきかを見極める力は、人間にしか持ち得ない。
質問力とは何か|表面を突き破る思考技術
質問力とは単に「疑問を投げかける能力」ではない。それは相手の思考を刺激し、隠れた真実を引き出し、問題の本質に迫るための高度な思考技術である。
優れた質問には三つの特徴がある。一つは、相手が「そこまで考えていなかった」と気づかされる深さがある。また、相手が答えたくなる、思わず考え込んでしまう磁力がある。そして、対話を前に進める推進力がある。
例えば新規事業の企画会議で「この商品は売れますか?」と聞くのは質問ではあるが、質問力があるとは言えない。これに対して「この商品を買う人は、購入する瞬間にどんな感情を抱いているでしょうか?」と問えば、チーム全体の思考が顧客の心理へと深く潜っていく。前者は単なる予測を求めているが、後者は本質的な顧客理解を促している。
質問力とは、相手の中に眠っている答えを掘り起こす技術であり、同時に自分自身の思考を研ぎ澄ます訓練でもある。なぜなら、的確な質問をするためには、問題の構造を深く理解し、何が本質で何が枝葉なのかを見抜く必要があるからだ。
なぜ今、質問力が求められるのか|変化する仕事の本質
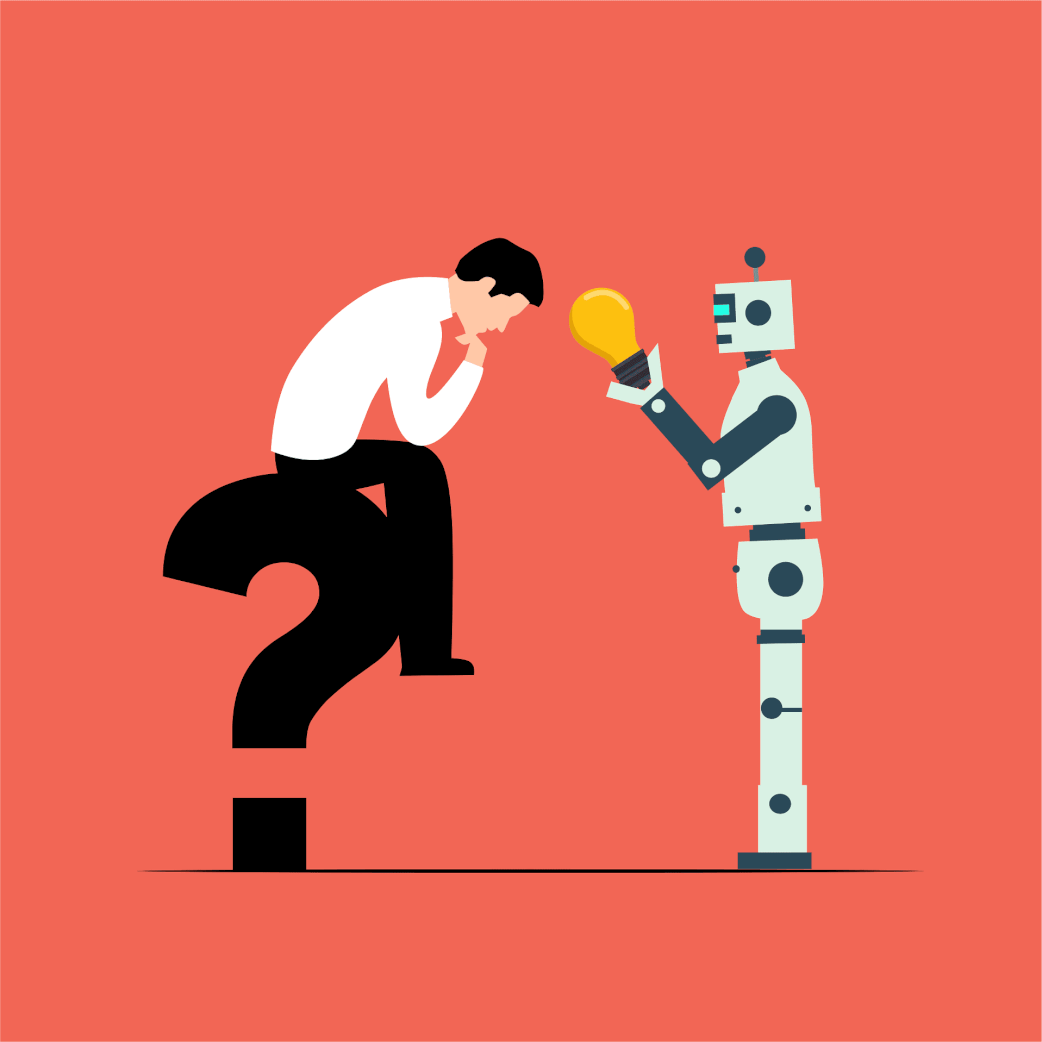
かつてのビジネスパーソンに求められたのは「指示通りに動く力」だった。上司からの命令を正確に理解し、効率的に実行することが評価された。しかし現代の仕事環境は根本的に変わった。
正解が一つではない問題が増えている。市場は複雑化し、顧客のニーズは多様化し、技術革新のスピードは加速している。こうした環境では、過去の成功パターンをなぞるだけでは通用しない。状況を正確に把握し、本質的な課題を特定し、新しい解決策を見出す力が必要だ。そのすべての出発点が「適切な問い」にある。
リモートワークの普及も質問力の重要性を高めている。オフィスで顔を合わせていれば、相手の表情や雰囲気から情報を読み取れたが、オンラインのコミュニケーションではそれが難しい。限られた時間と手段で本質的な情報を引き出すには、一つ一つの質問の精度を上げるしかない。
さらに言えば、AI時代の到来が質問力の価値を決定的にした。AIは膨大なデータから答えを導き出すことは得意だが、「何を問うべきか」を自律的に判断することはできない。人間がどんな質問をAIに投げかけるかによって、得られる答えの質が劇的に変わる。つまり質問力こそが、人間がAIを使いこなすための必須スキルなのだ。
質問の構造を理解する|五つの層を使い分ける
質問には深さのレベルがある。表面的な質問から本質を突く質問まで、少なくとも五つの層が存在する。これを理解することが、質問力向上の第一歩だ。
1
2