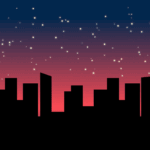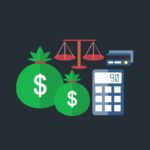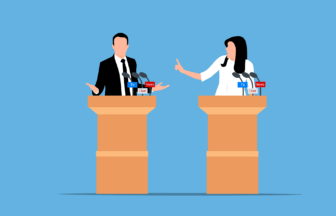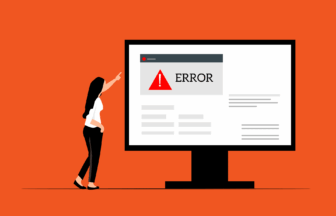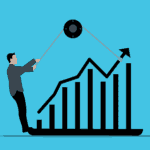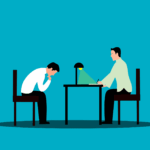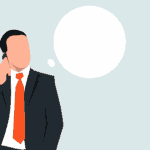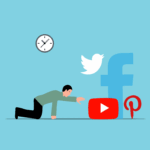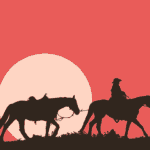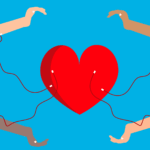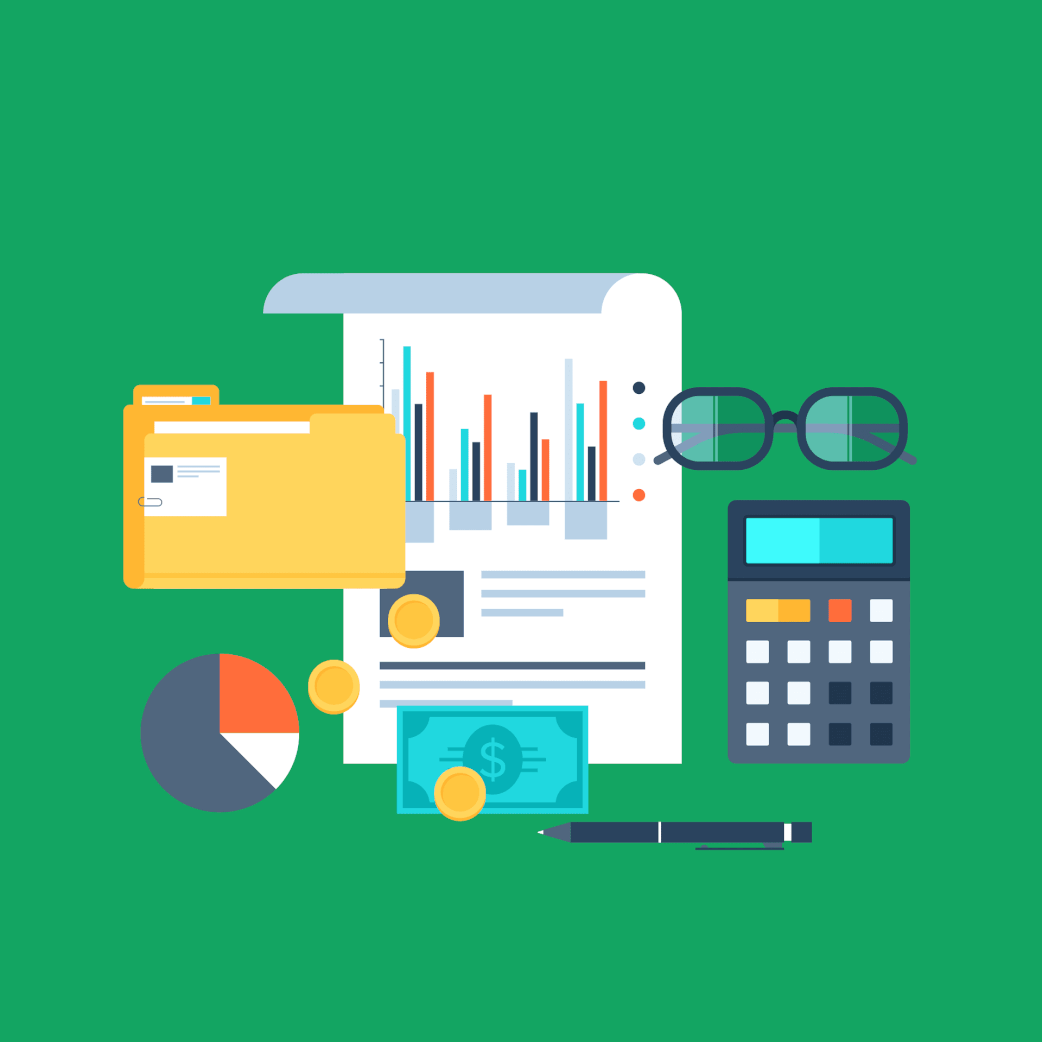
消えた「魔法の言葉」の正体
2020年前後、日本中の観光地で「ワーケーション」という言葉が飛び交っていた。リゾート地でノートパソコンを開き、海を眺めながら優雅に仕事をする──そんな夢のような働き方が、新しい観光のスタイルとして喧伝されていたのだ。自治体は競うように補助金制度を創設し、観光協会はワーケーション誘致のための豪華なパンフレットを作成した。ホテルや旅館は「ワーケーションプラン」を次々と打ち出し、まるでそれが観光業界の救世主であるかのように扱われた。
しかし、2025年の現在、その言葉はどこへ行ってしまったのだろうか。多くの自治体のウェブサイトから「ワーケーション」の文字は静かに消え、あれほど力を入れていた専用施設は閑散としている。一体、あの熱狂は何だったのか。そして、投じられた莫大な税金はどこへ消えたのか。
この問いは、ワーケーションという一つの事象を超えて、日本の観光施策が抱える根本的な問題を浮き彫りにする。表面的な流行を追い、効果検証を怠り、税金を湯水のように使う──そんな構造的な欠陥が、観光行政の至るところに見え隠れしているのである。
ワーケーションという幻想─なぜ定着しなかったのか
ワーケーションとは「ワーク(Work)」と「バケーション(Vacation)」を組み合わせた造語である。休暇を楽しみながら仕事もする、あるいは地方に滞在しながらリモートワークをするという働き方を指す。コロナ禍によってリモートワークが急速に普及したことで、この概念が一気に注目を浴びたのは記憶に新しい。
当時、観光庁や各自治体は「これからの観光の柱」としてワーケーションを位置づけた。観光需要の平準化、地方創生、交流人口の創出──あらゆる社会課題を解決する万能薬のように語られた。しかし、実態はどうだったか。
まず、根本的な問題として、ワーケーションを実践できる人々は極めて限られていた。フルリモートワークが可能で、時間と場所の制約が少なく、なおかつ滞在費用を負担できる経済的余裕のある層。この条件を満たす人は、日本の労働人口のごく一部に過ぎない。多くのビジネスパーソンは、依然としてオフィスへの出勤を求められ、対面でのミーティングに縛られ、上司の目を気にしながら働いている。
さらに、ワーケーションを実践した人々の多くが直面したのは「仕事と休暇の境界線の曖昧さ」という問題である。リゾート地で仕事をすることは、一見すると魅力的に映る。しかし実際には、仕事に集中できない環境、不安定なインターネット接続、家族や同行者への気兼ね、そして何より「休暇なのか仕事なのかわからない」という精神的な居心地の悪さが付きまとう。結局、多くの人にとって、仕事は仕事場で、休暇は休暇として分けた方が効率的であり、精神衛生上も健全だという結論に至ったのである。
税金で作られた「ワーケーション施設」の末路
ワーケーションブームの最盛期、全国各地で専用施設の整備が進められた。古民家を改装したコワーキングスペース、高速Wi-Fiを完備したリゾートホテルの専用フロア、自然に囲まれたワーケーション専用施設──その多くが、国や自治体の補助金、つまり税金によって建設・改修されたものである。
ある地方都市では、最新のオフィス機器、高速通信環境、カフェスペース、さらには宿泊施設まで備えた豪華な施設を整えた。しかし、オープンから2年が経過した現在、その施設の稼働率は10%にも満たない。広報に使われた美しいパンフレットは今も配布されているが、実際に足を運ぶ人はほとんどいない。維持費だけが毎年発生し続けている。
別の観光地では、温泉街の旅館組合が共同でワーケーションプランを開発した。自治体から補助金を得て、各旅館にワークスペースを整備し、長期滞在者向けの割引プランを用意した。初年度こそ、物珍しさから一定の利用があったものの、2年目以降は激減。結局、多くの旅館が「通常の宿泊客の方が収益性が高い」という当たり前の結論に達し、ワークスペースは物置と化している。
これらの事例に共通するのは、需要の見極めの甘さである。「リモートワークが普及している」「新しい働き方が注目されている」という表面的なトレンドだけを見て、実際にどれだけの人が、どのような条件で、どれくらいの頻度で利用するのかという具体的な検証を怠った結果である。マーケティングの基本である「誰に、何を、どう売るか」という視点が完全に欠落していた。
「やって終わり」の観光施策─PDCAサイクルという概念の不在
ワーケーション施策の失敗は、日本の観光行政が抱える構造的な問題の象徴である。最も深刻なのは、事業の効果検証がほとんど行われないという事実だ。
民間企業であれば、投資に対するリターンを厳しく問われる。新規事業を立ち上げれば、売上、利益率、顧客獲得コスト、リピート率など、あらゆる指標が精査される。目標に達しなければ、原因を分析し、改善策を講じる。それでも成果が出なければ、事業の縮小や撤退を決断する。これがPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)の基本である。
しかし、多くの観光施策においては、このサイクルが機能していない。予算が付き、事業が実施され、報告書が提出される──そこで完結してしまうのだ。報告書には「○○名が参加した」「アンケートで高評価を得た」といった表面的な数字が並ぶが、本質的な効果検証はなされない。
たとえば、ある自治体が年間2000万円の予算を投じてワーケーション誘致キャンペーンを実施したとする。その結果、100人のワーケーション利用者を呼び込んだとしよう。一人あたりの誘致コストは20万円である。これは果たして適切な投資なのか。その100人が地域にもたらした経済効果はいくらなのか。彼らは再訪したのか。地域の事業者にとって実質的なメリットはあったのか。こうした問いに答えられる自治体はほとんどない。
さらに問題なのは、失敗が失敗として認識されないことである。民間企業であれば、成果の出ない事業は責任問題となる。しかし行政の世界では「予算を執行した」という事実が重要であり、その結果がどうであったかは二の次になりがちだ。担当者は数年で異動し、事業の継続性や責任の所在が曖昧になる。こうして、同じような失敗が形を変えて繰り返されるのである。
世間の経済感覚とずれた観光施策の実態
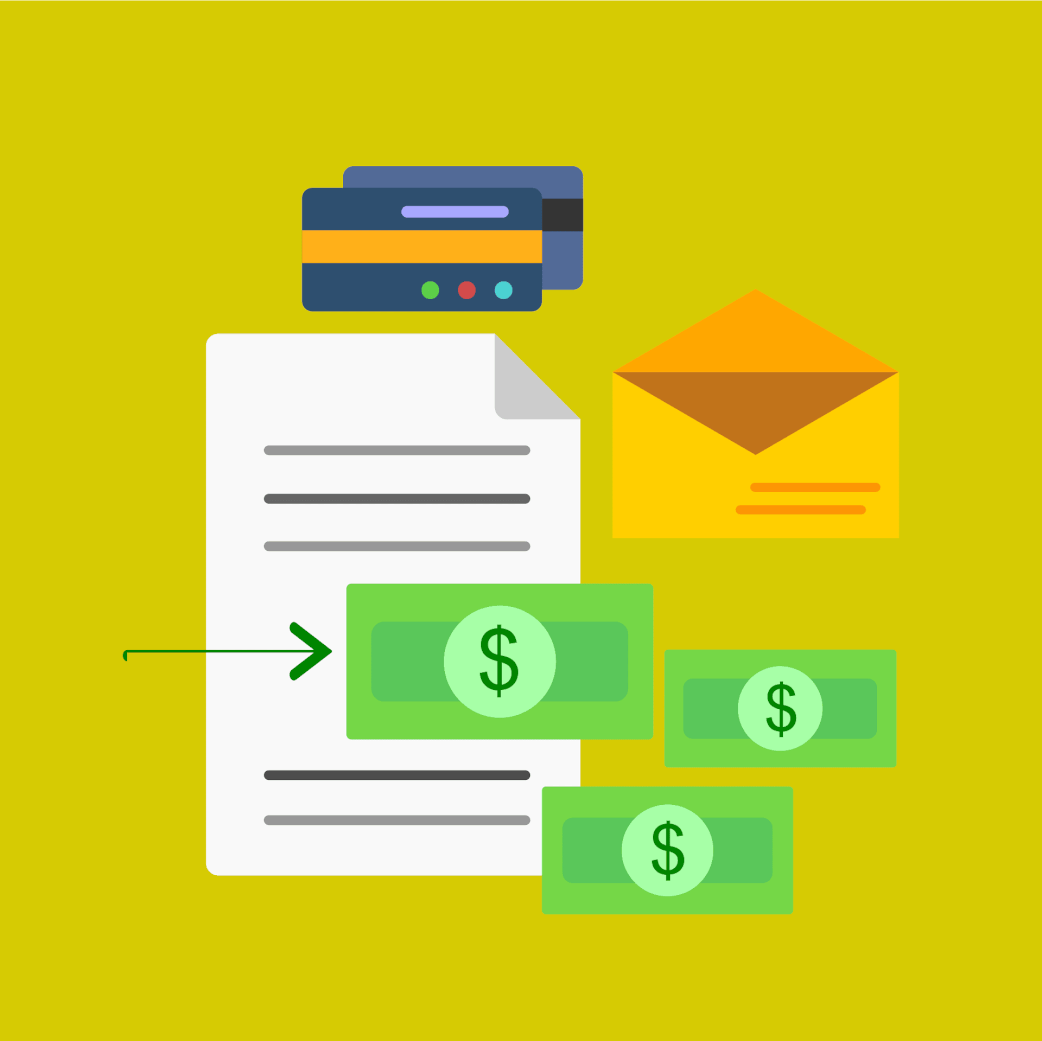
日本経済は長期にわたる低成長に苦しんでいる。実質賃金は伸び悩み、多くの家庭が生活費の上昇に直面している。若者は奨学金返済に追われ、中高年は老後資金に不安を抱える。一般市民は日々の支出に敏感になり、少しでも安い商品を求めてスーパーを渡り歩く。
こうした厳しい経済環境の中でも、観光関連の公的支出は大盤振る舞いである。「観光立国」という大義名分のもと、莫大な予算が投じられるが、その使途は必ずしも国民の利益に直結していない。
典型的なのが、海外への観光プロモーション事業である。各自治体は海外の観光博覧会に出展し、現地でのPRイベントを開催し、インフルエンサーを招聘する。一度の海外プロモーション経費として数百万円が使われることも珍しくない。しかし、その成果は極めて測定しづらい。「認知度が向上した」「興味を持つ人が増えた」といった曖昧な評価に終始し、実際にどれだけの観光客増加につながったのか、費用対効果はどうだったのかという具体的な検証は行われない。
また、豪華なパンフレットやプロモーション動画の制作にも巨額の予算が投じられる。デザイン会社に発注すれば、A4判のパンフレット1種類で数百万円、動画なら数千万円という見積もりが当たり前のように提示される。これらのコンテンツは確かに美しい。しかし、本当にそれだけの投資価値があるのだろうか。同じ予算があれば、地域の観光事業者への直接支援や、実質的なインフラ改善にもっと有効に使えるのではないか。
こうした支出の背景には、「税金だから」という意識の希薄さがある。自分の財布から出るお金であれば、誰もがシビアに費用対効果を吟味する。しかし、公的予算となると、その緊張感が失われがちだ。「予算を使い切らなければ来年度の予算が減らされる」という行政特有のインセンティブ構造も、無駄な支出を助長する。
1
2