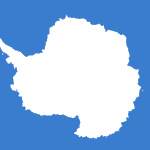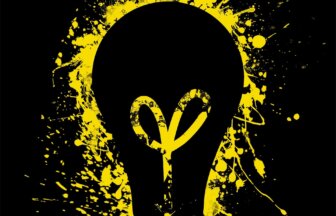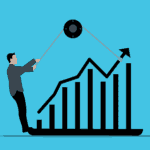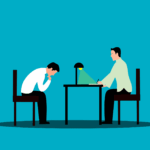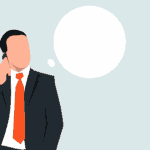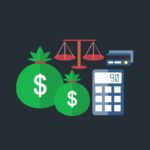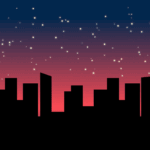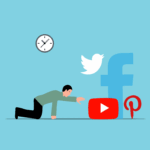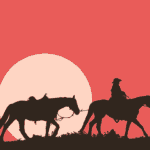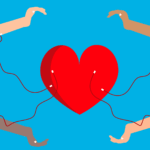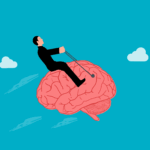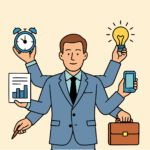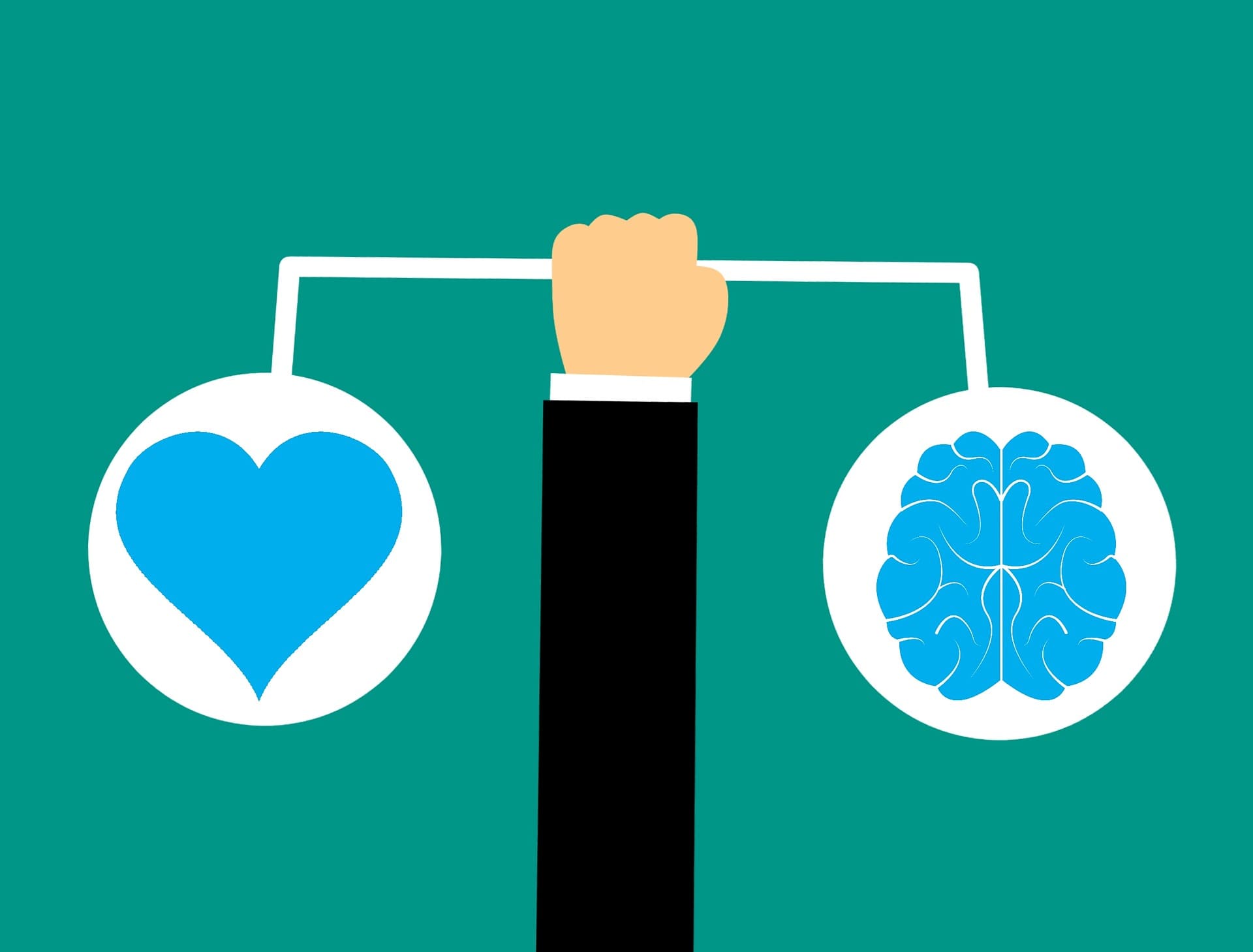
あなたも感じたことがある「なんとなく」の正体
「なんとなく嫌な予感がする」「この人、信用できそう」「今日は何かいいことがありそう」こんな漠然とした感覚を抱いたことは誰にでもあるだろう。これこそが、いわゆる「第六感」と呼ばれる不思議な感覚の正体である。
人間には視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚という5つの基本的な感覚があることは誰もが知っている。しかし、これら5つの感覚だけでは説明できない「何か」を私たちは日常的に感じ取っている。それが第六感だ。
これは決してオカルトや超能力の話ではない。実は、現代の脳科学や心理学の研究によって、その正体が少しずつ明らかになってきているのである。私たちの脳は、意識的には気づかないレベルで膨大な情報を処理し続けている。その結果として生まれる「直感」や「勘」こそが正体なのだ。
第六感が生まれるメカニズムとは|脳の驚くべき情報処理能力
私たちの脳は、まさに超高性能なコンピューターのような働きをしている。毎秒1100万ビットもの情報を処理していると言われているが、そのうち意識的に認識できるのはわずか40ビット程度に過ぎない。残りの99.9%以上の情報は、無意識のうちに処理されているのである。
この無意識の情報処理こそが、第六感の源泉だ。例えば、初対面の人に会った時の「この人は信頼できそう」という感覚は、相手の表情、声のトーン、姿勢、視線の動き、呼吸のリズムなど、無数の微細な情報を脳が瞬時に分析した結果として生まれる。意識的にはそれらの情報を認識していないが、脳は確実にキャッチして総合的な判断を下しているのだ。
そしてこの無意識の情報処理能力は、過去の経験や学習によって磨かれていくという点である。例えば、長年商売をしている人が「このお客さんは買わないな」と瞬時に判断できるのは、過去の膨大な経験から得られたパターン認識能力が働いているからだ。これも立派な第六感の一種である。
科学的な解明|ミラーニューロンの発見
この感覚の正体を科学的に解明する上で、重要な発見の一つが「ミラーニューロン」である。1990年代にイタリアの研究者によって発見されたこの神経細胞は、他者の行動を見ただけで、まるで自分がその行動をしているかのように反応する特殊な性質を持っている。
ミラーニューロンの働きによって、私たちは他人の感情や意図を直感的に理解することができる。相手が悲しんでいる時に自分も悲しくなったり、誰かがあくびをしているのを見て自分もあくびが出そうになったりするのも、このミラーニューロンの働きによるものだ。
これが第六感とどう関係するのかというと、ミラーニューロンによって私たちは相手の微細な変化を無意識に感じ取り、「なんとなく機嫌が悪そう」「何か隠しているような気がする」といった直感を得ることができるのである。まさに、人の心を読む能力の科学的基盤と言えるだろう。
「気」を感じる感覚|人間の電磁場感知能力
第六感の中でも特に神秘的に感じられるのが、「気」や「オーラ」と呼ばれる感覚である。「あの人からは良い気が出ている」「なんとなく嫌な気配を感じる」といった表現は、多くの人が実際に体験したことがあるだろう。
実は、これにも科学的な根拠がある。人間の体は微弱な電磁場を発生させており、心拍や脳波、筋肉の動きなどによってその強度や周波数が変化している。そして、人間には微弱な電磁場を感知する能力があることが近年の研究で明らかになってきている。
特に人間の心臓が発生させる電磁場は、体から約3メートルの範囲まで届くということだ。つまり、私たちは文字通り他人のハートビートを感じ取っている可能性があるのである。感情的に興奮している人や、逆に深く落ち込んでいる人の近くにいると何となく影響を受けてしまうのは、こうした電磁場の相互作用が関係しているかもしれない。
予知能力の正体|パターン認識の極み

不思議に感じられるのが、未来を予知するような感覚である。「何となく今日は事故に気をつけた方がいい気がする」と思った日に実際に危険な目に遭いそうになったり、「あの人から連絡が来そう」と思った矢先に本当に連絡が来たりする経験は、多くの人が持っているだろう。
これらの現象の多くは、実は高度なパターン認識能力によって説明することができる。私たちの脳は、日常的に膨大な情報を蓄積し、そこから未来を予測するためのパターンを抽出している。例えば、天気の微細な変化、交通量の変化、周囲の人々の行動パターンなど、意識的には気づかないレベルの情報から、脳は「今日は何か起こりそう」という予測を立てているのだ。
また、確率的に考えても、私たちは日常的に数多くの予感や直感を抱いている。その中のいくつかが偶然的中することは十分にあり得ることであり、当たった時だけが強く印象に残るため、予知能力があるように感じられるのである。
1
2