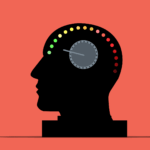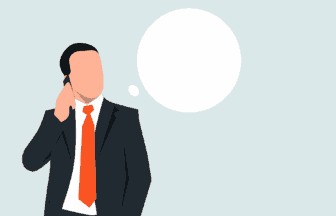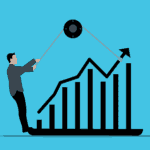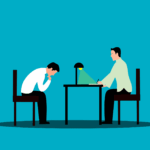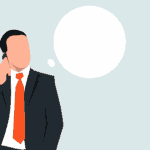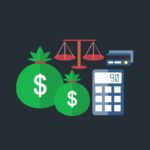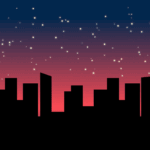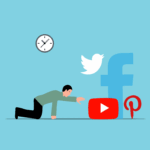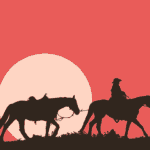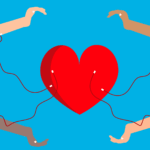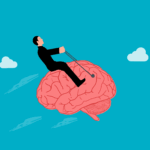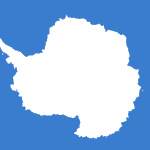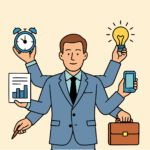他者を見下し、優越感に浸る人間が増加傾向にあると感じることはないだろうか。SNS上で些細なミスを徹底的に批判する人、会議で他者の意見を一蹴する上司など、様々な場面で「他人を見下す人」は日常的に存在している。
このコラムでは、なぜ人は他者を見下すのか、その心理的メカニズムを深掘りするとともに、近年増加している社会的背景を考察する。さらに、見下してくる人間に対して効果的に対処し、精神的優位性を保ちながら相手を黙らせる実践的な方法論を紹介する。
見下してくる人間との遭遇は不快な体験だが、適切な対応策を身につければ、むしろ自分自身の成長機会に変えることも可能である。この記事を読み終える頃には、あなたは見下してくる人間に振り回されることなく、毅然とした態度で対応できるようになるだろう。
なぜ人は他者を見下すのか
自身の不安と自己価値の揺らぎ
人が他者を見下す行動の根底には、多くの場合、自分自身に対する不安や自己価値の揺らぎが存在している。他者を批判し、見下すことで、相対的に自分の立場を高く位置づけようとする心理が働いているのである。
この現象は心理学では「下方比較」と呼ばれ、自分より劣っていると認識できる対象と比較することで自尊心を保とうとする防衛機制の一つである。つまり、見下してくる人間は、実は内面的な脆さを抱えており、それを補償するために他者の価値を下げようとしているのだ。
「他人を見下す人間ほど、実は自分に自信がない」というのは、心理学的にも裏付けられた事実なのである。
優越感という麻薬
他者を見下し、批判することで得られる優越感は、一種の快感をもたらす。この感覚は脳内で報酬系が活性化し、ドーパミンが分泌されることで生じる。つまり、見下し行為は一種の「気分の良くなる行為」として習慣化しやすい傾向がある。
特に日常生活で挫折や失敗を経験している人にとって、この「優越感」は手軽に得られる精神的報酬となる。職場で評価されない人が、家庭やSNSで他者を批判し、小さな優越感を味わうというパターンは珍しくない。
共感能力の欠如
見下し行為を頻繁に行う人には、共感能力の欠如が見られることが多い。相手の立場や感情を想像する能力が低く、自分の基準や価値観を絶対視する傾向がある。このような思考パターンは「認知的硬直性」と呼ばれ、柔軟な思考や多様な価値観の受容を困難にしている。
共感能力の高い人は、たとえ相手に問題があると感じても、批判よりも理解を優先する傾向にある。反対に、共感能力の低い人は、相手の行動や発言を即座に自分の価値基準で判断し、否定的な評価を下しやすい。
現代社会における「見下し行為」の増加要因
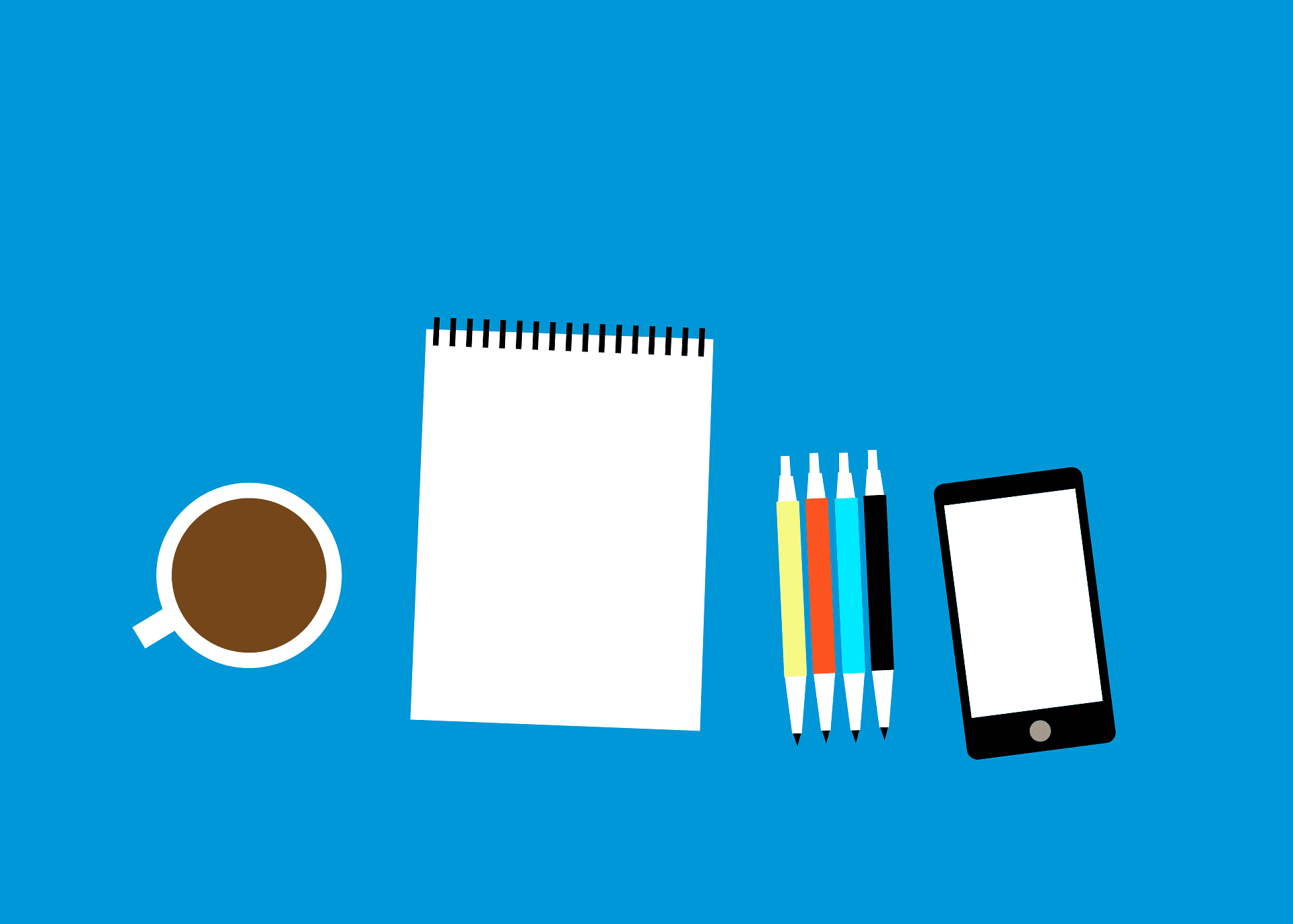
SNSがもたらす匿名性と拡散力
ネットやSNSの普及により、匿名または半匿名で他者を批判できる場が増加した。対面では言えないような厳しい批判も、スクリーンを通せば容易に発信できるようになり、また「いいね」や「シェア」などのフィードバックによって、批判的な発言が強化されやすい環境が整っている。
特に匿名性の高いプラットフォームでは、自分の発言に対する社会的責任を感じにくく、抑制が効きにくいため、より過激な表現や見下しが生じやすい。こうした環境が「見下し文化」を助長しているのである。
情報過多と二項対立の思考様式
現代は膨大な情報が流通する時代である。こうした情報過多の状況下では、複雑な現実を単純化して理解しようとする心理が働き、「正しい・間違っている」「善・悪」といった二項対立的な思考に陥りやすい。
このような思考様式は、グレーゾーンや多様性を認める余地を狭め、自分と異なる意見や行動を即座に「間違っている」と判断する傾向を強める。結果として、他者を見下す行為が正当化されやすくなるのである。
社会的分断と不安の増大
経済格差の拡大や将来への不安感が高まる中で、人々は自分の立場や価値観を守ろうとする防衛機制が強くなっている。自分と異なる集団や価値観を持つ人々を批判し、見下すことで、自分の所属集団の正当性を確認し、安心感を得ようとする心理が働いている。
こうした社会的分断は、「内集団びいき」と呼ばれる現象を強め、自分と異なる集団への寛容さを失わせる原因となっている。その結果、以前なら許容できたような些細な違いも、批判や見下しの対象になりやすくなっているのだ。
見下してくる人間を黙らせる実践的方法論
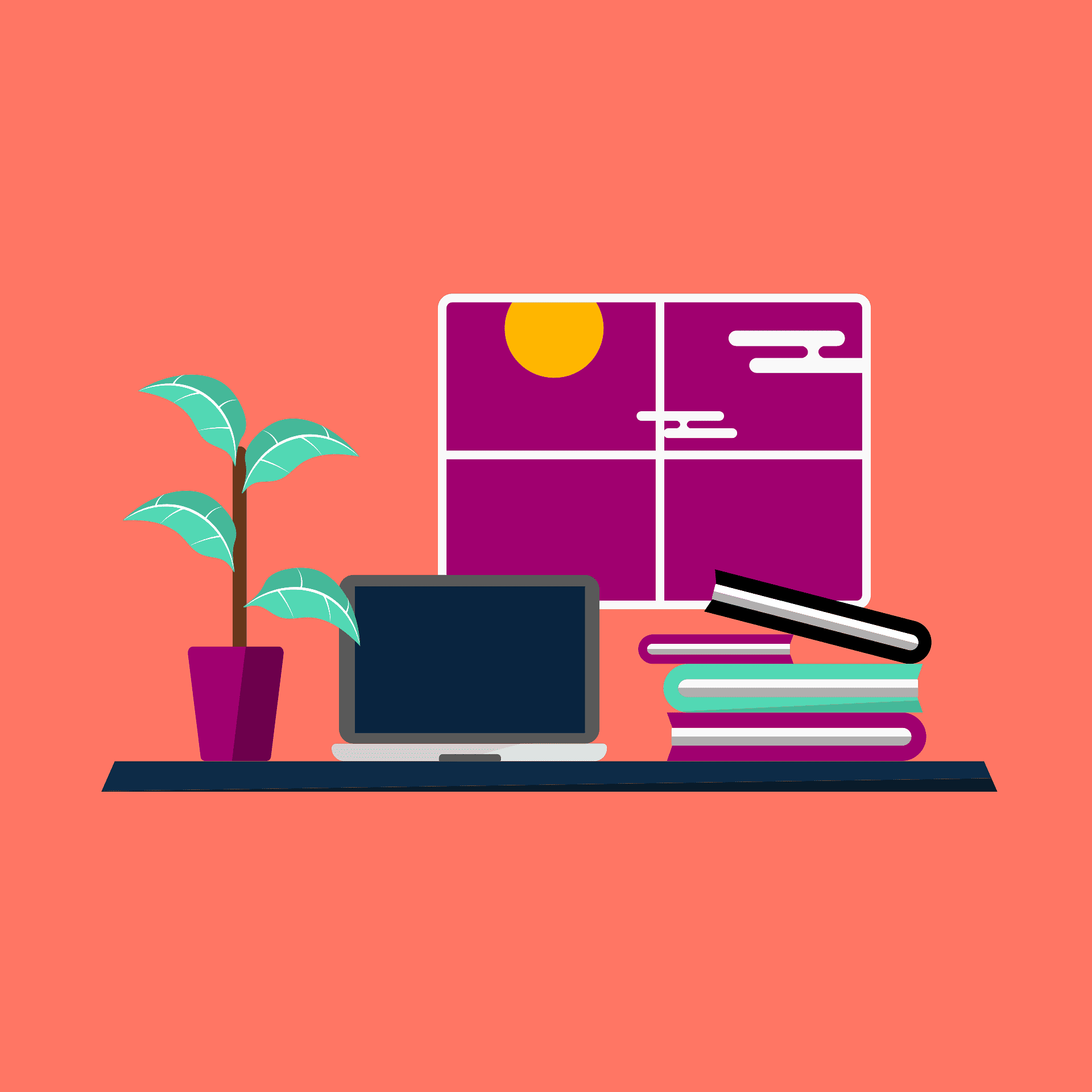
自己認識と感情コントロール|平静を保つこと
見下してくる人間に対応する最初のステップは、自分自身の感情をコントロールすることである。相手の言動に感情的に反応すると、冷静な判断力を失い、効果的な対応ができなくなる。
まず、深呼吸をして心を落ち着かせる。次に、「この人の言動は彼・彼女自身の問題であり、自分の価値を下げるものじゃない」と自分に言い聞かせる。この内的対話によって、感情的になることを防ぎ、冷静な対応が可能になる。
感情をコントロールできた状態で初めて、相手に対する効果的な反応が可能になるのだ。
1
2