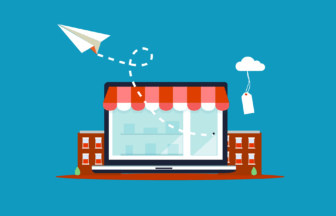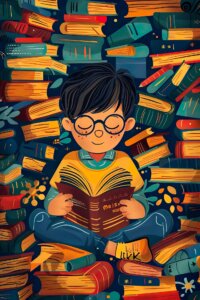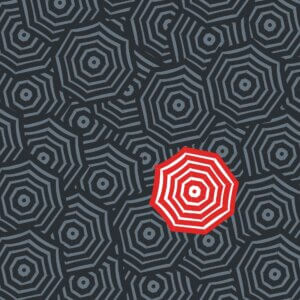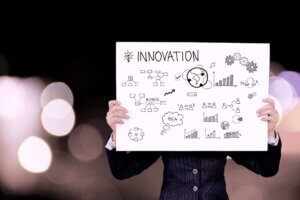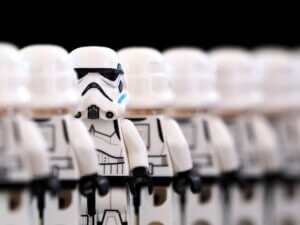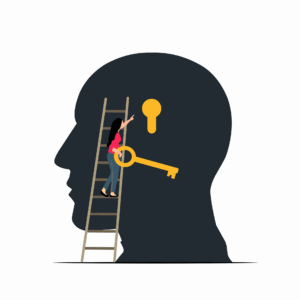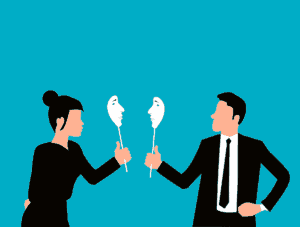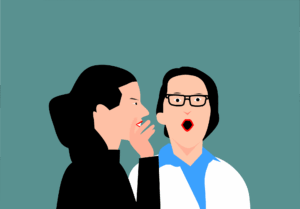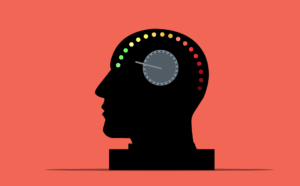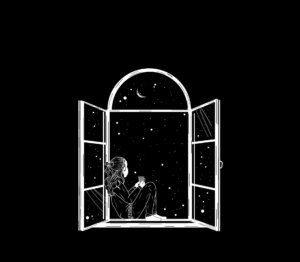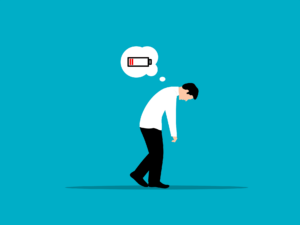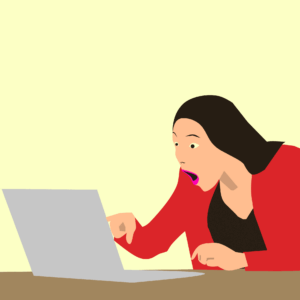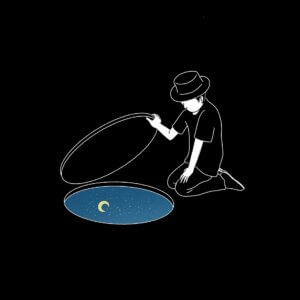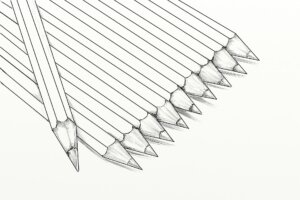新潟県出雲崎町にある出雲崎レトロミュージアムが、2025年2月3日での閉館を決定しました。わずか1年での閉館という決定の背景には、親による理不尽な言動が大きく影響していると言われています。この問題は、現代の深刻な「自己中心的社会」を浮き彫りにしています。
出雲崎レトロミュージアムとは
出雲崎レトロミュージアムは、昭和時代の懐かしい品々が展示され、直接触れて遊べる私設博物館として、地域の人々に愛されていた施設でした。館長が長年かけて収集した昭和時代の生活用品や玩具、教科書など、約1万点もの貴重な展示品を所蔵していました。館内では、展示品に触れることができ、子供たちが昔の遊び方を体験できる機会も提供されていました。
館長は、展示品の維持管理や修復を全て自己負担で行い、来館者への丁寧な解説も欠かさず行ってきました。地域の子供たちの社会科見学の場としても活用され、教育的な価値も高く評価されていました。
閉館に至った理由と親の理不尽な要求
報道によると、子供が展示されていたおもちゃで遊んでいた際、不適切な使い方をしたため、館長が優しく注意をしました。しかし、その親は「だったらそんなところに置いとくんじゃねえよ」などと一方的で傲慢な態度で主張し、館長を執拗に非難したのです。
この出来事は、館長に大きな精神的ダメージを与えました。子供がものを壊すのは仕方ないとしても、長い年月をかけて収集し、大切に保管してきた展示品に対する親という立場での理解のなさ、そして一方的な非難に耐えかね、やむなく閉館を決意するに至ったのです。
現代の深刻な「自己中心的社会」
今回の一件は、現代社会が抱える深刻な問題を如実に表しています。「自己中心的」な人間が巷にはますます溢れかえっているような気がしてなりません。他人を敬ったり、物を大切にする気持ちなど、もはや一昔前の美談。
物を大切にする心の欠如、展示品は単なる「古いもの」ではありません。それぞれが昭和の時代を生きた人々の思い出や歴史を伝える貴重な証です。そこを含めて子供への教育としなければいけないところであり、そういった価値観の真逆をいく親の態度は、私たちの文化や歴史を継承していく上で大きな障害となります。
他者への思いやりの欠如、館長は長年、趣味とはいえ個人の時間と資金を投じて、地域の文化発信に貢献してきました。その善意の活動に対して、理不尽な非難を浴びせる行為は、ボランティア精神や社会貢献の意欲を著しく損なわせるものです。
さらに深刻なのは、子供を盾にした身勝手な言動です。子供の自由な発想や行動を育み、尊重することは大切ですが、それは他者や物を大切にする心と両立させるべきものです。むしろ、親の理不尽な言動は、子供に誤った価値観を植え付けることにつながりかねません。
私たちが失ってはいけないもの
出雲崎レトロミュージアムの閉館と、親の嘆かわしい言動は、昔から社会が大切にしてきた価値観の危機を象徴する出来事なのです。
歴史を継承し、文化を守り、次世代に伝えていく。そのために無償の善意で尽力する人々がいる。そうした当たり前の営みが、一部の自己中心的な言動によって脅かされている現状に、私たちは真摯に向き合う必要があります。
物を大切にする心、他者への思いやり、世代を超えて継承される知恵や経験の価値。これらは、豊かな社会を築く上で欠かせない要素です。しかし、今回の事例は、これらの価値観が軽視される危険性を警告しているのです。
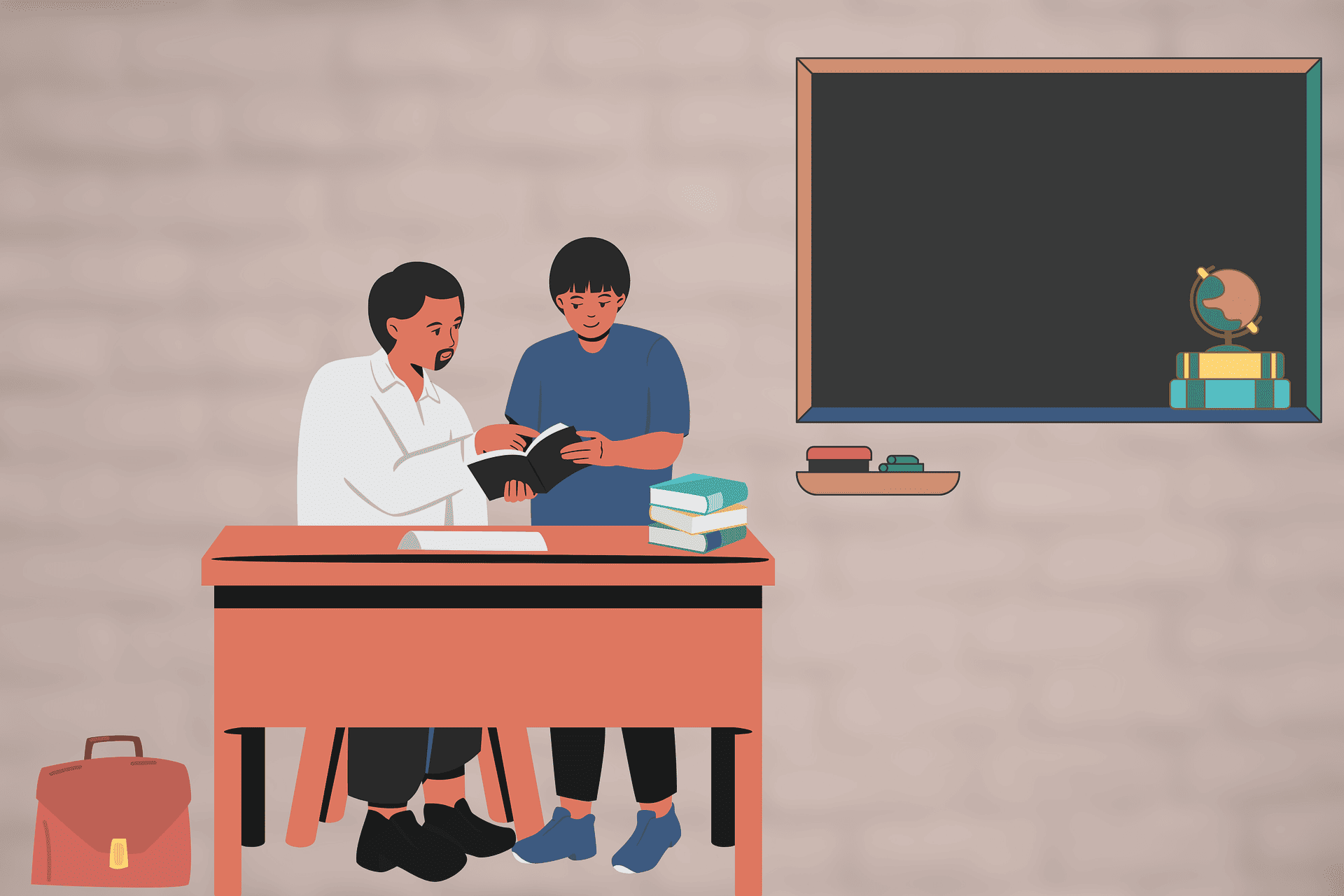
今、私たちにできること
出雲崎レトロミュージアムの閉館は決定的となりましたが、この出来事から学ぶべきことは多くあります。
まず、私たち一人一人が、文化や歴史を守る活動の意義を再認識する必要があります。地域の歴史や文化を伝える施設やその活動に関わる人々の存在意義を、改めて考え直すきっかけとすべきでしょう。
また、子供たちに対する教育のあり方も見直す必要があります。物を大切にする心、他者への思いやり、歴史や文化の価値を理解する力。これらを育むためには、家庭での教育が極めて重要です。
そして何より、善意の活動を行う人々を守り、支える社会の仕組みづくりが必要です。一部の理不尽な言動によって、貴重な文化的資産や活動が失われることのないよう、地域社会全体で支援する体制を整えることが求められます。
おわりに
出雲崎レトロミュージアムの閉館は、今の日本に大きな警鐘を鳴らしているような気がします。物質的な豊かさと引き換えに、私たちは大切なものを失いつつあるのではないでしょうか。
この出来事を、単なる一施設の閉館として終わらせてはいけません。私たち一人一人が、自分の言動を振り返り、次世代に何を伝え、どんな社会を築いていくべきか、真剣に考える契機としなければなりません。
館長の長年にわたる献身的な活動に心からの敬意を表すとともに、このような形で幕を閉じることになったことに、深い憤りと悲しみを感じずにはいられません。私たちは、この教訓を決して忘れることなく、より良い社会の実現に向けて歩みを進めていかなければならないのです。