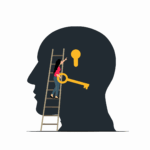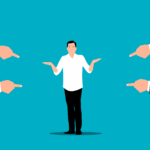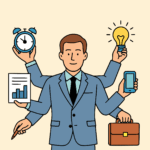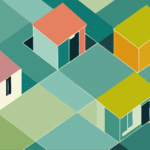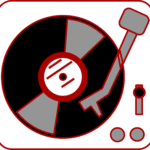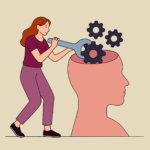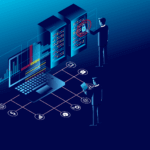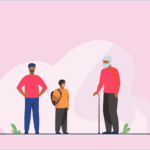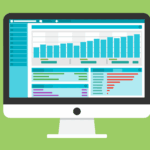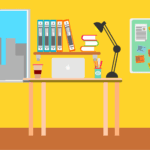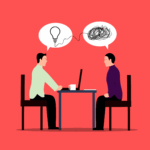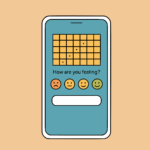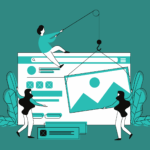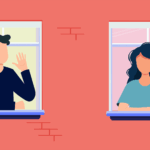高度経済成長期「働くことの意味」からわかることとは
日本の高度経済成長期、1955年から1973年にかけての約20年間は、日本経済が驚異的な成長を遂げた時代である。この時期の日本人の働き方は、現代の我々から見れば信じがたいほどの激しさと献身、そして独特の労働文化を持っていた。テレビドラマでは2024年に、端島(軍艦島)に暮らす人たちの激動の物語「海に眠るダイヤモンド」に描かれている「炭鉱に携わる人たちの姿」にも通ずるところがあるだろう。今回の記事では、この時代の勤労者たちの姿を、逸話や興味深いエピソード、そして彼らの思いなども交えながら伝え、現代を生きる私たちに仕事とはどうあるべきかを考えるきっかけとなれば幸いである。
「モーレツ社員」の誕生
高度経済成長期の象徴的存在として、「モーレツ社員」という言葉がある。これは、仕事に命を懸ける熱狂的な社員を指す言葉だ。彼らは早朝から深夜まで働き、休日返上で仕事に打ち込んだ。
「朝7時に出社し、夜11時まで働くのが当たり前でした。土日も休まず会社に来ていましたね。家族と過ごす時間なんてほとんどありませんでした。でも、不思議と苦しいとは思わなかった。日本の発展のために頑張っているんだという誇りがあったんです。」
この「モーレツ社員」たちの存在が、日本の急速な経済成長を支えたと言っても過言ではないだろう。彼らの献身的な働きぶりは、海外からも驚きの目で見られていた。アメリカのビジネス誌は、「日本人は働きすぎる。彼らは人間というより機械だ」と評したほどである。
事業所数の推移(昭和47年〜平成13年資料)
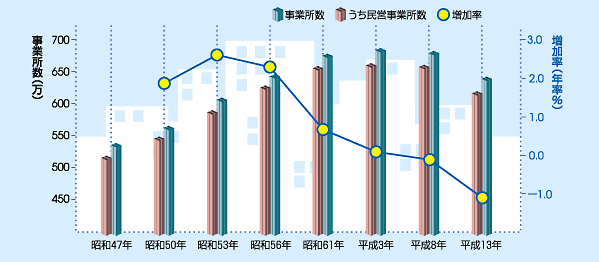
従業員数の推移(昭和47年〜平成13年資料)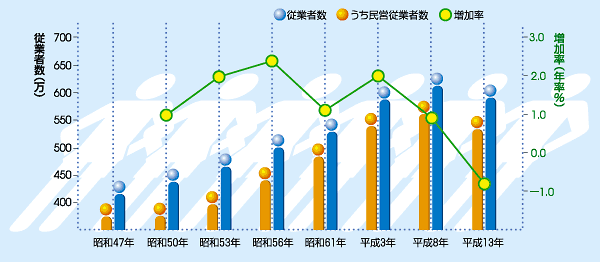
出典:総務省統計局ホームページ
「社畜」文化の始まり
高度経済成長期に形成された労働文化は、後に「社畜」という言葉を生み出すことになる。「社畜」とは、会社に飼い慣らされた家畜のように働く社員を指す蔑称だ。この言葉自体は1990年代に生まれたものだが、その源流は高度経済成長期にあると言える。
当時の多くの企業では、従業員の私生活よりも会社への忠誠心が重視された。「結婚式の日でさえ、上司から『午前中だけでも出社してくれ』と言われたものです。断れば出世に響くかもしれない。そんな空気がありました。」
この「会社第一」の姿勢は、日本的経営の特徴とされる終身雇用制度と密接に結びついていた。従業員は会社に一生涯面倒を見てもらえるという安心感と引き換えに、私生活を犠牲にしてでも会社に尽くすことを求められたのかもしれない。
「サービス残業」の常態化
高度経済成長期に定着し、後の日本の労働問題の根源となった慣行の一つが「サービス残業」である。これは、残業代が払われないままに働くことを指す。
「残業代なんて請求したことありませんでした。みんな当たり前のように残業していましたからね。『残業代をください』なんて言ったら、仕事に熱心でないと思われそうで…。」
この「サービス残業」の慣行は、企業にとっては人件費の抑制につながり、経済成長を後押しした一因とも言える。しかし、労働者の権利という観点からは大きな問題をはらんでいた。にもかかわらず、多くの労働者がこれを受け入れていたのは、前述の「モーレツ社員」精神や「社畜」文化と無縁ではないだろう。
「過労死」という悲劇
高度経済成長期の過酷な労働環境は、後に「過労死」という深刻な社会問題を生み出すことになる。過労死という言葉自体は1970年代後半に生まれたものだが、その土壌は高度経済成長期に形成されたと言える。
1969年、30代の社員が過労が原因で突然死した事件は、日本社会に大きな衝撃を与えた。彼は1ヶ月に159時間もの残業をこなしていたという。この事件は、経済成長の裏で進行していた労働者の健康被害を浮き彫りにした。
労働問題に詳しいあるジャーナリストは次のように分析する。「高度経済成長期の『頑張れば報われる』という神話が、多くの人々を過酷な労働に駆り立てたのです。しかし、その代償は余りにも大きかった。過労死は、経済成長の影の部分を象徴する現象だと言えるでしょう。」
「企業戦士」たちの誇りと葛藤
高度経済成長期の労働者たちは、しばしば「企業戦士」と呼ばれた。彼らは文字通り、企業のために戦う戦士のような存在だったのである。
「確かに今から思えば、あの働き方は異常だったかもしれません。でも、日本の未来のために頑張っているんだという自負がありました。海外出張で外国人に『日本製品は素晴らしい』と言われるような場面もあり、本当に嬉しかったですね。」
一方で、家庭を顧みる時間のなさに悩む者も多かった。「夫は子どもの顔を見るのは週末だけ。それも寝ている姿を見るだけでした。子どもたちは『お父さんは会社に住んでいるの?』と聞いてきたものです。」
このように、「企業戦士」たちは仕事への誇りと家庭への罪悪感の間で葛藤していた。彼らの多くは、日本の発展のために自己を犠牲にすることを美徳と考えていたのかもしれない。
「出世競争」の熾烈さ
高度経済成長期の企業では、激しい出世競争が繰り広げられていた。この競争が、さらなる長時間労働を助長したと言える。
「同期入社の仲間たちと、誰が一番遅くまで残っているかを競っていましたね。早く帰るということは、仕事への熱意が足りないと思われかねない。だから皆、必死で残業していました。」
この出世競争は、時に非人間的な状況を生み出すこともあった。ある商社では、社員の勤務時間を可視化するために、各自の机の上に「退社時間表示板」を置くことを義務付けていたという。これにより、誰がどれだけ遅くまで働いているかが一目でわかるようになった。
ある労働社会学者は、この現象を分析する。「高度経済成長期の日本企業では、長時間労働が出世の条件の一つとなっていました。これは生産性の向上には必ずしもつながらず、むしろ非効率な労働を助長した面があります。しかし、当時の日本人にとっては、これが『当たり前』の光景だったのです。」

「社宅」文化と会社への帰属意識
高度経済成長期には、多くの企業が「社宅」を提供していた。これは単なる福利厚生ではなく、従業員の会社への帰属意識を高める役割も果たしていた。
「社宅では、隣近所全員が同じ会社の人間でした。休日に家族ぐるみの付き合いをしたり、子どもたちも一緒に遊んだり。会社の話で盛り上がることも多かったですね。会社が生活の全てと言っても過言ではありませんでした。」
この「社宅」文化は、従業員の私生活と仕事の境界をさらに曖昧にした。会社の同僚が隣人であり、子どもの遊び友達の親でもあるという環境は、否が応でも会社への帰属意識を高めることになった。
労働問題に詳しいあるジャーナリストはこう指摘する。「社宅制度は、従業員を会社に縛り付ける『黄金の手錠』の役割を果たしていました。会社を辞めることは、住む場所を失うことにもつながる。そのため、多少の不満があっても会社に留まる従業員が多かったのです。」
「根性論」と「精神主義」の蔓延
高度経済成長期の日本の職場では、「根性論」や「精神主義」が蔓延していた。これは、困難な状況でも精神力で乗り越えるべきだという考え方だ。
「上司からよく『根性が足りない』『精神力だ』と言われました。体調不良で休もうものなら、『甘えるな』と叱責される。そういう雰囲気が当たり前でした。」
この「根性論」は、時として非人間的な労働環境を正当化する口実にもなった。とある工場では、真夏の炎天下での作業中に熱中症で倒れる労働者が続出しても、「根性で乗り切れ」と作業を続行させたという。
『根性論』や『精神主義』は、個人の努力で全てが解決できるという幻想を生み出した。しかし、これは労働環境の改善や労働者の権利向上を妨げる要因にもなり得る。過酷な労働条件を個人の努力で乗り越えるべきだという風潮が、労働問題の解決を遅らせたと言えるのかもしれない。
「社員旅行」と「運動会」の盛況
高度経済成長期の特徴的な企業文化として、「社員旅行」や「運動会」の盛況が挙げられる。これらのイベントは、従業員の士気を高め、チームワークを強化する目的で盛んに行われていた。
1
2