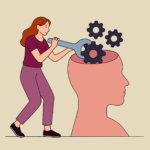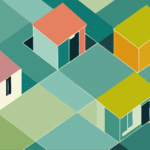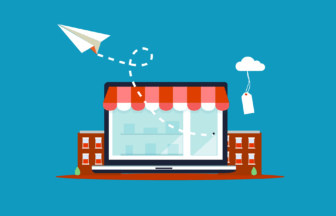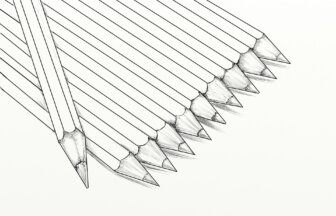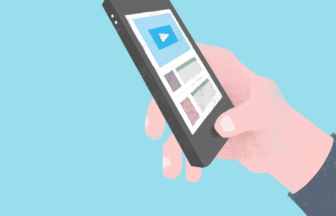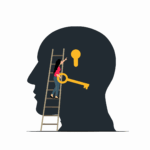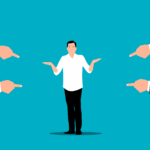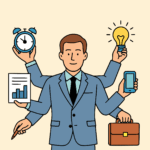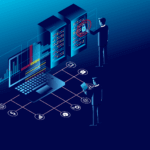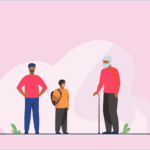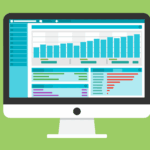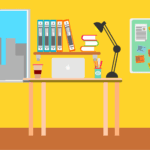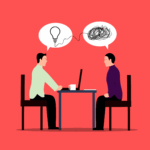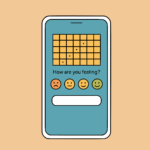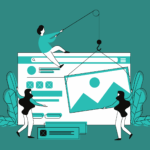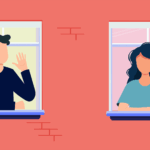楽器のチューニングのわずかなズレが許せない
音楽を演奏する際、楽器のチューニング(調律)は非常に重要な作業である。一般的な演奏家は、チューナーやピアノの基準音に合わせて楽器を調整するが、絶対音感を持つ人にとって、チューニングは単なる作業以上の意味を持つ。
ピアノの場合、標準的な調律では「A4(ラ)」の音が440Hzに設定される。しかし、オーケストラによっては442Hzや443Hzといった、わずかに高いピッチを基準とすることがある。また、バロック音楽の演奏では415Hz前後の「バロックピッチ」が使用されることもある。こうしたピッチの違いは、絶対音感保持者にとって非常に気になるものなのだ。
特に厄介なのは、長年使用されて音程が狂ったピアノである。調律されていないピアノで弾くと、頭の中で鳴っている「正しい音」と、実際に鳴る音との乖離が大きく、演奏に集中できなくなってしまう。中には、あまりにもピッチがずれたピアノでは演奏したくないと感じる人もいるほどだ。これは、完璧主義というよりも、知覚と現実のミスマッチによる不快感と言える。
また、弦楽器や管楽器の演奏では、チューニングは演奏中も常に意識すべき要素である。気温や湿度の変化、楽器の状態によって、音程は刻一刻と変化する。絶対音感を持つ演奏家は、こうした微妙な音程の変化を敏感に感じ取り、演奏中も常に調整を行う必要がある。アンサンブルで演奏する際には、他の奏者の音程のズレも気になってしまい、音楽を純粋に楽しむことが難しくなることもあるという。
さらに、ギターなどのフレット楽器には「平均律」という妥協的な調律システムが採用されており、純正律で聞こえる「自然な和音」とは微妙にずれた音程で和音が鳴る。絶対音感を持つ人の中には、この「完璧ではない音程」に違和感を覚える人もいる。音楽の美しさを追求するがゆえの、贅沢な悩みとも言えるだろう。
音楽を聴くことが純粋な楽しみではなくなる矛盾
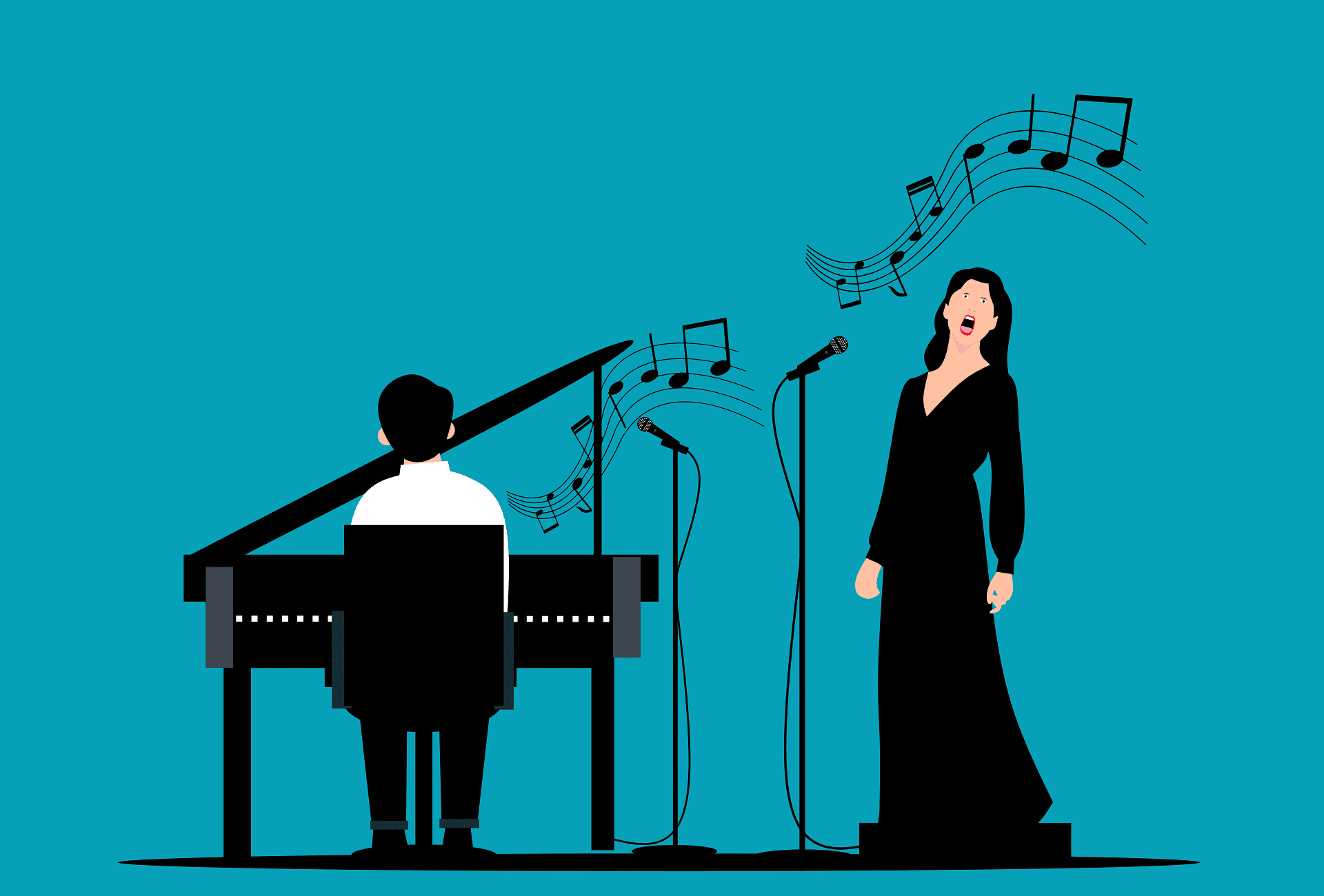
音楽の才能として羨望の対象となる絶対音感だが、皮肉なことに、この能力が音楽を純粋に楽しむ妨げになることがある。分析的に音を聴いてしまうため、感情的に音楽に浸ることが難しくなるのだ。
例えば、友人が勧めてくれた新しいアーティストの曲を聴くとき。多くの人は、メロディーの美しさや歌詞の世界観、全体的な雰囲気を楽しむだろう。しかし絶対音感保持者は、無意識のうちに「このコード進行はII-V-Iだ」「ここでナインスが使われている」「このベースラインは半音階的に下降している」などと分析してしまう。音楽理論的な構造が見えすぎるがゆえに、音楽が持つ感動や驚きが薄れてしまうのだ。
これは、マジックショーを見ているのに種が見えてしまうようなものである。トリックが分かってしまえば、純粋な驚きや感動は半減する。絶対音感保持者にとって、音楽は常に「種が見える」状態で、その仕組みが透けて見えてしまうのだ。
また、映画やドラマの劇伴音楽を聴く際にも、この分析的な聴き方が邪魔をすることがある。感動的なシーンで美しい音楽が流れても、「この和音進行はよく使われるパターンだな」「ここでストリングスがクレッシェンドするのは定番だ」などと冷静に分析してしまい、物語への没入が妨げられることがあるという。制作者が意図した感情操作が「手の内」として見えてしまうことで、素直に感動できなくなるのは、なんとも皮肉な現象である。
さらに、ポップミュージックにおいては、音程の「揺れ」や「ニュアンス」も重要な表現要素である。感情を込めて歌う際の微妙なピッチの不安定さ、ブルージーなベンド、ジャズのスウィング感。こうした「正確ではない」表現が、かえって音楽に命を吹き込むこともある。しかし、絶対音感が強すぎると、こうした表現的な音程のズレが「間違い」として聞こえてしまい、演奏の良さを素直に受け取れないことがあるのだ。
日常生活の中で「音」から逃れられない宿命
絶対音感を持つ人々の困りごとの根底にあるのは、「音から逃れられない」という事実である。視覚情報は目を閉じれば遮断できるが、聴覚情報は耳を塞いでも完全には遮断できない。そして、耳に入る全ての音が音名として認識されてしまう絶対音感保持者にとって、これは24時間365日続く状態なのだ。
静かな図書館で勉強しているとき。空調の微かなモーター音が「ソ#」として聞こえ、隣の席の人のペンが紙を走る音がリズミカルな音列として認識される。カフェで友人と会話を楽しんでいるとき。BGMの音楽はもちろん、エスプレッソマシンの蒸気音、食器がぶつかる音、他のテーブルの笑い声が、全て音程を持った情報として脳に流れ込んでくる。
就寝時も例外ではない。寝室の小さな音、隣家から漏れ聞こえるテレビの音、遠くを走る車の音。こうした音が全て音名として認識されるため、なかなか寝付けないという人もいる。特に神経質な性格の絶対音感保持者にとって、音の洪水の中で心を静めることは、大きな挑戦なのだ。
この「音から逃れられない」状態は、ある種の感覚過敏とも言える。近年注目されている「聴覚過敏」とは異なり、音の大きさではなく「音の情報量」が過多になっている状態である。脳は常に音を処理し続けなければならず、それが慢性的な疲労の原因となることもある。絶対音感は才能であると同時に、日常的に背負い続ける十字架でもあるのだ。
絶対音感がもたらす豊かさと代償
ここまで、絶対音感がもたらす様々な困りごとを見てきた。音程のズレへの敏感さ、日常音の音楽化、分析的な聴き方による感動の減少。これらは、この特殊な能力を持つ人々が日常的に直面する現実である。
しかし、絶対音感が全くの不便であるわけではない。音楽の記憶力は抜群で、一度聴いた曲を正確に再現できる。楽譜がなくても耳コピが容易にでき、作曲や編曲の際には大きな武器となる。音楽教育の現場では、生徒の音程の間違いを瞬時に指摘できる。プロの音楽家にとって、絶対音感は確かに有用なツールなのだ。
問題は、この能力が「オンオフできない」ことにある。必要なときだけ使える便利な道具ではなく、常に稼働し続ける自動システムなのだ。それゆえに、音楽に関係ない日常生活においても、絶対音感は働き続け、時に煩わしさをもたらす。
また、絶対音感の「質」にも個人差がある。全ての音が瞬時に音名で認識される強固な絶対音感を持つ人もいれば、ピアノの音など特定の音色に限定される人もいる。さらに、年齢とともに基準ピッチがずれていく「老化性絶対音感」という現象も報告されている。自分の中の「A音」が徐々に上がったり下がったりすることで、外界の音とのズレが生じ、新たなストレスの原因となることもあるのだ。
まとめ|才能と向き合いながら生きる人々の知恵
絶対音感を持つ多くの人々は、この能力と折り合いをつけながら生きている。完全に苦痛なわけではなく、むしろ世界を豊かに感じられる側面もある。彼らは様々な工夫をしながら、才能の恩恵を享受しつつ、その代償を最小限に抑える方法を見出しているのだ。
例えば、音楽を聴く際に意識的に「分析モード」をオフにし、感情的に音楽を楽しむ訓練をする人もいる。また、日常生活では音楽的でない環境音をできるだけ気にしないよう、心理的な「フィルター」をかける技術を身につける人もいる。瞑想やマインドフルネスを取り入れ、音への過度な反応をコントロールする方法を学ぶケースもある。
音楽家として活動する絶対音感保持者の中には、この能力を「ツール」として客観視し、必要に応じて活用するという姿勢を持つ人もいる。演奏や作曲の際には絶対音感を最大限に活用し、音楽を聴いて楽しむ際には相対的な音の関係性に注目するなど、場面に応じて意識の向け方を変えるのだ。
結局のところ、諸刃の剣であるこの絶対音感、音楽家にとっては強力な武器となり得るが、日常生活においては予期せぬ困難をもたらすこともある。しかし、この特殊な知覚を持つ人々は、その特性を理解し、上手に付き合う方法を見出しながら、私たちとは少し異なる音の世界を生きている。彼らにとって、世界は常に音楽的な意味を帯びた、特別な場所なのである。
2