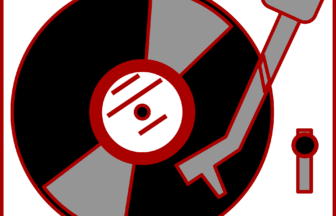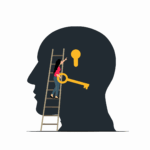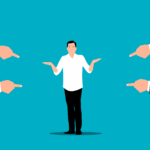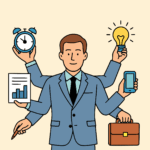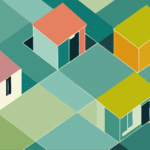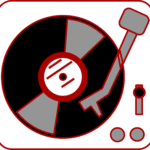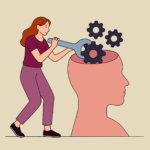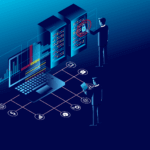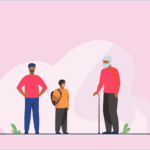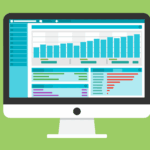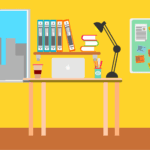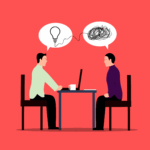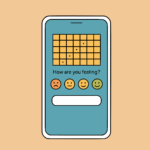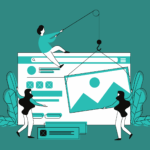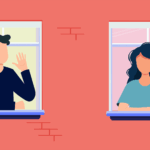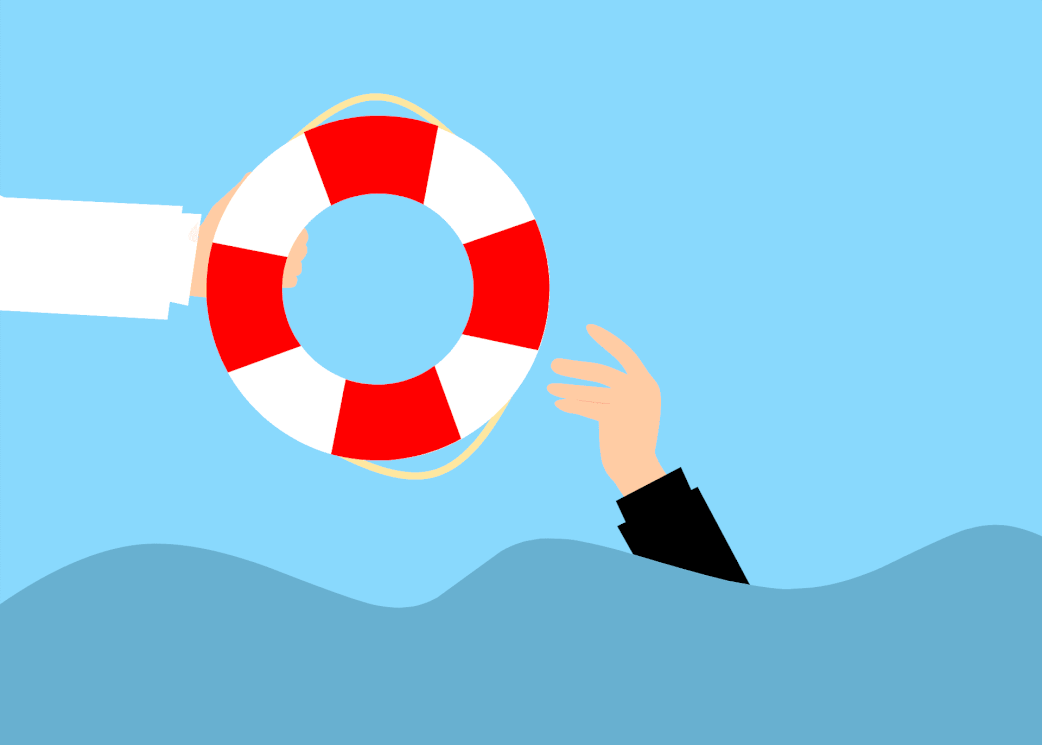
極限状態が引き出す謎の能力
「母親が燃える家から車を持ち上げて子どもを救出した」という類いの話を耳にしたことがあるだろうか。通常では考えられない力を発揮する現象、いわゆる「火事場の馬鹿力」は、古今東西で語り継がれてきた人間の不思議な能力だ。しかし、この現象は単なる都市伝説なのだろうか。それとも、私たちの身体に本当に隠された能力が眠っているのだろうか。
この問いは、単に生理学や心理学の領域にとどまらない。むしろ、人間存在そのものの本質に関わる哲学的テーマである。なぜなら、火事場の馬鹿力という現象は、「人間とは何か」「私たちの可能性の限界はどこにあるのか」「理性と本能の関係性はいかなるものか」といった根源的な問いを投げかけてくるからである。
身体に刻まれた「リミッター」の謎
人間の筋肉は、実は普段の生活で使っているよりもはるかに大きな力を発揮できる潜在能力を持っている。スポーツ科学の研究によれば、私たちは通常、筋肉が持つ最大出力の30〜40%程度しか使用していないという。では、なぜ身体は自らの能力を制限しているのか。
この問いに対する答えは、進化生物学的な視点から見ると実に興味深い。筋肉が全力を出し切れば、腱や骨格、関節への負荷が極端に高まり、自らの身体を破壊してしまうリスクがある。つまり、脳は筋肉を守るために、意識的に出力を制限しているのだ。これは生存戦略として極めて合理的である。日常生活で全力を出し続けていたら、すぐに身体が壊れてしまうからだ。
しかし哲学的に考えると、ここには深いパラドックスが潜んでいる。私たちの身体は「自己保存」のために力を制限しているが、同時に「生命の危機」においてはそのリミッターを解除する。つまり、身体は「今を守る」ことと「究極の瞬間に全てを賭ける」ことの間で、常に微妙なバランスを取っているわけだ。この二重性こそが、人間存在の根本的な構造を示唆している。
アドレナリンという名の「覚醒スイッチ」
火事場の馬鹿力を生理学的に説明する際、必ず登場するのがアドレナリンという神経伝達物質だ。危機的状況に直面すると、副腎からアドレナリンが大量に分泌され、心拍数が上昇し、血流が増加し、痛覚が鈍くなる。さらに、普段は使われない筋繊維まで動員され、通常を超えた力が発揮される。
だが、ここで注目すべきなのは、アドレナリンが単なる化学物質ではなく、人間の「存在様態」を根本から変容させる触媒として機能している点だ。フランスの哲学者メルロ=ポンティは、身体を「世界への存在」として捉えたが、アドレナリンの分泌は、まさに私たちの「世界への関わり方」そのものを変えてしまう。
普段の私たちは、理性によって世界を把握し、計算し、予測しながら行動している。しかし極限状態では、そうした思考のプロセスが圧縮され、身体が直接的に世界と対峙する。言い換えれば、「考える存在」から「行為する存在」へと、人間の在り方が根本的にシフトするのだ。この変容は、単に力が強くなるという以上の、実存的な転換を意味している。
時間感覚の歪みと「フロー状態」の哲学
火事場の馬鹿力と並んでよく語られるのが、極限状態における時間感覚の歪みだ。事故の瞬間がスローモーションで見えた、数秒の間に膨大な思考が駆け巡ったという体験談は枚挙にいとまがない。この現象は、私たちの「時間経験」が決して客観的なものではなく、意識状態によって伸縮自在であることを示している。
心理学者チクセントミハイが提唱した「フロー状態」という概念は、ここに接続する。フローとは、課題と能力が完璧にマッチし、自己意識が消失して活動そのものと一体化する状態を指す。アスリートが語る「ゾーン」も同様の体験だ。火事場の馬鹿力は、このフロー状態が生死の境界線で極限まで強化されたものと考えることができる。
ここには、ハイデガーの「時間性」の概念を重ねることができる。ハイデガーにとって、本来的な時間とは時計の針が刻む均質な時間ではなく、人間が自らの存在可能性に向かって企投する「実存的時間」だった。火事場の馬鹿力が発揮される瞬間、人は未来への可能性(生き延びること、他者を救うこと)に全存在を賭ける。その時、時間は引き延ばされ、一瞬が永遠のような密度を持つのだ。
恐怖を超えた先にある「勇気」の本質
見落とされがちなのが「恐怖」という感情の役割である。通常、恐怖は私たちを萎縮させ、身体を硬直させる。しかし、ある閾値を超えると、恐怖は逆に行動の原動力へと反転する。この逆説的な転換は、勇気という徳の本質を照らし出す。
アリストテレスは『ニコマコス倫理学』の中で、勇気を「恐怖すべきものを恐怖しつつも、それでも立ち向かう」態度として定義した。つまり、真の勇気とは恐怖の不在ではなく、恐怖の只中での決断なのだ。火事場の馬鹿力が発揮される状況では、人は極度の恐怖を感じながらも、それを突き抜けて行動する。このとき、身体は恐怖というエネルギーを推進力に変換しているのだ。
さらに、多くの証言で「無我夢中だった」「何も考えていなかった」と語られることだ。これは、意識的な決断のプロセスを経ずに身体が動いていることを示唆している。いわば、恐怖と勇気が思考を媒介せずに直結し、理性を迂回した回路で行動が生起する。ここに、人間の道徳性や倫理が、必ずしも理性的熟慮に基づくものではないという洞察が得られる。
他者のための力|利他性と超越の契機
火事場の馬鹿力にまつわる物語の多くは、自分自身のためではなく、他者を救うために発揮されている。母親が子どもを救うため、見知らぬ人が事故に遭った他人を助けるために、通常を超えた力を出す。この事実は、人間存在の根底に利他性が組み込まれていることを示唆している。
フランスの哲学者レヴィナスは、他者の顔との出会いが倫理の起源であると論じた。他者の苦しみや困窮が私に向けられる時、私は応答する責任から逃れられない。火事場の馬鹿力は、この倫理的呼びかけに対する身体的応答だと解釈できる。つまり、他者の危機が私の身体そのものを変容させ、通常の限界を突破させるのだ。
ここには、個人と他者の境界が曖昧になる瞬間が捉えられている。私たちは通常、自己と他者を明確に区別して生きているが、極限状態では「他者を救うこと」が「自己を保存すること」と同一の緊急性を帯びる。この瞬間、人間は自己の閉じた殻を超えて、他者と繋がった存在として自らを実現する。火事場の馬鹿力は、人間の孤立した個としての側面ではなく、関係性の中で生きる存在としての側面を鮮やかに浮かび上がらせるのだ。
1
2