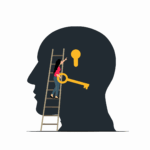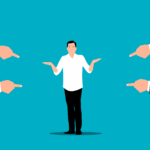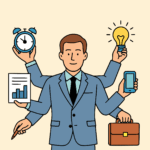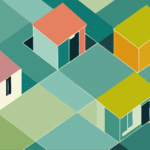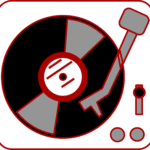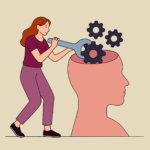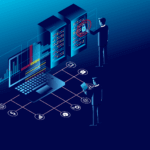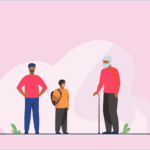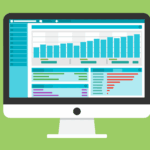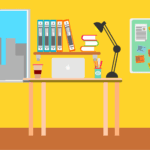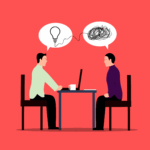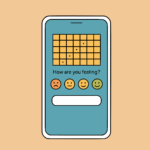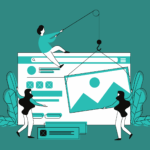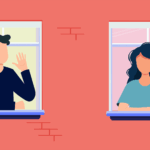天下りという名の日本的慣習がもたらす闇
天下りとは、中央官庁や地方自治体の官僚が退職後に関連企業や外郭団体に再就職する慣習を指す。建前上は「専門知識の活用」や「官民交流の促進」と説明されるが、実態は権力構造の温存と既得権益の維持にほかならない。この慣習が生み出す組織的な無駄は、税金の使い道として国民が知るべき重要な問題である。今回は、天下り企業で実際に起こり得る非効率で無駄な事象を徹底的に検証していく。
1. 存在意義が不明な「特別顧問」ポストの乱立
天下り企業で最も象徴的な無駄が、実務を伴わない「特別顧問」や「専務理事」といった肩書きの氾濫である。これらのポストは、退職した役人を受け入れるために新設または常設されることが多く、明確な職務内容も責任範囲も定義されていない。
ある公益社団法人では、特別顧問が5人も在籍しているにもかかわらず、彼らが具体的に何をしているのか現場の職員すら把握していないという事例がある。月に一度、2時間程度の会議に出席するだけで、年間1000万円以上の報酬を受け取るケースも珍しくない。時給換算すれば40万円を超える計算だ。
問題なのは、これらの顧問が実際の経営判断や業務改善に寄与しているかというと、ほとんど貢献していない点である。会議では当たり障りのない一般論を述べるだけで、具体的な提案や改革案を出すことはない。なぜなら、彼らの真の役割は「仕事をすること」ではなく「そこに居ること」だからだ。官公庁とのパイプを維持するための人的担保として、ただ籍を置いているに過ぎない。ただ一方ではそういったポストも必要という見方もあるのだが、税金運営を幹とする外郭団体であれば尚更、今の時代の「考えて動く・実力経済」においては無駄と言わざるを得ないだろう。
2. 意思決定の階層が増えすぎて何も決まらない会議地獄
例えば天下りにより上層部が肥大化した組織では、意思決定プロセスが異常に複雑化する。元官僚たちは役所時代の慣習を持ち込み、何事も「稟議」と「根回し」を経なければ進まないシステムを構築する。
例えば、わずか10万円の備品購入を決めるのに、担当者会議、課長会議、部長会議、理事会議、そして最終的に特別顧問への報告という5段階もの承認プロセスを経る組織がある。それぞれの会議で資料を作成し、説明し、質疑応答に対応しなければならない。結果として、決定までに2ヶ月を要し、現場が必要としていたタイミングはとうに過ぎ去っている。
さらにこうした多層構造の中で誰も責任を取らない体質が定着することだ。各階層の人間は「上に報告した」という事実だけで自己の責任を免れたと考え、最終決定者も「下から上がってきた案件だから」と責任を回避する。結果、誰も本気で検討せず、リスクを恐れて革新的な提案はすべて却下される。組織全体が思考停止状態に陥るのである。
3. 実態のない「調査研究事業」への予算垂れ流し
天下り企業、特に外郭団体でよく見られるのが、実効性の疑わしい「調査研究事業」の乱発である。これらの事業は、組織の存在意義を示すための看板として掲げられるが、その成果が実社会で活用されることはほとんどない。
ある団体では、毎年数千万円の予算を投じて「○○産業の将来展望に関する調査研究」を実施している。しかし、その報告書は誰に読まれることもなく、関係機関に配布されて終わりだ。内容も外部の受託会社に丸投げした二次情報の寄せ集めで、独自の視点や新規性はほぼゼロである。
問題の本質は、こうした調査研究が「仕事をしている証拠」を作るためだけに存在している点にある。天下り役人たちは、自分たちの存在意義を正当化するために、何らかの事業実績を示す必要がある。しかし、民間企業のように利益を生み出す必要はないため、形だけの調査研究でお茶を濁すのだ。
そして翌年になると、ほぼ同じテーマで「継続調査」という名目で再び予算が計上される。前年度の調査結果を踏まえて何かが改善されるわけでもなく、ただ予算消化のサイクルが永遠に続くだけである。そんな予算は、公共福祉に回した方が遥かに社会に役立つ。
4. 天下り官僚のための豪華すぎるオフィス環境整備
役員室の豪華さも一般職員のそれと比べて格差がある。元役人たちは、役所時代に享受していた「特別扱い」を民間でも当然のように要求する。
問題は、これらの整った設備がほとんど使われていない点だ。月額数十万円のオフィス賃料を考えれば、これほど非効率的な空間利用はない。
加えて、役員専用の公用車やハイヤーチケットも用意される。「要人としての体面を保つため」という理由だが、実際には近距離の移動にも惜しげもなく利用され、年間の交通費が一般職員の数倍に達するケースもある。
5. 既存業者との癒着による競争原理の完全崩壊
天下り役人が企業に持ち込む最大の弊害の一つが、特定業者との不透明な関係である。官僚時代に関わりのあった企業や団体を優遇し、公正な競争入札を形骸化させるケースが後を絶たない。
例えば、システム開発の案件で「仕様書が特定ベンダーの製品でなければ実現できない内容」になっていたり、コンサルティング業務の発注で「実質的に応募できる企業が1社しかない条件」が設定されていたりする。表向きは競争入札の形式を取りながら、実態は出来レースなのである。
こうした癒着により、本来であれば半額で実施できる業務に倍の予算が投じられる。業者側も「天下り先だから」という理由で高額な見積もりを提示でき、双方にとって美味しい関係が成立する。しかし、そのツケを払わされるのは最終的に国民や利用者である。
さらに既存業者との関係を重視するあまり、新規参入や技術革新を拒絶する体質が生まれることだ。より安価で優れたサービスを提供できる新興企業が現れても、「実績がない」「信頼性に欠ける」といった理由で排除される。組織全体が既得権益を守ることだけに注力し、利用者の利益は完全に無視されるのである。
1
2